エッセイのご感想がありましたらフォームより送信ください。
各エッセイは筆者個人の意見であり、REDDYの見解とは必ずしも一致しません
母が私を出産した時、大量の出血があった。母子ともに命に別状はなかったが、母は二度と子供が産めない体になった。生後40日目に、40度の高熱を出した。脱水症状があり、危険な状態が続いたが、しばらくして回復した。
初めて生まれたわが子を抱いて、母は北海道の実家に帰省した。
「母ちゃん、歩、連れてきたど~」
荷物と私を抱えた母が、祖母を呼ぶ。
「よくけえってきたな~」
祖母は洗い物の手を止めて、玄関まで母を迎えに来る。
「母ちゃん、歩を抱っこしてくんろ」
母が私を祖母の胸に預ける。
「ああ、めんこいなあ」
私を抱いた祖母はほほ笑みながら私をあやす。
その時、ふと、私の異常に気が付いた。
「この子の足、なんかおかしくないかい?」
私の足は左足だけ変に浮いていた。
不安になった母は東京に戻ると、私を大きな病院に連れていき、検査を受けさせた。そこで小児麻痺という診断が下りた。
小児麻痺は時々、発作が起きる。それが起こる前は、決まって胸の中がざわざわする。
「お父さん」
私は父の所へ行き、身体をピタリとくっつける。
そうすることで、発作を鎮めようとするが、それをあざ笑うかのように身体が硬直する。
呼吸が上手くできず、手足が思うように動かない。
「大丈夫、大丈夫。歩は強い子だ」
父が私の体をさすりながらそう繰り返す。私はじっと耐えた。
小学校は普通科へ行ったが、小児麻痺の私は学校で浮いていた。友達がいない学校生活は惨めだった。
母は看護師をしており、夜は家にいないことが多い。私の面倒をみるのはもっぱら父の役目だった。
共働きで障害のある子供を育てる生活に、2人とも不満が溜まっていったのだろう。父と母は顔を合わせると、口げんかをすることが増えた。そして、私が小学校3年生の春休みに、母が大きな荷物を抱えて、家を出て行った。
「お父さん、お母さんはどこへ行ったの?」
「アメリカに行ったんだ」
馬鹿な私は父の言葉を信じ切っていた。
両親が離婚して、私は父に引き取られた。そしてすぐに新しいお母さんが来た。
しばらくして、障害者手帳を取得した。左半身の麻痺が普通の生活を送るのに障壁になっていると認められたのだ。学校も養護学校に変わった。
その後、義母が妊娠し、弟が生まれた。父と義母は弟に夢中だった。
私は養護学校に行く定期券で駅の改札を通ると、学校へ行かず、新宿に向かった。そして、特急列車に乗った。しかし、新横浜あたりで駅員に見つかってしまう。
駅員から家に連絡が行くと、父が迎えに来る。父はブスッとした表情をしていたが、私は父を独り占めできて嬉しかった。
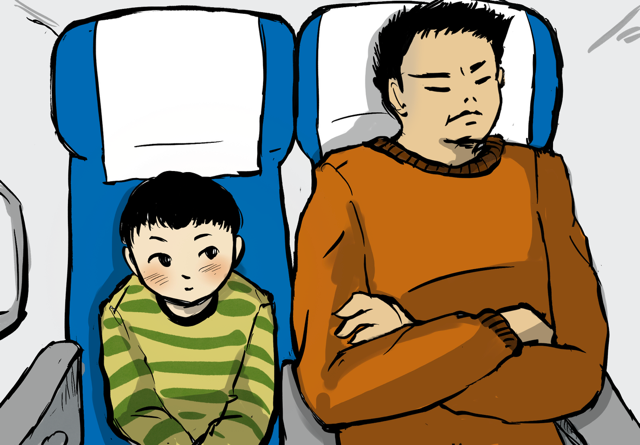
義母はその後も妊娠し、妹を出産した。私は家に帰りたくなくて、また新宿に行き、特急列車に乗った。今回は終点の長野まで行った。
電車を降りて、駅を出ようとしたとき、無賃乗車で捕まった。私は警察に引き渡された。
「靴下とベルトを寄こせ」
黙って靴下を脱ぎ、ベルトを外す。
「ズボンのベルト通しのところに、安全ピンがついてるな。それも取れ」
ベルト通しの紐が千切れていたので、それを留めていただけなのに没収された。
その後、個室に入れられ鍵を閉められた。壁には鉄格子がはめられている。
トイレに行きたくなったので、素直に「トイレに行きたい」と警官に言った。
「馬鹿言うな」
「じゃあ、ここでするよ」
「本当にしたら怒るぞ」
「するったらする」
「仕方ねえなあ」
警官は折れて、私をトイレに連れて行ってくれた。
夜遅く、父が東京から私を迎えに来た。警官に父は何度も頭を下げ、私にも頭を下げさせた。
その日の最終列車に乗り、父と一緒に東京へ帰る。父は私の方を見もしない。それでも、私は父と一緒に居られることに幸せを感じていた。それくらい、私は愛情に飢えていた。
長野までの無賃乗車事件の後も、私は勝手に特急電車や新幹線に乗って、父を困らせた。
「なあ、どうしたら止めてくれるんだ?」
「あずさ号に乗って、お父さんと旅行に行けたらもう二度とやらない」
その後、父は休日に長野へ私を連れて行ってくれた。列車はもちろんあずさ号だ。
私は約束通り、無賃乗車して遠くに行くことを止めた。
ある日、父が神妙な顔つきで、私に言った。
「歩、悪いけど、これからはお母さんと一緒に暮らしてくれ。実は、お母さんは隣町に住んでいる。向こうも歩と暮らしたいそうだ。ここ数年、歩と暮らして良く分かった。子供には父親よりも母親の方が必要なんだ」
私は父の気を引きたくて特急電車に乗ったことを後悔した。しかし、後の祭りだ。
小学6年生になった時、母が私を引き取りに来た。昔は地味だった母が、紫色のニットにヒョウ柄のコートを羽織って現れたので私はギョッとした。どうやら、看護師をやめて水商売を始めたという。貯めたお金で自分のお店を開いたそうだ。お酒を提供しているだけで、変なことはしてないよ、と笑った。
「歩、お母さんが帰るのは深夜12時過ぎるけど、何かあったらお店に電話しなさいね」
母は大ぶりのイヤリングをつけ、胸の開いたワンピースを着て、ファーコートを羽織る。
私は母を見送ると、1人で食事を取り、テレビをつけた。
来年は、とうとう中学生になる。母が頑張って普通科の中学校に行けるよう、手配してくれた。
洗濯物を右手でだけで、取り込み、左手を添えながらたたむ。障害は固定化してきて、これ以上、良くなる気配はなかった。
春になり、中学校に入学した。学ランを切ると少し大人になった気持がする。友達ができることを期待していたが、友達ができるどころか、私の身体を理由にしたいじめが始まった。
汚い言葉を言われるのはマシな方で、酷いのになると、美術のテストの時間に私の身体を持ち上げて頭から床に落とした。私は脳震盪を起こして何も絵が描けず0点を取った。いじめは中学を卒業するまで続いた。
高校は商業科に進学した。中学の時とは打って変わって、楽しい毎日が始まった。友達がたくさんでき、放課後になると、私の家はたまり場になった。
「買ってきたプレイボーイ読もうぜ!」
男向けの週刊誌にはきわどい女性のグラビアが載っている。
「見ろよ、これ、たまんねえな」
高校生の私たちは興味津々でページをめくる。
「なあ、歩、この漫画読まして」
他の奴は私の本棚から漫画を漁る。みんなそれぞれ好き勝手にたわいもない話をしながら過ごした。
母の仕事が軌道に乗り、郊外に一戸建てを購入したのもあり、広い我が家は格好のたまり場になっていた。店が休みの時は母がみんなに夕食をご馳走した。
笑い声が家中に溢れていた。
高校のクラブ活動は旅行研究会に入った。入部理由は、いろんなところに行けて楽しそうという軽い気持ちからだった。
クラブ活動として、春休みと夏休みに日本三景を巡った。
松島の太平洋、天橋立から望む日本海、宮島を中心とした瀬戸内海は穏やかで心が和らいだ。思い返すと、私がした最初の旅行は父を独占するためだった。しかし、本来の旅とはその土地や文化を楽しむものだ。それを、私はこの旅で学んだ。
旅行研究会の部長は、旅行に関する仕事に就きたいと言って、高校卒業後は大手旅行会社に就職した。その姿を見て、私も部長と同じ会社に行きたいと考え始めた。
私は高校卒業後、専門学校に通い、その後、旅行会社に就職が決まった。先輩と同じ大手旅行会社は無理だったが、満足のいく就職先だった。障害があったが、健常者に負けないくらい働いた。
この頃は仕事が終わると、毎日、居酒屋に飲みに行った。家に帰ってからも飲み続けた。1日に飲む量はビールの大瓶4本。5本だと次の日に響いてしまうのが、飲んでいて分かったからだ。
そうやって生活しているうちにお金が足りなくなり、サラ金に通い始めた。
サラ金と言ってもいかがわしい様子は全くなく、銀行のように清潔な店内には、これまた銀行のようにしゃんとした女性の店員が座っている。
書類に記入し、保険証を見せて身分照会をすると、会社に在籍しているかどうかの連絡がいく。確認が取れると5万貸してくれた。
最初はすぐに返せると思っていたのだが、利息しか返せず、元本が減らない。
酒に金を使うのを止めればいいのだが、頭の中はアルコールの事でいっぱいだ。
仕事中、アルコールの禁断症状で指が震え、英文タイプが上手く打てない。
数年後、借金の額は300万にまで膨らんだ。
にっちもさっちも行かなくなった私を助けてくれたのは母の彼氏だった。
私の借金が発覚したその日に300万をポンと用立ててくれた。
母も私のことを心配して店をたたんだ。それ以来、一滴も酒は飲んでいない。
その後、人間関係が嫌になり、会社を辞めて人材派遣会社に登録し、旅行の添乗員を始めた。同年代が結婚していく中、私は実家で母親と暮らしていた。その母が卵巣がんになり、53歳という若さであっという間に亡くなった。
お店を経営していたせいか、母の葬儀にはたくさんの弔問客が来た。その中に、母の元夫である私の父親もいた。
父と顔を合わせるのは何年ぶりだろう。しかし、話したいことが何もない。他人行儀な挨拶をして私たちは別れた。
母が亡くなったので、一戸建てを売り、私は賃貸のマンションに引っ越した。
添乗員の仕事は楽しいが体力を使う。
北から南まで飛び回り、分厚い参加者名簿を見ながら、一人ひとり連絡する。
小児麻痺の影響もあり、体力的に限界を感じ、仕事を辞めた。
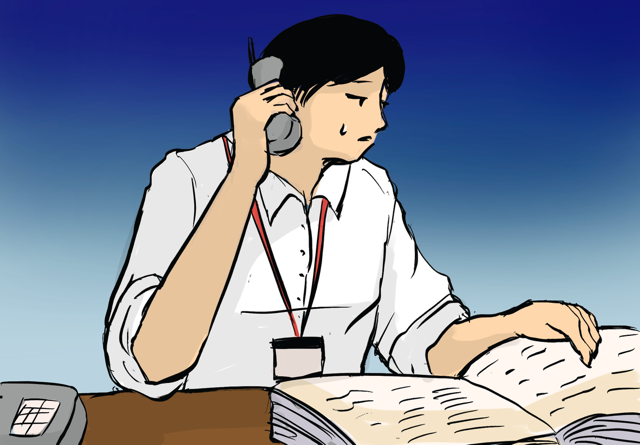
その後は旅行会社の営業をしたが、疲れてしまって家に帰ると何もできない。この働き方を続けていたら、きっと私は長く持たない。
正社員にこだわるのはやめよう。そもそも、私は障害者なんだ。障害者の働き方というのがあるはずだ。
職安で障害者雇用の仕事を探し、スーパーの商品管理の仕事に就いた。
障害者雇用だから、障害者に優しい仕事だと想像していたが、全くそうではなかった。
私は、1年でスーパーの仕事を辞め、次は営業の仕事をしたが、こちらも体に応えた。
ある日、張り詰めていた糸がぷっつりと切れた。働くのをやめよう。私は今まで、たくさん頑張った。貯金は十分ある。残りの人生は好きなように生きよう。
それから私は、海外旅行にたくさん行った。
ハワイ、台湾、フィリピン、グアム、サイパン。
美しい海と、日本ではお目にかかれない珍しい料理。英語の看板が並んだショッピングモールでは、あちこちから外国語が聞こえてくる。
海外から日本に戻ると、見慣れた日本の風景はアジアの小国のものだと思い知らされる。
自分が生きている世界は大きいようで小さい。
旅行に行かないときは、家でダラダラと過ごした。1人というのは気楽だが、少し寂しい。
ある日、携帯電話に知らない人からメールが来ていた。
「はじめまして。メル友にならない?」
携帯電話が普及し始めた頃、メル友を探すために、適当な番号にメールを一方的に送るのが流行っていた。
いつもなら無視するのだが、この時はなんとなく「いいよ。メル友になろう」と返信した。
メールの相手は20代の女の子で名前は愛美と言った。
愛美からのメールは「暇してる」「お腹空いた」「今日天気良くて嬉しい」などのたわいもないものだったが、私の孤独な生活に色どりをくれた。
メールの着信音が鳴ると嬉しくなり、すぐに携帯を開いて返事を打つ。愛美からの返事が来るまで小さい液晶画面で携帯サイトを眺めていると、ピロリンと着信音が鳴り、私の胸は高鳴った。
ある日、愛美から「お母さんにメル友がいること話した。同じくらいの年齢だからやってみたらって勧めたよ」とメールが来た。その後、愛美の母親ともメールをするようになる。
愛美からこんなメールが来た。
「ねえ、今度、お母さんと愛美と一緒にご飯しない?」
私は直ぐに「もちろん行くよ」と返事を出した。
週末、都内のファミレスで愛美親子と食事をした。愛美は若さもあってか、コロコロと笑ってばかり。母親も娘に負けないくらい大声で笑う。私は久しぶりに楽しい夜を過ごした。
その後、愛美の母親と急速に親しくなり、母親は離婚して、私の家に来た。子供は3人とも成人しているので母親の行動に、一切、口を出さなかった。
1年後、私は愛美の母親と正式に籍を入れた。
45歳になって、誰かと結婚するとは思わなかった。自分でも、障害者である私は結婚とは無縁だと、どこかで考えていた。
妻との生活は楽しかった。しかし、他人と暮らすのが初めての私は、気に入らないことがあると、つい、怒鳴ってしまう。
洗濯物が溜まっている、食事の味付けが濃い、床にゴミが落ちている。他人からしたら些細なことだが、なぜか、自分はそれを許すことができず、火が付いたように怒鳴り散らしてしまう。そのうち、妻はノイローゼになった。
妻が仕事に行けなくなり、収入が途絶えた私たちは、生活保護を受けることになった。
その後、精神科に行った妻は統合失調症という診断を受けた。
「あなたも精神科に行って欲しいの。お医者さんに夫と喧嘩していると話したら、ぜひ連れてきてくださいって」
私が妻の言葉に従い、一緒に精神科に行くと、軽いうつ病と診断され、薬が少し出た。
薬を服用するようになってから、よく眠れるようになり、喧嘩も落ち着いた。
そんな時、愛美が一緒に暮らしたいと連絡を寄こしてきた。無下にすることもできず、愛美と養子縁組をし、3人で暮らすことになったが、その後、愛美はメールで知り合ったおじいさんと暮らすと言って家を出ていった。
また、妻との2人の暮らしが始まり、それと同時に、怒鳴り散らす癖も再発した。
妻は年中「眠れない」とつぶやき、精神科で大量の薬をもらってきた。そして、処方された2週間分の薬をすべて飲んだ。病院で治療してもらい、体調が回復しても、しばらくすると、また多量服薬をする。何回も繰り返すので、こちらも慣れてきてしまった。
ある日、「眠れない」と訴え続ける妻にとても強い睡眠薬が処方された。真っ赤な、真っ赤な錠剤。妻はそれをまとめて飲んだ。
ある夜、妻の寝室を覗くと、ぐっすりと眠っていた。しかし、多量服薬していると知らず、放っておいた。夜も遅いので、自分も薬を飲んで寝た。
次の日、妻はいびきをかいて昼過ぎまで寝ていた。きっと疲れているのだろうと思い、そのままにしておいた。
しかし、次の日になっても起きない。不審に思い、妻の口元に顔を近づける。昨日まであった呼吸がなくなっていた。大急ぎで119番する。
「妻が眠ったまま、息をしていないんです!」
「これから向かいます。それまで心臓マッサージをしてください」
「私は左手が不自由なので、できません!」
自分が酷くみじめに思えた。右手だけで胸を押し、死なないでくれと願う。窓の外から救急車のサイレンが聞こえる。妻は病院に運び込まれたが、もう、以前のように健康な体で家に戻ることはできなかった。
「延命治療を行う病院に移るか、一般の病院にするか、ご主人が決めてください」
妻の腕、口、足の付け根、様々な場所に管が刺さっていた。その姿があまりにも可哀そうで、見ているだけで胸が苦しかった。延命治療をするということは、一生妻が管だらけだということだ。それは受け入れられない。せめて、最後くらいは何もつけず、綺麗な姿のままでいて欲しい。
「一般の病院にしてください」
妻から全ての管が外され、その場で死亡が確認された。私は大粒の涙を流して泣いた。なぜ、気が付けなかったのか。いや、そもそも、私と結婚しなければもっと長生きできたはずだ。
妻の三女の夫が警察で働いている関係で、妻の死は私が伝えるより早く、子供たちに知らされた。愛美だけは連絡が取れなかった。長女と三女は私を酷く責めた。
生活保護を受けていて、家族が亡くなった場合、葬祭扶助を利用すれば、葬儀に関する費用を出してもらうことができる。お寺に行くときに、自分の家が墓を持っていることを話し、妻を家の墓に入れることになったのだが、これがいけなかった。葬祭扶助からは戒名や墓石に名前を彫るお金は出してもらえない。何十万ものお金を今の暮らしで用立てることは不可能だ。
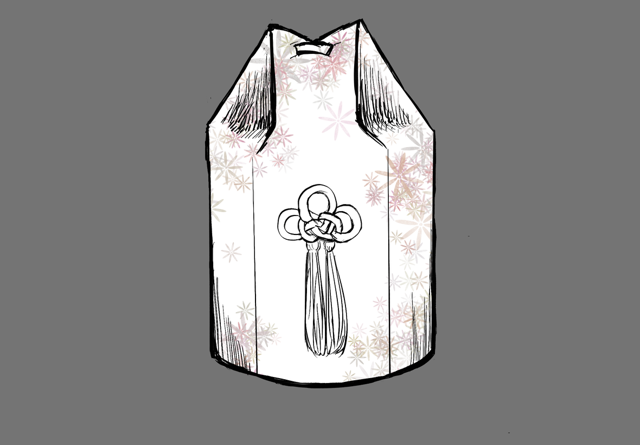
どうしようもできない私は、妻の遺骨を自宅に持ち帰り、ずっと手元に置いていた。6年後、妻の長女から電話が来た。
「お久しぶりです。まだ、お母さんの遺骨はお墓に入ってないんでしょうか?」
私は答えることができず、黙りこくっていた。
「お母さんが夢に出るんです。お墓に入れなくて悲しいって泣くんです。お墓のことは、こっちで何とかするから、遺骨を送ってください。それと、もう二度と、うちの家族には関わらないで下さい」
私は骨壺が割れないように、タオルで何重にも包んで段ボールに入れた。
「何もしてやれなくてごめんな」
そうつぶやいて、ビニールテープでビリリと封をした。遺骨を宅急便で送った人間なんて、この世で私だけかもしれない。
妻の遺骨がなくなってから、自分の胸にぽっかりと大きな穴が開いた。私はなぜ、妻の苦しみを分かってやれなかったのか。妻を自殺にまで追い込んだ自分には生きる価値などないのではないか。
妻の真似をして、医者から処方された睡眠薬と精神薬を多量服薬した。しかし、倒れている私を訪問看護師が発見し、そのまま病院に送られた。
退院する時、迎えに来てくれたケースワーカーがこう言った。
「1人で暮らすのは不安でしょう。救護施設というところがあるんですよ。生活保護を受けながら暮らすことができて、スタッフもついています。ほら、ここです」
車窓越しに大きな敷地内に建てられている3階建ての建物が見えた。もう、1人で暮らすのは限界かもしれない。
見学と一時入所を経て、正式に救護施設に入所した。
救護施設で暮らし始めてから、1人で暮らすよりも大きな安心に包まれている。しかし、大部屋のため、プライバシーが保てないのが難点だ。
「老人ホームに移りたかったらいつでも言ってくださいね」
施設長は利用者の気持ちを尊重して、そう言ってくれた。老人ホームでは、小さいけれど、個室で生活できるそうだ。
思い返すと、長い人生、様々なものを得て失ってきた。しかし、まだ自分にはこの身体が残っている。私の母が命がけで与えてくれたものだ。
普通の人より劣る身体かもしれないが、この身体は色々なことを教えてくれた。身体の麻痺をからかう人間もいれば、そんなことを気にせず、愛してくれた人がいた。そのことを知れただけで十分だ。
秋の空は高く、どこからか金木犀の香りが漂ってくる。
顔をあげると、柔らかい陽の光が体中に降り注ぐ。
私はそっと目を細めた。

1977年生まれ。茨城県出身。短大を卒業後、エロ漫画雑誌の編集に携わるも自殺を図り退職。
その後、精神障害者手帳を取得。その後、生活保護を受給し、その経験を『この地獄を生きるのだ』(イースト・プレス2017)にて出版。各メディアで話題になる。
その後の作品には『生きながら十代に葬られ』(イースト・プレス2019)、『わたしはなにも悪くない』(晶文社2019)、『家族、捨ててもいいですか?』(大和書房2020)、『私がフェミニズムを知らなかった頃』(晶文社2021)『私たち、まだ人生を1回も生き切っていないのに』(幻冬舎2021)がある。
→エッセイ 私たちが救護施設に出会うまで
→エッセイ 地獄とのつきあい方
最近私は人の助けなしでは生きていけない状況になった。いままでも多少はその傾向はあったものの、なんとかひとりで生きている実感はあった。
明らかに、生活弱者になってから私は一日何回「ありがとうございます」を口にするだろう。家から一歩出ると人々は私を優先してくれる。それは時にはありがたくもあり、ユウツで迷惑であったりもする。人々は優しさのひとつを私にくれる。私は「ありがとうございます」を当り前にお返しする。「ありがとう」の大安売りである。二束三文になってしまった「ありがとう」は私が今後生きていく上で忘れてはいけない言葉として刻み込まれた。
一方でこんな私になんの見返りも期待せず優しく協力をしてくれる人達がいる。「ありがとう」だけでは返しきれない程の誠意だ。でも私は「ありがとう」しか返す言葉を持っていない。なんともどかしいことか。感情を込めてとか笑顔でとかいう人もいる。そんなことは分っているし、やっているのである。二束三文の「ありがとう」にだって笑顔を忘れない。
「ありがとう」の最上級は「ありがとうございます」感謝の気持ちを伝える敬語表現だという。感謝の対象や「いつも」などの言葉を前につけることで、より相手に対する感謝の気持ちが伝わるというが、私にはまだ足りない。私に向けてくれた行為は言葉だけでは応える事ができないのだろうか。言葉の限界なのだろうか。見知らぬ人に言う「ありがとう」と区別したい。二束三文になってしまった「ありがとう」をどうにか、最高級にしたい。私が生きていく上で決して忘れてはいけない言葉のひとつとしての「ありがとう」を伝えたい。と思うが未だ見つからないもどかしさを抱えて生きている。
1960年生まれ。
生まれ育ちも宮城県
大好きだった夫は生まれも育ちも東京都。結婚と同時に仙台市の住民になりました。そんな夫も二年前に旅立ってしまいました。
趣味 食べること
私は脳性まひの障害者である。年齢は71。50歳のときの頸椎症で歩けなくなり、電動車いすを利用するようになったが、手足はそれなりに動かすことができている。この原稿も、最近、指の動きが悪くなり、キーボードの誤打がやたらと多くなったが、パソコンを使って自分で書いている。
現状では、障害の中で私が最も困難を感じているのは言語障害である。私の言語障害は脳性まひに伴う構音障害であるが、その厄介なところは、自分では正しく発音しているつもりであり、自分の耳には正しく聞こえていることである。子供のころには口からわからない発音の言葉を無意識に垂れ流しにしていた。初めてオープンリールのテープレコーダーで自分の声を聴いたときには、普通の発音よりもゆっくりで、メロディーが理解の助けになる歌以外では、言っていることがほとんどわからなかった。そのことをきっかけとして、自分の発音がおかしいということを意識するようになった。それでも、どこかに私の言葉を理解してくれる人はいるもので、小学校のクラスの中にも、教員や他の友達に通訳をしてくれた人が、幼いころから一緒に遊んでいた人を中心として何人かいた。それでも一番理解してくれていたのは母親であった。
中学生になると筆談を併用するようになったが、その中で私は心の交流ができるようにユーモアを最大限意識するようにしていた。そして、筆談を併用することは、高校、大学を経て、60歳で会社を定年退職するまで、店での買い物などの生活に不可欠な部分や趣味関係のグループでの活動なども含めて続いていた。ただ、話題が共通している人や商売関係の人には、筆談の必要はそれほどなかったように思う。書く文字については、それほど読みにくくはなかったと思っている。筆記具の持ち方は、一般人と異なっていた。単純に握っているように見えるらしいが、実際には、掌と指の間に筆記具を挟んで、細かい調整ができるようにしていた。仲の良かった従兄は、その持ち方で書いてみて、結構書きやすいと言ってくれていた。それでも、疲れやすく、きちんとした長文を書くことは苦手であった。JISキーボードのワープロには1983年ごろのかなり早い時期に飛びついた(シャープのWD-500)。使い勝手は、私のゆっくりの発音と、文字を打つことのできる速さがほぼ同じで、快適に感じられ、また推敲した長文がきちんと印字されることもありがたかった。
定年退職の少し前、私は虫歯を何本か抜いた。抜いた部分はインプラントにする腹積もりであったが、担当の歯科技工士から「インプラントは不具合が生じたときに根元から取り換えなければならなくなるので、やめたほうがいい」と言われた。その代わり、入れ歯を作ったが.つけているのが苦しく、外したままになってしまった。
そうなると、従来よりも格段に話がしにくくなり、発音も不明瞭になった。そこで、私は話をするために発音することをあきらめ、ほとんどを筆談によるコミュニケーションに頼ることにした。そのように割り切ってしまうと、緊張して発音するときの顔のゆがみがなくなり、表情が自然になり、また、精神的にも余裕ができ、筆談でのユーモアにも磨きがかかったように思う。そして、このことは、定年退職後の翻訳家・文筆家としてのカネにならない仕事にも大いに役立っていると思う。
3年前、私は、筋力の低下と痛みで、手すりさえ使えずに自宅の廊下に倒れ込み、2か月半入院した。便秘がひどく、体重も60キロ台から20キロ程度激減していたので、悪性疾患を覚悟したが、精密検査では内臓関係に異常はなかった。しかし、入院中のリハビリによっても筋力は回復せず、以前にできていたつかまり歩きができないことは同じであった。また、悪化した機能もあり、手を動かすときに痛みが伴うようになり、字が書きにくくなった。どうしたものかと思っていると、主治医が、おそらく言語療法士と相談して、「あいうえお」の文字盤を作ってくださった。はじめのうちは、漢字を交えることができないので、少し幼稚に感じられ、使うことに抵抗があったが、思ったことを即座に伝えることができるので、意外なほど実用性が高く、退院してからも、自宅を訪問していただいている医療関係者、介護者、そして耳の遠くなった96歳の母親とのコミュニケーションに便利に使っている。それでも将来的には、キーボードの誤打がもう少し少なくなれば、パソコンの画面の文字を特大にして、私からの一方的なチャットのような形式で、多少複雑なコミュニケーションのために使うことができるのではないかと思っている。
母親も含めて、電話が使えないことは、いろいろと不便ではあるが、すべてメールでの連絡対応をお願いしている。どうしても緊急で困ったときには、パソコンの読み上げソフトで何とかしたいと思っている。
近年、新型コロナへの感染を避けるために、私は外出を極端に減らしてきている。最近は少しずつ増やしているが、それでも、3年前の退院以来での外出は10回程度にとどまっている。また、コロナ以前には年何回か行っていた一泊程度の旅行は、身体的な状況という面からも、まだ難しいと思っている。
外出のとき、私はできるだけ介護者を付けないようにしている。電動車いすの操作は上手いつもりである。今のところ、ほとんどが金銭がらみの用事での外出なので、あまり内容を知られたくないということも理由に含まれるが、それ以上に大きな理由として、金融機関等の担当者が私ではなく、介護者のほうにまず声をかけがちなことがある。私としては、車いすに乗っている私の文字通り頭越しに話をされるので、あまり気持ちの良いものではない。相手としては、「ひょっとこ爺さん」に見える私に言語障害ばかりでなく、知的障害もあるのではないかという不安もあるのであろう。まあ、その後、私が、ペンを取り出して筆談を始め、初対面の印象とは異なる「立派な」顧客に変身することでの担当者の態度の変化を観察することも、私の密かで意地悪な楽しみであると言えないこともない。ただ、調子に乗って、わかってもらえることをうれしく思いすぎると、相手に悪意があった場合に詐欺などに引っかかる恐れがあるので、少しの用心は欠かせないと思っている。結局のところ、脳性まひという障害は、容姿、風貌、見かけによる異質性が大きな部分を占めていると私は思っている。このことに関連して、私は興味深い体験をしたことがある。ある障害者福祉関係の集会で視覚障害の人と初対面であったにもかかわらず、全く普通の形で完璧なコミュニケーションができたことである。私としては、筆談ができないので、そのとき言葉を発したのはあきらめ半分で、アセトーゼ型脳性まひ特有の緊張が少なかったこともあるが、それ以上に、相手の人が私の容姿、風貌を知ることがなく、また視覚障害ゆえの研ぎ澄まされた聴覚を有していたということが理由であろうと思っている。
一九五三年二月生。都立武蔵丘高等学校から一浪後、早稲田大学政治経済学部経済学科入学・卒業。金融機関の在宅嘱託として三十四年間実務系の翻訳に携わる。退職後、フリー研究者(バリアフリー旅行、障害学)。翻訳家。
→エッセイ ひょっとこ爺さん徒然の記
妻の運転免許証更新に同伴した。
手際よく、視覚検査、写真撮影、ビデオ講習が行われた。私は車椅子に座って、音楽を聴きながらロビーでずっと待っていた。終わるまで、あまり時間はかからなかった。多くの日本人が、かかわる行政手続きとしては、よくできている制度だと思う。確定申告も免許証の更新並みに簡便になれば内閣支持率もあがるのに、と思った。
昨年、私も更新の通知を受け取った。しかし、外来で、車の運転をシミュレーション装置を使ってリハビリ中だったため、更新を保留したままにしている。脳卒中の後遺症で、右半身に麻痺が残り、車の運転は到底無理だった。
入院の早い段階で、自分が車のハンドルを両手で持てなくなったことを自覚し、いささか、ショックを受けた。車の運転に必要な最低限の滑らかな動きができない。むしろ右手はハンドルを触らない方が無難だ。
ハンドルの左上に球形の補助具を装着し、左手でその球を握ってハンドルの操作を練習することになった。どこまでハンドルをきればいいか、はじめて8か月たつのにまだわからない。ハンドルに角度表示でもあればいいのに、と思う。経験的に会得するのが下手な人間は時間がかかる。
方向指示器も左手でレバーを操作することになった。脳卒中発症時乗っていた車の方向指示器は、ハンドルの左側にあった。だから、まともな左手で方向指示器を操作することになって少しよろこんだ。そうはいっても、ハンドル補助具を握りつつ、方向指示器を上げたり下げたりするのは難儀だった。と思っていたら、乗る予定の車が変わった。方向指示器もハンドルの右側にかわった。やれやれ。右手のリハビリがはじまった。
ブレーキ、アクセルを左足で踏むことになった。左足では踏み込む加減が難しい.微妙な調節を滑らかにするには相当な練習がいる。シミュレーション装置の画面上で、適性位置に停車できるのは稀だ。だいたい早過ぎる。公道上で試せる技量ではない。
不器用を自認する私にとって、この運転リハビリは苦痛以外の何物でもない。
シミュレーション装置のモニターに映る街路を走行すると、次から次へと画面上で事故を引き起こす。
スタートの場面。さあ、始めるぞ、アクセルを踏んで発進だ、と思った瞬間、「発進するときは、右に方向指示器を出してください」 すみません。
再スタートの場面。気を取り直して発進すると、突然、ドシン、後続車に追突される。「ミラーで後方確認してください、この車が接近していました」 すみません。
信号が赤にかわった場面。ブレーキを踏む。くそ、強く踏み過ぎた。前方には意味のない空間。
交差点、車は右折する場面。歩道走行中の自転車が突然、横断歩道へ、避ける間もなくガシャン。そこでまがってくる? 「ゆっくり曲がりましょう、危険予知の余裕が必要です」 すみません。
交差点、車は左折する場面。ハンドルを適切に操作できない、曲がり切れずに、停車中の対向車に正面衝突。ガシャン。すみません。
細めの路地の場面。対向車が来る、左によって安全にすれ違おうとすると目測を誤る。右前部接触、ガシャン。すみません。
運転リハビリ、ああ、面白かった。という日はいまだない、もうやめようか、と思い悩む日は多い。それでも月に一度の運転リハビリを続けている、いや、続けるつもりだ。
歩く方は上達する見込みがない。調子のよい日、悪い日はある。しかし、あと半年やれば、杖を手放せますよ、と言うのではない。右に開き気味の体の向きを矯正できるかどうか、せいぜいその程度だ。
車は違う。まだ全然だめだけど、もし運転できるようになったら、革命的に行動が変わる。ただ横に座って目的地まで連れていってもらうだけの便乗者から、自分の意志で運転する行動者に変身する。生きる姿勢が本質的に異なる存在へと変わる。個人的にはそう思っている。
それに伴うリスクはもちろんある。事故の危険性はいくら強調してもたりない。自分だけではない。他人を巻き込む可能性も0ではない。
入院中の主治医は、私が運転免許証を取りたい、と申し出た時、はっきりと反対された。リハビリを続ければ運転は可能になるかもしれない、しかし、判断力、注意力が劣化しているのは否定できないのだから、乗るべきではない。そうおっしゃった。誠にもっともなご意見で、反論しようがない。免許証は、私にとって悪魔の誘惑なのかしらん。
1959年生まれ。早稲田大学中退、都内で塾講師を10年務めたあと、福山で独立開業。昨年、脳卒中で半年間入院。塾をたたむ。
右半身に麻痺を抱え、妻の介護なしには生活できない。
にもかかわらず、その自覚は乏しく、傲慢不遜な性格は、おそらく死ぬまで治らない。
交通事故に遭った。
左脳の陥没骨折、失語症との診断である。
〝ことば〟の障害――話せないだけではない。聴覚理解や読み書き能力も失われた。
失語症の完全治癒は困難という。
この先どうなる?知る由もない大学3年時の別れ道。
言語聴覚士による言語リハビリが始まり、これでは困ると必死に取り組んだ日々。
大学に復学すると「ことば」への強烈な現実を科せられた。
講義も専門書も解らない。会話が成り立たず、友人との輪にも加われなかった。
孤立した感覚、惨めだった。
卒後の就活は惨敗続き。
〝何を試みてもダメ〟と自己嫌悪に陥るばかり。
東京での一人暮らし――誰とも会いたくない。
扉を叩く訪問者には、立ち去るまでジッと潜む。
電話には出ず、通院以外は部屋に閉じこもった。
適当に本を読み、音楽を聴き、勉強のまね事をするなど、ごまかすように時間を潰した
「ダメ人間!」と自己否定するばかりで、解決のメドはつきそうもなかった。
“無能さ”に悲痛な思いを抱きながら、“恥辱”に苛まれていた。
身体の障害と違い,外見上失語症はわかりづらい。
ことばをうまく使えないのは恥であり、無能さを広めることとなる。
ならば黙っていた方がいい。その場を無言で切抜け、適当に相槌を打つ。
緩やかに引きこもっていった。
失語症から派生する辛さは様々。
伝えられない、受け取れない、楽しめない、思い切れないなど多岐にわたる。
一々挙げていたら際限がない。
失語症者の辛さは“閉ざされた心”そこに限る。
煩わしいからと、他人との関わりを全て拒否したら、心は閉ざされたままだ。
紆余曲折があり4年後、言語聴覚士として勤めはじめた。
収入を得て自活するようになり、経済的、社会的に多少落ち着けた。
だが、課せられ果たさねばならぬ任務に対しては、穏やかではなかった。
現に読解力は低下したままで、新聞記事は十分に内容把握できない。
専門書は自ずからお手上げ状態だった。
失語症当事者であることを、職場では公言しなかった。
障害は浸透されておらず、誤解を生みやすい。
黙っていた方が良い――その引いた思いから余計な制限が生じた。
仕事の電話連絡による不備、会議でのぎごちない答弁など、不適切な対応ばかり。
それまで以上に失われたことばに追い込まれるような日々――自己卑下に陥るばかり。
その場を取り繕いながら凌ぐのに精一杯。
仕事を十分にこなす満足度には至らなかった。
失語症者は好きで黙っているのではない。
伝えたいが言えない、心にあるものを出せないでいる苦しみであり、痛みでもある。
言いたいことは山ほどあるのだ。
それをじっくり聴いてもらうことは癒しであり、心的外傷の克服に繋がるのだろう。
勤めた病院は1年で辞め、大阪の大学研究室へ行くことにした。
仕事や人間関係など慌ただしい日々に、かなりストレスを感じていた。
表向きは「学ぶ」だが、心の休憩所を求めていた。
実際、学生生活に戻れたことで不安が減少し、学ぶ中で自信も生じていった。
学びながら失語症ケアにおいて、最も大切なのは何かを思い描いた。
病院を退院した後の生活期リハビリ――自らの経験からそこへ辿り着いた。
そして、その実践に適した山形県の病院に就職した。
当時山形県には十分なリハビリテーション施設が少なかった。
リハビリスタッフも少なく、特に言語聴覚士は目新しい職種だった。
脳卒中多発地域であり、「ことば」で悩む患者も多い。
未知の土地での生活に不安を抱いていたが、職場は家族的な雰囲気。
県外から来た私をすぐに包んでくれた。
仕事上うまくいかない時も、失敗をなじらず、成功だけを認めてくれた。
初体験のスキーは毎晩のようにナイターに誘われ、何とか滑れるようになった。
山歩きの会にも誘われ、県内外の名峰に連れていってもらった。
海釣りの体験では、釣りあげたばかりの魚を刺身で頂くこともできた。
おいしい食べ物と旨い酒、庄内弁に囲まれ、楽しい時間を過ごすことができた。
失った「ことば」のみならず、私は生きていく自信を取り戻すことができた。
心的外傷の核心は孤立と無力化という。
回復の基礎は他者とのつながりを取り戻し、自立性の感覚を新たに取り戻すこと。
新たな土地で心地よい仲間と巡り合い、臨んだ道を奔走できた。
私自身の失語症体験で感じ取れるのは、「ことば」だけでなく「こころ」の問題。
――心的外傷を如何に緩和していくかということ。
引き起こされるデメリットの中で、苦痛を感じるのは「誰にも解かってもらえない」という心ではなかろうか。
そして、その解決策は理解してくれる仲間の存在だろう。
「あなたは一人ではありませんよ」というメッセージは、新たな自身を見出す勇気となろう。
認めてくれる仲間の中で、多くの時間を過ごすことで、苦しみや悲しみ、そして絶望感は自然と解消されていくのではないか。
そんな仲間づくりを、「ことばをこえて」目指していけたらと考える。
山梨県出身。1983年大学在学中に交通事故に遭い、失語症になる。1985年 青山学院大学教育学科卒業。1988-1989年 大阪教育大学言語治療コースで学ぶ。1987-2002年山形、山梨のリハビリテーション病院に勤務。1999年第1回言語聴覚士国家試験に合格し、言語聴覚士免許取得。2002-現在 在宅言語聴覚士として訪問ケアを展開しながら、山梨市立牧丘病院、上條内科クリニック、デイサービスセンター「けやき横丁」、韮崎東ケ丘病院、県立育精福祉センター、障害者支援施設「そだち園」などに非常勤で勤務。NPO法人失語症デイ振興会理事、東山地区失語症友の会を事務局として主宰。
主な著書:
「失語症者、言語聴覚士になる」(雲母書房2003/12)
「失語症の在宅訪問ケア」(雲母書房2005/10)
「この道のりが楽しみ」《訪問》言語聴覚士の仕事(協同医書出版社2013/12)
本稿は、2017年10月30日付けの愛媛新聞 福島通信33の中で書いた原稿を加筆修正したものです。文中、現在は不適切とされる表現である「らい病」、「らい患者」という表現がありますが、これは大正生まれであり、パーキンソン病を患って寝たきりになった父に「ハンセン病」という名称がわからない可能性があったので、敢えて使いました。事実を伝える事が重要と思い、ありのまま表現しております事をご了承ください。

放射線衛生学者である私にとって2017年8月6日、広島に原子爆弾が投下されてから72年経った日、心に刻まれる出来事がありました。
都内の小学校で教諭をしている幼なじみに誘われ東京都東村山市にあるハンセン病資料館に行ったことです。資料館の隣には、国立ハンセン病療養所多摩全生園があり、そこには今も入所者がお住まいになられています。
ハンセン病とは昔「らい病」と呼ばれた病気です。「らい菌」に侵され、なんらかの理由で傷ついた顔や手足の一部に別の菌が入り、化膿し脱落するなど異形の患者であったことから、天刑病とも血の病とも言われ、忌み嫌われてきた人々の歴史があります。
1943年にアメリカで「プロミン」という治療薬が発表された後も戦時中の日本ではなかなか手に入らず、その薬が日本で使われるようになるのは戦後まで待たねばなりませんでした。「らい菌」はアルマジロなど特定の動物の体の中では見つかるものの、未だに菌の培養すらできないほど弱い菌です。(2023年のハンセン病学会で低温でも培養が可能なヒト由来神経細胞が見つかり、培養ができる系が確立された)。しかし、特効薬により完治することを知りながら日本政府は、1996年3月まで「らい予防法」という基本的人権を無視する法律が存在したため隔離政策を続けました。
現在のハンセン病に対する差別意識は、国の政策が誤りであったことを認めてからも続いており、間違った認識を持つ人々が少なからずいることが問題とされています。
資料館で学芸部長をされている黒尾和久さん(当時)に案内され、多摩全生園を案内されながら聞いた数ある言葉の中で、『「我;われ」と「彼;かれ」を隔てた』という言葉が私の心に重くのしかかりました。堀と土塁という物理的な隔たりより、同じ人として扱われることがなかった人々の精神的隔たりを意味するもの。残された一族が差別や迫害を受けないようにするため、決して表に名を明かせない者として生きて行くこと。隔離政策により生涯施設の敷地より外に出ることが許されなかった患者たち。夢や希望を持つこと自体も生きる足かせになる生き方とはどのような思いだったのか。
 木村仙太郎の生まれた愛媛県北宇和郡好藤村東仲(現鬼北町)にある神社境内から集落を望む。写真の撮影時期は1940~50年代と思われる。写真に写る一本道の一番奥に木村家本家がある。
木村仙太郎の生まれた愛媛県北宇和郡好藤村東仲(現鬼北町)にある神社境内から集落を望む。写真の撮影時期は1940~50年代と思われる。写真に写る一本道の一番奥に木村家本家がある。
私の大伯父木村仙太郎は、ハンセン病のため岡山県の長島愛生園に送られ、そこで生涯を閉じました。大伯父仙太郎がハンセン病であったことに気がついたのは私が大学院の博士課程の頃ですので、今から30年近く前だったと記憶します。跡を継いだ兄から珍しく私の携帯電話に写真が送られてきました。その中に父が従軍していた頃の写真と傷病兵として病院に入院中のものらしい写真がありました。詳しいことを兄に聞いたのですが、自宅を改修する際、小学校3年生の時に亡くなった義理の祖母(父の養母)の遺品が見つかったというのです。
その後、数ヶ月経った頃、母方の祖父がいよいよ危ないとの報せがあり、親しかった祖父が生きているうちに祖父に会いに行こうと実家のある四国に帰りました。その際、兄に祖母の遺品の話をすると籐で編まれたバスケットを渡されました。その中に古い1枚のハガキはありました。子供の頃に切手を集めていたこともあり、ふと、手に取ると木村仙太郎と書いてありました。私が小学校の頃、実家の仏壇に粗末な無垢の木に木村仙太郎と書かれた位牌があったのを思い出しました。しかし、誰も仙太郎のことを話すこともなく不思議に思っていたのを記憶しています。何気なく送られて来た葉書の差出人の住所を見た私は愕然としたのを覚えています。そこには長島愛生園と書かれていたのです。大学院の博士課程で衛生学の分野に進んでいた私には,それがハンセン病の隔離施設であることに気がついたのです。葉書の内容は、「皆は元気か、今年の米の出来はどうか、自分は大丈夫だから気にするな」という他愛もないものでしたが、私は胸の締め付けられる思いで、それを読みました。
当時、私の父は難病であるパーキンソン病にかかり、寝たきりとなっていました。かろうじて昔の記憶はあるようだったので、「この仙太郎という人は、らい病やったんかな。それは木村の家から、らい病患者が出たというんかな。」と父を問い質しました。長い沈黙の跡、父は絞り出すような声で「言えんかったんよ」と言いました。それを聞いていた母が「うちはそがいなこと、聞いとらんで」といったその時、父が母に対し、吐き捨てるように「そがいなこと言うたら、結婚させてもらえんかったやろうが」と言ったことに、その場にいた母も兄も私も凍りつきました。初めてハンセン病を身近に感じた瞬間でした。
 木村家の墓地から見た東仲集落(現在)、眼下、右手前にある総2階の建物(実家が営む介護施設)とその奥の建物が私の実家である。写真には写っていないがすぐ下に、元弘元年(1331)後醍醐天皇から勅願寺と定められた奈良山等妙寺(鬼北町内)を開いた理玉和尚の隠居寺がある。
木村家の墓地から見た東仲集落(現在)、眼下、右手前にある総2階の建物(実家が営む介護施設)とその奥の建物が私の実家である。写真には写っていないがすぐ下に、元弘元年(1331)後醍醐天皇から勅願寺と定められた奈良山等妙寺(鬼北町内)を開いた理玉和尚の隠居寺がある。
私が世の中の矛盾と闘うようになった原点は、兄の同級生が森永ヒ素ミルク中毒患者であったこと。母親に手を引かれ奇声を発し、曲がりくねった身体を引きずりながら歩く姿を見て、小さな私には恐怖を感じ、家の物陰からそっと、その人たちを見ていた記憶があります。その時、私の母が「あの子は森永のミルクを飲んだけん、あがいになったんよ。うちの子は50円安かった明治を飲んだけん助かったんよ」と言ったときの言葉です。世の中の不条理を一瞬にして感じ取りました。
仙太郎の一件は、私が差別問題の当事者であることに気付かされた瞬間でした。そこから、私自身がハンセン病患者遺族と名乗ることができるようになるまで、20年ほどかかりました。
次回は、その話をさせていただきます。
本件に関する原稿料はいただいておりません。その代わり、科研費23K17530 挑戦的研究(萌芽)「カルテ・解剖録から見るハンセン病研究の変遷」の成果の一部として掲載します。
獨協医科大学国際疫学研究室福島分室
木村真三
木村 真三(きむら しんぞう) 愛媛県鬼北町出身
放射線衛生学者。科学技術庁放射線医学総合研究所、厚生労働省所管の労働安全衛生総合研究所を経て、獨協医科大学国際疫学研究室福島分室長・准教授。幼少期、近所に兄の同級生で森永ヒ素ミルク中毒患者が住んでいたことから、公害の悲惨さを体験し、社会に疑問を持つようになる。時を経て、衛生学者として世に出たと同時期に、東海村臨界事故が発生し、一番最初に現地入りを果たし放射能汚染調査を行った。そこから原発事故の可能性を危惧し、チョルノービリ原発事故研究に着手。2011年に起きた東日本大震災による原発事故発生直後の3月15日より福島県に入り放射能調査と人体影響を探るため福島県二本松市を拠点として調査、研究を続けている。原発事故後、被災者に対し差別や偏見が起きたことを契機に、自身がハンセン病患者の遺族であることを公表した。さらにハンセン病療養所に強制収容された親族の解剖録などの医療記録を日本で初めて一般公開し、人権啓発を進めている。これらの活動は第2の国立ハンセン病資料館である重監房資料館との共同製作として啓発映画となった。また、患者のみならず身内に起きた差別の実態にも触れ、2024年3月にはNHKの『Dearにっぽん』でも紹介された。
ウクライナのジトーミル国立農業生態学大学(現 ポリーシャ大学)名誉教授、ウクライナ国立公衆衛生研究所より名誉博士号授与。
一昨年の正月に姉がこの世を去った。七二歳であった。七二歳とは死んでもそう同情されないし、もちろん驚きもされない年である。それでいて、私は呆然とした。父が死んだあとも、母が死んだあとも一度も泣くことはなかったが、姉が死んだあとはしばらくは子供のように泣き止まなかった。
もし精神科医にかかったら何らかの病名を与えられていたのではないかと思われるほど姉は異様に依存心が強く、周りの人間は振り回された。妹の私も昔からさんざん振り回された。そんな迷惑な存在が突然消えてしまったのである。
文学とは自分の「気持を整理」するために書くものではない。だが私はそのとき文芸誌に連載していた小説を放り投げ、「気持を整理」するために姉について書きたかった――あんな姉を抱えていかに苦労したかと、姉の死を一応は悼みながらも、抑えていた思いをダラダラと記したかった。
そのころから私は折々、書庫の奥深く、大きなプラスティック製の箱にしまわれた昔の家族の手紙を引っ張り出して読むようになった。連載が終わり次第、姉について書こうと決めたが、自分の記憶に穴があるので、その穴埋めの手がかりにしようと軽く考えたのである。さらに小説家として残された命のこともあった。与えられた時間がいよいよ限られてきているうえに、体力精神力の限界も押し寄せてきている。姉が死のうと死ぬまいと、この先は虚構世界を描かず思い出話だけを綴ろうと前々から考えており、それらの手紙はいづれにせよいつかはざっと目を通すつもりであった。
ただ、きっちりと読むにはいかにせん量が多すぎた。
最初手にした束は父が沖縄に出稼ぎに行ったときに父と母が交わした手紙で私は生後半年。「美苗がエンコができるようになりました」。そんなつまらないことから始まって、二年半にわたって二人は手紙を書き合っている。そのあとしばらくして私達家族の外国生活が始まり、そのうちによく離ればなれに暮らすようになり、父をのぞいた女たち三人は頻繁に書き合うようになった。ことに母は書き魔であった。
全部で優に数千通はある。
「パンドラの箱」を開けてしまったのに気がついたのはしばらくしてからである。初めのうちは、適当に手紙を一通、二通と抜き出しあちこち斜め読みするつもりだったのが、いつのまにかとっぷりと日が暮れるまで一枚一枚丁寧に読んでしまっていた。何と自分は多くを忘れ、多くを都合良く曲解していたことか。姉の異様な依存心の強さは記憶していた以上に呆れ果てたものであった。ただ、自分の馬鹿さ加減もこれまた予想していた以上に瞠目に値するものであった。穴があったら入りたいと幾度も思った。自分は記憶力が良いほうだなどといったい何を根拠にうぬぼれていたのだろう。
姉について書きたいという気持はいまだに残っているが、今はこのような書簡の山を前に、姉が死んだとき以上に呆然としている。残された命で思い出話だけを書こうと考えていたこの後に及んで、新しい様相をまとった過去、いや、これぞ真実だと目の前に立ち上がった過去と向き合わねばならなくなった。これらの手紙を丁寧に読み、ノートを取り、年代順に整理していくとすると、いったい、この先、どれほどの時間と根気を要するか見当もつかない。もちろん、これらの手紙を無視して記憶だけを頼りに書くのは可能は可能だろうが、やはり思い出話となれば、なるべく真実に近づけたい。目の前にある手紙を無視して書くのは、何とも大げさな比喩だが、地動説を知りながら天動説を説くのとどこか似ているような気がするのである。
ただ、私にとって慰めが一つある。
小説家として保守的な私は、新しいことを試みるよりも、自分の作品が過去の「書き言葉」の伝統と繋がっているのを喜びとする。その「書き言葉」の伝統が今や亡びつつあるものであったら、なおさらである。自分が歴史の中の時間を生きているのを肌でひしひしと感じられるからである。
手紙とは今や亡びつつある「書き言葉」の伝統である。
人が誰かに向かって何かを「書き言葉」で伝えるという人間の営み――その昔ながらの営みは、いくら音声と動画が世に氾濫しようと、この先もいろいろな形で残り続けるであろう。だが、少なくともその営みが手紙という独特な形を取っていた時代は終わりを告げつつある。書き終えたばかりの手紙を片手に知らない町でうろうろとポストを探すことももうない。郵便配達が来る音に耳を澄ませることももうない。手紙が行き違ってしまって絶望することももうない。
手紙というものが当たり前だった時代を私は生きた。手紙というものが亡びつつある時代を私は今生きている。そういう時代の証人として、手紙という「書き言葉」を自分の作品の中で小説家とした果たして生かせるだろうか・・・・・・。
最近そういうことばかり考えている私は、いつのまにか姉の死を悼むところからずいぶんと遠く離れた場所に立っていた。
小説家。父親の仕事の関係で12歳で渡米。イェール大学および大学院で仏文学を専攻。
創作の傍らしばらくプリンストン大学やミシガン大学などで近代日本文学を教える。
著書に『續明暗』、『私小説 from left to right』、『本格小説』、『日本語が亡びるときー英語の世紀の中で』等。
近作『大使とその妻』を新潮社から2024年9月に出版予定。
『ことばを伝える役割』は、私にとって、ときに楽しく、ときに複雑な感情を生起させるものだった。
わが家は、ろう者の父と、聴者の母、私、弟の4人家族だった。私や弟のような、きこえない親をもつきこえる子どものことをコーダ(CODA:Children of Deaf Adults)という。両親ともきこえない場合でも、私や弟のようにどちらか一方の親がきこえない場合でも、きこえる子どもは皆コーダと定義される。(親がろう者であるか、難聴者であるかにも関わらない。)
かつてのわが家では、父はまったく声を出さず手話のみで会話をしていた。母と弟は手話が不得手で、父との会話は、家族の間でしか通じないホームサインや身振り、筆談など、あらゆる視覚情報を用いて成立させていた(のちに母は手話を習得した)。私はといえば、家族の期待を一身に背負い、幼少期から手話を覚えた。そうはいっても、今振り返れば、幼い頃の私の手話など拙いものであったのだが。
このような、友達の家族とは一風変わったわが家の会話のやり方は、私が生まれたときからごく当たり前のように家庭の中に存在していた。
一方で、家から一歩外に出れば、そこには音声日本語のみの世界が広がっていた。母や弟よりも手話ができる私は、ときに父と外の世界との間に立ち、互いのことばを伝える役割を期待された。その役割は、一般に「通訳」と呼ばれることを、大人になってから自覚した。
コーダは、幼少期から、きこえない親のために通訳の役割を担うことがある。コーダ104人を対象にした実態調査(中津・廣田, 2020)では、コーダは平均6.48歳の幼少期から頻繁(平均4.52日/週)に親の通訳を担う現状が明らかになった。通訳を担う場面は、電話や来客、親戚の集まりや買い物などの日常会話場面にはじまり、病院での診療や銀行窓口でのやりとり、コーダ自身の学校関係(授業参観や三者面談など)など多岐にわたり、それらは個々のコーダによって大きな違いがあった。通訳の役割に対する気持ちも、当然と受け止めるコーダもいれば、肯定的に捉え、親や周囲の期待に応えることで自信を持つコーダや、面倒で疎ましく思い、葛藤が喚起されるコーダ…と実にさまざまだった。
私といえば、大好きな父の役に立てることが嬉しく、父を守ろうと率先して父と外の世界との仲介役を担った。けれどもその役割は、ときに私の心に影を落とすこともあった。今でも鮮明に思い出すのは、中学2年生のとき。母が危篤状態となり、深夜の病院に私と小学生の弟、きこえない父が並び、主治医から説明を受ける。「お母さんは予断を許さない状況です。確率は半々です。」私の左側には泣きじゃくる弟、右側には「何?何?」と私に尋ねる父。私は、動揺しながらも、主治医の説明を父に伝えた。その様子を見た主治医が、私にこう言った。「お母さんに万が一のことがあったら、小さい弟さんもいるのに、お父さんはきこえないなんて、あなた気の毒に。可哀想に。」
主治医のそのことばは、父に伝えなかった。通訳としては失格だったけれども。
今では、情報保障などの社会資源が整備され、テクノロジーも発展して、ろう者や難聴者を取り巻く環境は格段に進歩した。けれどもまだ、きこえない親が生活を営むうえでは、コーダが通訳の役目を果たさざるを得ない場面がどうしても発生する。幼いコーダのために、たとえば手話通訳者や要約筆記者の派遣制度は、もう少し柔軟な形で利用できるようになればいいと思うし、大きな病院には常に通訳者が配置されていればありがたい。通訳者の職域確立も、もっと進めばいい。そもそも周囲の大人は、きこえない親とぜひ直接、会話をしてみてもらいたい。きこえない親と外の世界とのコミュニケーションのすれ違いを、コーダと親の家族だけが必死に頑張って解消しょうとする世の中は、そろそろ終わりにしたい。
さて、私の話に戻るが、時が過ぎ両親は他界し、幼い頃から担ってきた、私の『ことばを伝える役割』は無くなった。幼い頃から父を守ろうと(勝手に)踏ん張ってきた私は、守る対象が無くなり、心にポッカリ穴が開いてしまった。今さら自分のために生きろと言われても、自分というものがよく分からない、どうしようもない“こじらせコーダ”だ。コーダが(無意識的にも)過度な心身の負担のもと通訳を担う経験は、心にいつまでも痛手を残すこともあると、身をもって知らされた。若いコーダには同じような思いはしてほしくないと、既に人生の折り返し地点を迎えた、こじらせコーダは思っている。
※このあたりのことは、書籍に詳しく記述した。
『コーダ きこえない親の通訳を担う子どもたち』中津真美 金子書房
こうして、かつての私が担った『ことばを伝える役割』は、嬉しい思い出や苦い思い出とともに、今も私の原体験として脳裏に刻まれている。
東京大学多様性包摂共創センター バリアフリー推進オフィス
特任助教。生涯発達科学博士。
障害のある学生・教職員への支援のほか、
全学構成員へのバリアフリーに関する理解促進のための業務に従事している。
ろう者の父と聴者の母をもつコーダであり、コーダの心理社会的発達研究にも取り組む。
J-CODA(コーダの会)所属。
5年ほど間欠的に続けてきたこの連載は、今回で最後のつもりである。初回を読み返すと、ためらいがそうとう伺える。REEDYという大学に基盤を持つブログに書くことに対して、やさぐれているようで気負ってもいる。下駄をはかされたような少し得意な気持ちと、自分にとって鬼門にしか思えない学校(大学)との間で、どうにも座りが悪くなっているのだ。
高卒の自分にとって大学に触れたのは、吉田寮(京大)や駒場寮(東大)での経験だった。遊びに行ったり、居候したりと楽しかったけど、それは大学というより自主管理空間の面白さだった。そして、大学当局からは潰される対象であった。
それ以外は、イベントやその他でぼちぼち大学と関わったが、いずれも表面的に自由な感じはあっても、力関係に基づいた地金が剥き出しになる場面があって、気持ち悪かった。その度に、あらためて学校空間への嫌悪というものが累積されたものだ。
ひさしぶりに塔島さんから原稿依頼をうけ、最近、自分が路上でやっている「何やさん」というお店についての文章を提出しかかったのだけど、そのことをテントで暮らす友人に伝えたところ、「なんで路上の話を東大のブログに書くの?」みたいなことを言われた。その人は軽い揶揄のつもりだったのだろうが、ぼくは、そうだ!と思って恥ずかしくなった。
最近、香港の人と話した。もともと香港では路上販売が法的に難しいが、旧正月だけは町中に屋台があふれていたそうだ。しかし、当局がそれも禁止したため、2016年に魚ボール革命という屋台を守るための暴動が起こり、その後、彼は焼きそばパンの屋台をやっていたという(ちなみに、焼きそばパンは香港にはなかったそうだ)。
2020年以来、国家安全維持法などで、2つの政府によって強権的に統治されている香港について、彼はこう言っていた。つまらなくなったとされているがそうではない、あらゆる文化がアンダーグランド化しているため、すごく面白い。
もちろん香港と日本の状況は全く異なっている。日本で政治的・法的な意味でアンダーグランドと言えるものは限られている。それでも、マジョリティや権威からは簡単に手の届かない場所でこそ文化が育まれるということは同じだろう。なぜなら、文化には独自なコミュニティが必要であり、コミュニティは、ある一定、閉ざされることで生まれるから。
ぼくは、楽天的な傾向と自分では思い、優位な立場だからと他人には見えていたかもしれないこととして、開かれていることを先験的に良いと考えてきた。「みんなの公園」と言い、公園はだれが住んでもいい、と言ってきた。押しつけられた線引きに対しては有効だし、それが間違いという訳ではない。ただ、みんな、といい、だれでも、といい、開かれている、という中では、立場のちがいに鈍感になる。主体的に線引きすることが大切な場合は多くある。一方で、表現とは拡散し伝播するものだから、それは線引きを超えてしまう。線引きの更新の揺れ動きの中で文化は発展する。
ぼくは、ホームレスというコミュニティに属していて、そのことを文章として発表してきた。それは何のためなのだろうか?
近年、野宿者に身をやつして潜入取材をするルポライターや、テント村をうろつくユーチューバーもいる。ホームレスは、身近な異世界として表象され、消費されるものになっている。それらについて様々な問題があると思うが、本質的な問題は一般世間の欲望に立脚した光の当て方によって、コミュニティやホームレスのあり方が損なわれていることだ。
ぼくの文章は、ホームレスになろう、という呼びかけではないものの、一般世間とはちがう文化やコミュニティを作ろうとしている人たちを促すものでありたいとは思っている。ぼくは、そういう人に向けて書いている。
REEDYのエッセイという場は、塔島さんの個性を反映した、かなり多様で自由なものである。でも、その背後には大学や教養の世界が連なっている。ユーチューバーのような扇情的なものとは異なるものの、別の形で消費されうる世界である。
そう考えると、最初のころの違和感やひっかかりは、あまり変わっていないし、ぼくの浮つきがちな気持ちをもってしても、今後もそれは変わらないだろうと思える。
1970年生まれ。幼いころは多摩川の川原にあるセメント工場の寮に住んでいて、敷地に土管がたくさん転がっていて、多摩川は泡をたてて流れていた。2003年から都内公園のテント村に住んでいる。
ホームレス文化 https://yukuri.exblog.jp
ロンドンの空港から市内へ
5年前にロンドンに来た際は、ヒースロー空港から市内へ出る鉄道のルートは2つ、追加料金がかかるヒースロー・エクスプレスでパディントン直通か、時間がかかる昔ながらの地下鉄ピカデリー・ラインかであったが、2022年にエリザベス・ラインが新たに正式開通し、断然市内へのアクセスが便利になった。エクスプレスと並行のヒースロー・コネクトという線を市内中心部に延伸して東につながるようになったような路線だ。ヒースロー・エクスプレス、前回華々しく看板でてたけど、今回は仮設チケットブースも寂しい感じで、使う人いるのかと心配になる。
エリザベス・ラインは市内中心ゾーン1を東西に横断し、ゾーン内で5つの駅に止まる。この5つはいずれも既存の地下鉄の駅とステップフリーでつながって、車いすでも乗り換え可能(車両を間違えなければ基本段差もない)。ゾーン1内の車いすでも利用できる駅はやはり限られているが、移動はかなりしやすくなった。ゾーン1にはウォータールー・アンド・シティ・ラインとノーザン・ラインのバタシー・パワー・ステーション行きの路線、テムズリンクというナショナル・レールの路線も新たに通っている。






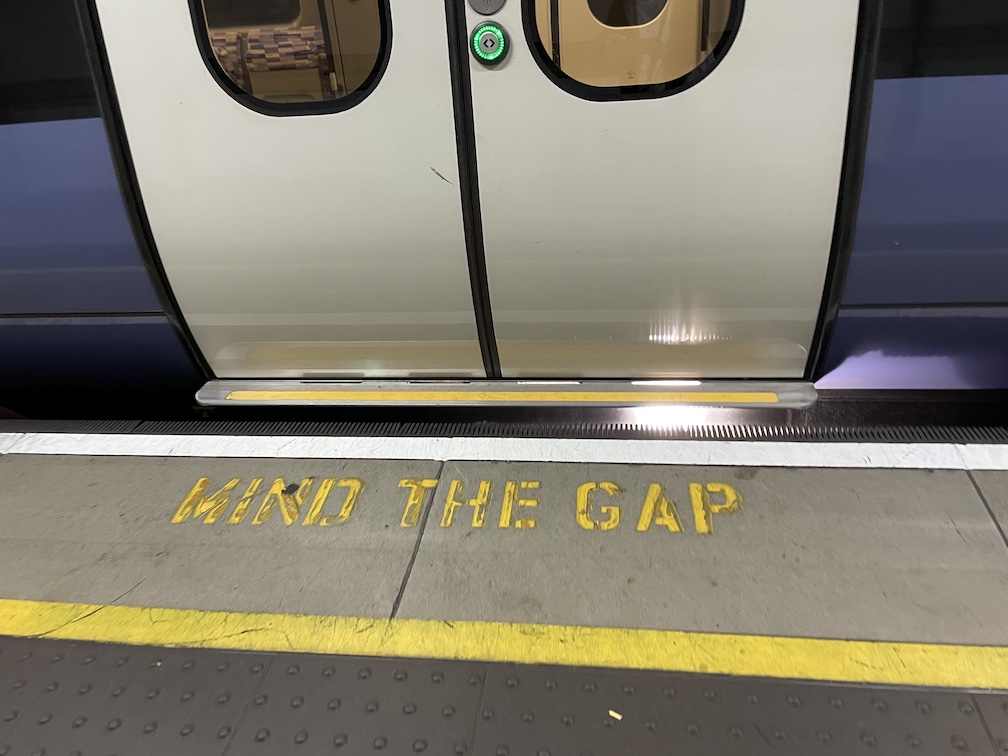


ロンドンのタクシー
タクシーは5年前も基本すべて車いすで利用可能。スロープの出し入れが引き出し式に替わっているようで、前の開き式のほうが楽そうではあった。
雨など、非常の際にはタクシーが気楽に(料金は高いが)利用できるので、ロンドンの移動で心配することはあまりない。


ロンドンのバス
ロンドンは地下鉄が非常に便利な交通手段であるが、中心部は古い路線が多く、車いすで利用できる駅は限られている。車いすでの細かな移動はバスがメインになる。こちらは5年前もスロープ完備、車いすスペースも必ずある。
バス路線は膨大で、大体いきたいところに行く路線が見つかるが、複雑すぎてわかりにくかった。今はスマフォアプリで行き先路線の番号を調べると、乗るバス停の位置も地図で確認できるので迷わなくなった。

チェンジング・プレイス —大きな個室トイレ
チェンジング・プレイスは、1人か2人の介助者がついているような重度の障害のある人たちのためのトイレです。
高さ調節可能な大人サイズの更衣ベッドと天井ホイストシステムが設置され、移動は着替えに介助が必要な人が使える十分な広さがあり、多くはシャワーも付いています。
2020年に改正されたイギリスのビルディング・レギュレーションには、主に新築の建物と大規模な改修が行われる建物の両方において、特定のタイプの(集会、レクリエーション、娯楽の目的で使用される)ものにチェンジング・プレイスを設置する規定を追加しています。
ナショナル・レールのターミナルであるユーストン駅にチェンジング・プレイスがありました。






行ってみると入口にカギがかかっていて入れない。仕方なく一般トイレに戻り、こちらの奥にでも車いすトイレがないかと覗いてみたところ、作業着のおじさんが出てきて「こっちじゃない」と言ってポケットからじゃらじゃらと鍵束を出して先ほどのチェンジング・プレイスを開けてくれた。
出てくる時には、両手にクラッチの少年が待ち構えていて入れ替わりで入っていった。
オーバーグラウンドで郊外へ
ロンドンの地下鉄はアンダーグラウンドというが、市内で地上を走る路線はオーバーグラウンドという。
中心部の地下鉄駅から郊外の駅で乗り換えてオーバーグラウンドを利用、新興の再開発住宅地へ。


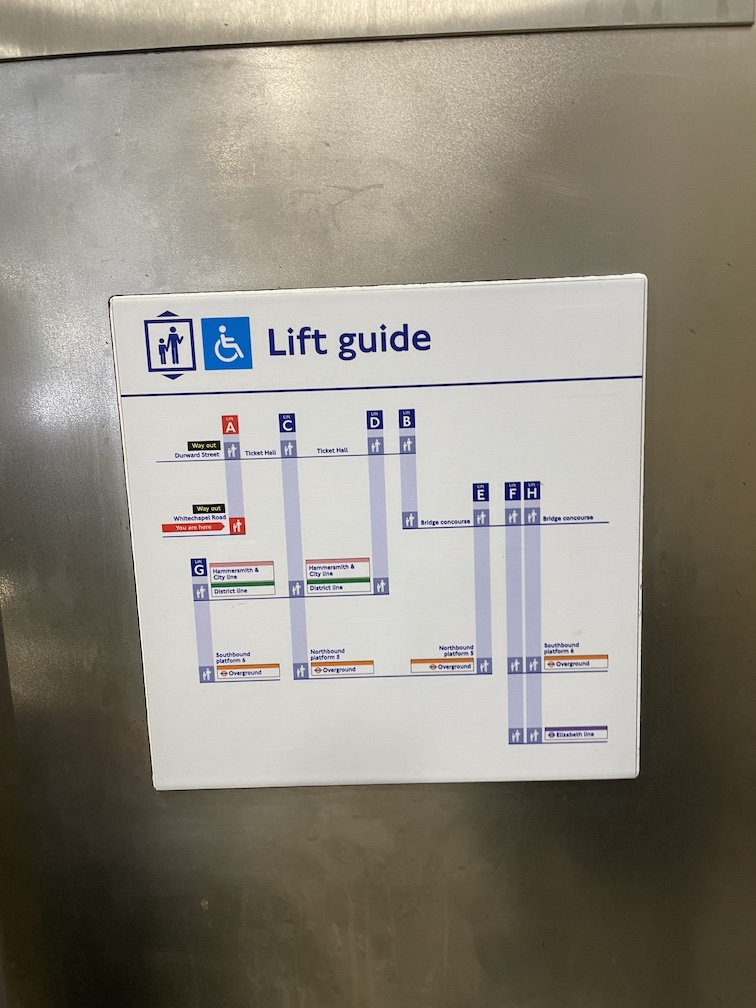
この郊外の乗換駅ではフォームとフォームの間を地下通路でつないでいて、それぞれのフォームには長いスロープで上がるようになっている。








車いすで改札を通ると、待機中の駅の人が必ず何か必要でないかと声をかけてくれる。


市内の地下鉄のステップフリーの駅は、フォームがそこだけかさ上げされていて車両とのギャップをなくしています。




DLR ドックランズ・ライト・レイルウェイ
2012年のロンドン・オリンピック・パラリンピックを機に一気に再開発が進んだロンドン東部は、もともと80年代のドックランズという地域の再開発時からドックランズ・ライト・レイルウェイDLRという鉄道路線がつくられてきた。DLRの駅は改札がなく、タッチ式のカードパスOyster(東京でいうスイカ・パスモのようなもの)か、今はコンタクトレスのクレジットカード、スマフォで駅のカードリーダーにタッチして乗降する。新しい路線なのですべてステップフリー。



テムズリンク
今回テムズリンクの鉄道は車いすで利用していないが、写真だけ。




空港へ




5年前はスペシャル・アシスタンスと案内されていたが、アシスタンスだけになっているのは、もっと幅広く利用者を受け入れるためでしょうか。


ロンドンは2012年のオリンピック・パラリンピックを経て明らかにバリアフリー化に勢いがついた。前述のパリと比べると、移動の保証はかなり定着している印象がある。パリは2024年を経て、さてどれほど変わっていくでしょう。
●本当に段差の少しある家が好きか
今住んでいる私の家は、購入した時から、ほぼバリアフリーの家でした。
赤いドアの玄関は狭いため最初から車いすの出入りは諦めましたが、玄関脇の居間に繋がる大きなサッシの幅は電動車いすが余裕で出入り可能でした。なので、サッシの高さに合わせて庭の一部をコンクリートで埋めてもらい、窓からの車いす出入りを叶えました。
お風呂は引き戸で中も比較的広く、湯船も一般の高齢のかたが使うのであれば使いやすそうなものが設置されていました。お湯は上下のレバー操作で簡単に使用することができ、温度調節も指一本でできます。
各部屋の照明スイッチも大きなもので、押しやすさを考えたものでした。
これだけちゃんと揃っている家を、ところどころ「使いにくい」と感じてしまう私は、やはり人と少し違う体を持っているんだと実感してしまいます。
お風呂の湯船は今のところお客様用です。私は入ることができません。昔なら、どうにか湯船に入ろうと考え、湯船と高さが合うスノコを洗い場に敷いたことでしょう。最近の私は、幼児用のプールにお湯を溜めて、なんとなく湯に浸かったという気分を味わうだけでいいのです。大きな湯船に入るよりも数十倍も安全だし、お湯も経済的だったりします。介助のかたに聞かないと本当のところはわかりませんが、私が楽だと思っているのだから、きっと介助の仕方もこのほうがうまくいっているのではないかと勝手に思っています。
もし今の私が、湯船に入ることを優先していたら、どのような生活になるでしょう。今の大きさの湯船に入るには、体を持ち上げるためにリフトが必要かも知れません。毎回の介助をお願いするには、介助のかたが二人は必要になるかも知れません。そのような生活を選んでもいいのですが、今の私は選択をしていません。おもちゃのような小さなビニールプールに毎回入って、転んでも痛くなく、溺れることもほとんどないこの環境を楽しんでいます。
今住んでいる家のトイレも、便座の高さがあり、私の身長では支えてもらっても腰掛けることができないものでした。なので、約10cm強の段差をつけるようにしました。軽い材質の、それこそスノコのようなものを重ねて、その上に安めのヨガマットを敷いて滑らないようにしています。
話が少しそれますが、最近の水洗トイレは高さがあるものが主流になりました。身長149cmの私は、街のどの多目的トイレでも腰掛けるのに背が足らなくて困る場合が多くなりました。車いすからの移乗の時に、抱きかかえてもらう方法を取るなら、便座の高さがある方が介助のかたの腰の負担が少なくなりいいのかも知れません。支えてもらって自分で車いすから便座に移る私には、利用が少し難しいトイレなのです。手すりの位置もトイレによってまちまちなことも手伝って、中には本当に「利用できない」多目的トイレに出会う事態が起こっています。他の車いすユーザーのかたはどうなのか、気になるところです。
家のトイレ問題も、お便器自体を床に埋めてしまうか、お便器をもう少し小さいものにするという改善策は浮かびます。ただまず現実的に今の時代、一昔前の小さな洋式便器はないようなのです。よくよく探せばもしかしたらあるかも知れませんが、「温水洗浄便座」の主流は背丈のあるもののようです(私は温水でお尻を洗う製品を使用しています)。床にお便器を埋めるのも、費用がかかります。私の障がいの程度が変わったら、また手直しが必要になるかも知れません。住宅改造については、活用できる障がい福祉制度がありますが、一回しか利用できませんから、とても慎重になります。
本当はお風呂の湯船に入れた方がいいし、トイレの段差なんてない方がいいのです。どう考えても、家の中は段差がない方がスムーズに動けるでしょう。車いすからの乗り降りも、車いすと並行した高さの床があれば、とても楽になるのですが、それを実現するには、また家の中に結構な高さの段を作ることになります。残念ですが、全てを思い通りにはできません。現実の中で生きているのですから。
ものごとはやはり、どちらがより必要なのか、選びやすいのかで選ばれていくものなのかも知れません。妥協点を探して選んでいるものに「好き」という言葉を使ってしまったから、おかしいことになったのかも知れません。
そう、私は、少し段差のある家が好きというわけではなく、より居心地良い、好みの合う家が好きなのです。段差をあえて家の中に作る背景には、全て希望通りの環境にできるほど資金持ちではないということもあります。また、生活する中で、より良いアイデアがなかなか浮かばないことも課題です。
確かにすべて住みやすく揃っていた方がいいとは思いますが、私にとって全てを求めることは、得る目的に対して(例えば引っ越す際のアパート選び等)とても高いハードルを自ら作ってしまうことでもありました。ちょっと不便でも、安価で、または少し簡単な作業で手に入り、工夫次第で自分らしく暮らせるならば、それはそれで面白いのではないかと思って乗り切ってきました。
今の家に暮らす一つ前の貸家に住んでいたときは、網戸のある部屋が限られていたり、隙間風が気になったり、物干し台がとても高い位置にあったりと、工夫した方がいいと思われることはわんさとありました。いろんな介助のかたと、ああでもない、こうでもないと話し合いながら工夫を形にしてもらいました。その時間はとても楽しいものでした。
そのような日常は、誰の日常であっても、他者には見えない世界です。私はたまたま自分ではできないことが多く、一緒に時間を過ごすその日の介助のかたに頼んでやってもらうので、日常のいろんなことは、介助のかたと共有されます。それもまた面白いところです。
確かにだからと言って、階段のある2階以上の部屋や、介助が大変なほど狭いトイレの設置された部屋は選ぶことはありませんでした。そう考えるといつも制限はあったのかも知れませんし、狭い範囲の中から選んでいるのかも知れません。でもそれなりにリサーチしたり自分で足を運んだり、行動した結果たどり着いているので、経験値としてはそれほど悪くはなかったのではないかと思っています。
今の家は、ほとんどバリアフリーですが、改善したいところは実はたくさんあります。それを改善していけるか、妥協点を探して落ち着けるかは私次第です。
●ムジュンはやはり心の中に
小さなお店に行くことも、私の中にムジュンはありません。
確かに商業施設の中は電動車いすでどこにでも行けるし、大抵はどこかの階に多目的トイレがあり、トイレを探す手間もありません。お店で入店拒否されることもあまりないし、そういう意味ではドキドキすることもありません。
ただ、私が行きやすいということは、多くの皆さんが行きやすい場所であるということです。なのでいうまでもないことですが、いつもとても混んでいます。それはいいことであると思うのですが、人混みは少ししんどいと感じることがあります。
私の場合、商業施設では顔を覚えられることはあまりありません。一回一回丁寧な対応はしてもらいますが、顔を知っての挨拶をしあうことはあまりありません。別の言い方をすると、大型商業施設では、私は独りになれるのです。丁寧に対応されるけれども、孤独な時間も味わえる、皮肉でなくそういう場所なんだと思います。
小さいお店だとそうはいきません。愛想良くされるかそっけないかは入ってみないと分かりませんし、歓迎されるかどうかも何回か行ってみないと分かりません。電動車いすで行けば、相手にとって好ましく感じてくれてもくれなくても、インパクトが強く、すぐに見知った関係になります。名前などお互いに知らなくても、お店の人と私との関係性は始まっていきます。そこのところがとてもドキドキして、好きなのです。もちろん、車いすで店内に入れるなら本当に楽しいと思います。でもそれは私にとって運のようなものです。
以前、しっかりした障がい者団体が活動していると思われるまちで、絶対余裕で車いすも入れそうな蕎麦屋さんに入ろうとした時、入店拒否をされたことがありました。店内はお客さんもまばらでした。その頃私はまだ青くて、障がい者団体があるところは飲食店も理解者が多いと思い込んでいるところがありましたから、こんなこともあるんだとショックを受けたのを覚えています。だからといってそのまちの障がいある知人に言うこともなく私は帰りました。お店の人を説得しなかった私にも障がいある側として非があるような気になってしまったからです。なんとなく、障がい者としての義務を果たさなかったような、すまない気持ちになってしまったのです。
入れそうだと思う店に入れなかった時、入れてもらえなかった時、私の中には憤りを感じますが、受け入れられなかったお店の人の心はどうだったのでしょう。そこに何があったのでしょうか。
以前、名が売れている下着屋さんに電動車いすで入ろうとした時、「電動車いすは入れないんです」と、入店を断られたことがありました。手動の車いすは入れるとのことで、通路も広くとってあるお店でした。その場では介助のかたに店内を見てきてもらって買い物を済ませましたが(多分少し店員さんと揉めたとは思います)、煮え切らず、その店の社長さん宛に手紙を書いたことがあります。
しばらくして、社長さんから返信をいただきました。
そのお店ではその頃、店内の電動車いす使用者と歩行者が接触する事故が多かったそうです。高齢のかたが客層として多いお店でした。近年、高齢のかたも簡易電動に乗られるかたが増えていることは知っていましたが、お客同士でトラブルに発展してしまうことが、そしてそれが賠償問題まで大きくなってしまう場合の多いことが、社長さんの気に病んでいる点とのことでした。
「あなたのようにマナーのいい人ばかりではない」とあった文面に、どう返信しようか迷っているうちに月日は流れてしまっています。おそらくその店は今も電動車いすでは入店できないのではないかと推測しています。反論も何も書けなかった私も悪かったと、今も心に残る出来事です。
私にとって電動車いすは「足」ですから、入れそうな店で入店禁止を言い渡されるとやっぱり悲しい気持ちになります。ただ、そのかたの偏見や知らないことから来る「拒否」だけでなく、それぞれの理由があるのだということも実感しました。
今は、すべての人に差別をしないように求めるのはとても難しいことだと言うことを知っています。悲観的に言っているのではなく、現実として実感しています。現実を知れば、他者の行動に対してひとつひとつ感情的な反応をすることよりも、自分がどうしたいかで、次の行動を決めた方がいいと思えるようになります。入店を拒まれたらかなしいですが、たくさんのお店がある今の世の中、相性のいい店に行けばいいだけのこと、と思ってしまうのは、いけないでしょうか。
●心地やすさが変化していく
最近になって、私の身体は老化により大きく変わりつつあります。簡単に安全に使いつづけていけるはずだったビニールプールのお風呂も、出入りに苦戦するようになりました。電動車いすの運転にも、多少の難しさを感じるようになりました。
私の障がい、脳性まひ特有の不随意運動の出方が変わったことと、筋力が落ちたことで、普段の体の使い方に支障がでてきたのです。
老化による障がいの変化は初体験です。なのでここ数ヶ月はなかなか現実を受け入れられずに困りました。なぜかこの状態になって、「人に迷惑をかけてはいけない」などと言う気持ちが大きくなってしまい、体の状態が変化していくリアルタイムの介助方法が考えつかなくなってしまったのでした。
腰を支えてもらう、という一つの介助を増やすだけで、介助のかたの体に負担をかけてしまうのではないか、介助の仕方を変えることは「迷惑をかけることなのではないか」と、神経質になってしまうのです。今まで、「できないことは頼んで代わりにしてもらえばいい」と言う考えのもとで生活してきたというのに、ここにきて沸き起こった私にとってとても大きな心のムジュンでした。
これは、私の中の偏見もあると思います。障がいが重くなることで「人に迷惑をかけてしまう」と感じてしまうことは、「自分のことは自分でしたい」と感じている自分がいるということになります。気持ちは感じても仕方ないとしても、できないことを人に頼むということは、「迷惑」にはならないはずです。できないことをしてくださる相手に対して感謝の気持ちを持ち、相手のことを思いやり、誠実であれば、頼むことに罪悪感は持つ必要はありません。そこのところを、今回私は見失ってしまいました。少し卑屈になったし、びくついてしまったのです。
やはり自分は「何かをできている」と思いたいのでしょう。そして「できないということは人の迷惑になる」と、未だ心のどこかで思っていたのでしょう。これは私の中の無知な部分だったのだと思います。半世紀も重度障がい者と呼ばれる立場で生きてきながら、まだその「できない立場」を理解していなかったのですから。
今回のことで、介助のかた一人一人と介助方法について話し合ってみました。今までの介助に加えてひとつ体を支える動作が増えたり、電動車いすの運転の時にやってもらいたいことを話し、介助がうまくいかない時は介助の仕方について提案をもらったりもしました。
自分がどうやって介助をしてもらいたいか、自立生活を始めてから、私はずっと自分で考えて、介助のかたに伝えてきました。介助のかたの体のことも、私なりに考えてきたつもりでした。
でも、今回の体の変化で身体的な支えが多くなった時に、介助を受ける私側と、介助をする介助者側双方の感覚のすり合わせも必要なんだということを学びました。私も気持ちを殺さず、かと言って勝手にこの介助の仕方がベストと思い込むことはせずに、いいと思うやり方は話し合ってみようと改めて思ったのです。
今の時点で、老化による機能低下はまだ進みつつありますが、関わってくださっている介助のかたがたと話をしたり説明したり提案を聞かせてもらったりしたことで、これからもどうにかなるかも知れないと思えるようになりました。
心のムジュンというものは、自分の中にある偏見や、物事を知らないことを、あらわにするものなのだとも感じました。
●ムジュンの世界と私
どう考えても、ムジュンがある世界の方が真の世界なんだと、ここまでいろいろ書いてみて思います。理想の世界は心の高いところにあるけれど、もしかしたらそれ自体が歪んでいるのかも知れません。
私にとっては、障がいあるこの体で社会に出た時、自然に受け入れられることが理想であり望みであるのです。「できない体」で生活する時、なるべく自分で自身のことを考え決めて生きていきたいのです。水の合う人とできれば一緒にいたいし、折り合いの合わないところはできるだけ避けたいと思っています。
そして、興味のあるところにはどこでもいきたいし、苦手そうなことも時には挑戦しながら生きていきたいと思っています。多くの人と接点を持ちたいし、できるだけ住んでいる地域に溶け込んで、市民の一人として生きていきたいと思っています。
ただそこで、私の中の世界でものを見ている私には、いつも思いもよらないことが起こります。時に納得していなくても、私はそこに自分をはめ込んで生きようとします。私の側が感じるムジュンです。
例えばなんとなく子供扱いされているように感じたり、入店を嫌がられたりするさまざまなことは、私でない他者の感情や都合が起こすことです。私の世界には、私を拒絶するものは作らないようにしているからです。
もう数十年も前、駅にエレベーターがないのが普通の、世界がありました。多目的トイレが行政機関や大きな商業施設にしかない世界がありました。私はその世界に生きながら、「誰でも乗りたい人が乗れるエレベーターがある駅に変わればいい」「必要な人が使える広いトイレがあちこちにある街になってほしい」と願いながら生きてきました。私なりに動いてもきました。
今、駅のエレベーターを当たり前に以前からそこにあるように、多くの人々が利用しています。私は時間があることも手伝って、忙しそうに駆け込んできた人や順番など守らず先に乗り込もうとする人に「どうぞ」と先に乗ってもらう確率が高くなっています。車椅子に乗った私に順番を譲られて先にエレベーターに乗っていく人々は、さまざまな表情を残していきます。すまなそうに乗る人や、一瞬戸惑う人、ありがとうと言ってくださる人、我関せずのように見える人、本当にそれぞれです。
多目的トイレも、以前より格段に設置場所が増えましたが、多機能なこともあって利用人口も増えたように感じます。私は外出するときは、その周辺で利用できそうな多機能トイレの場所を数カ所想定して出かけます。利用人口が多いので、使用中の場合も多いのです。デリケートな場所なので、それぞれ使われるかたにご事情があるのだと私は思っています。社会状況でいろんな手立てを考えること自体は、私が車いす使用者だから、ということではなく、きっともっと多くの人たちがそれぞれの事情の中で思い悩んでいるのではないかと感じています。
それに、私は、駅にエレベーターがないとき、「みんなが使えるエレベーター」が設置されるといいと望んできました。どこか特別な通路の先にある「専用エレベーター」は望みませんでした。
多機能トイレも同じです。街中に設置されていってほしいと望んだトイレは、使いたい人が誰でも使用できるトイレでした。今私が生きる世界は、以前の夢であった環境が叶いつつあるのです。
誰でも使えるということは、いろんな価値観の人が使えるということなのだと、変わりゆく環境を体験しながら私は知りました。私が出先で多機能トイレをなかなか使えない現実は、当時の私にとっては想定外だったと思いますが、夢が叶いつつある今の日常の中で何が起こるのかを体験していくしかありません。多機能トイレをそれほどの多くの人が使いたいと思うとは、私には思いもつかなかったし、理解していなかったからです。
エレベーターに対しても、同じように私は捉えていたと思います。「みんなが使えるように」と言いながら、心のどこかで「私も使えるように」という気持ちだけが大きかったのではないかと思うのです。
あくまで私だけの気持ちです。活動家のかたがたは、今の世界のあり方を見込んで話を進めてこられたのだと思います。私は本当に、何も知らないままにいろんなほしいものを望んできたんだと、そう感じます。ムジュンに見えて、実はちゃんと世界はムジュンなく進んでいるのかも知れないと、多くの人たちが順番を待つエレベーターの前で思うこの頃です。そうは言っても、本当に設備がなかった一昔前から見れば、格段に街は進歩しました。私が今抱えているムジュンは、設備が整いつつある中での幸せないきどおりなのかも知れません。
日々起こるさまざまなことは、私の世界と、広い世界との接触によるものなのだと思います。
広い世界にはいろんな人がいて、私のことをよく思わない人、車いす使用者だからなんとなく離れる人、私と付き合ってみて「馬が合わない」と思う人もいるでしょう。私も同じく、普段自分の世界の価値観の中でいい悪いを決めながら生きているので、ふと広い世界で人と出会うと、自分の価値観で判断したりその人を見てしまったりしているのかも知れません。そこにもしかしたら相手のかたは、私が感じることのないムジュンを感じているのかも知れません。
広い世界は、私のことをよく知らないのかも知れません。私が広い世界のことをよく学んでいないように。
私の世界と「広い世界」は、相互関係で成り立っているのかも知れません。知り合おうとすれば理解は深まるけれど、一方通行ではすれ違ってしまうかも知れません。
広い世界を作っているのは、私も含めて一人一人であり、年月や地域性やお国柄も絡んで複雑になっていて、だからこそ多くのムジュンがあるのが当たり前な環境になっているのでしょう。
私ができることは、広い世界を少しでも理解することなのでしょう。世界はなかなか私の生き方を理解してくれないかも知れないけれど、私も広い世界のいろんなことを理解しようとしていないのかも知れないから、そこから一歩でも進もうとすることが大事なのだと感じます。それを具体的に書くなら、少し行きにくい場所でも興味があるならチャレンジすること、水が合わないと感じることを理由に価値観の違う人を拒絶しないこと、思いもしないことを言われても、すぐに毛嫌いしないでその人がなぜ私にそう言いたかったのか考えてみること、そして、落ち込むことがあってもめげないこと、でしょうか。
こうしてカッコよくまとめようとすることも、本当はビビリーな私の中にあるムジュンなのかも知れません。
夏生まれ。現在板橋区民。今は肩書きはありません。マイペースでブログに詩を書いています。
ご縁をいただいて、2冊(エッセイ1冊、詩集1冊)出版の経験があります。
あんドーナツ 筒井書房 (発行 七七舎) 1995年
誇りを抱きしめて 千書房 1997年
脳性まひの障害があります。肢体不自由児施設で9年過ごし、その後、家庭で13年過ごしました。自立生活を始めてもうすぐ30年になります。
食べることと読書と街を歩くことが好きです。
尊敬する人物は「アンリ・サンソン」。好きな小説は「十二国記」、好きな映画は、気持ちはいつも変わりますが、現在は「インビクタス・負けざるものたち」です。
ふりかえると、話を聴く側に立つ経験をすることが日々の中で多くありました。私はきっと、話を聴ける人間になりたかったのでしょう。
・ホームページ等
詩のサイト 詩的せいかつ https://ameblo.jp/sakuranoichiyou/
ホームページ http://littleelephant.cute.coocan.jp/index/top.html
よろしかったらのぞいていただけると幸いです。
・お世話になっている方々のサイト
今回書かせてもらった文章の内容に関係したり、実際のやりとりを表現させていただいた方のサイトを、許可をいただいたので載せさせていただきます。
第3回・第10回エッセイ関連
Medicine Wheel https://medicinewheel.tokyo/index.html
介助派遣を主にお願いしている団体
特定非営利活動法人スタジオIL文京 https://ilbunkyo.jimdofree.com
→エッセイ 障がいあるからだと私
音楽は誰でもない、神様がおれに与えてくれた最高のプレゼントだと思っている。
酒田に戻ると、子どもの頃にお世話になった担任の先生に無性に会いたくなった。既に何人も亡くなったと聞いたからかもしれない。
こうしてはいられないと、すぐに高校の担任宅へ訪ねて行った。失礼にも突然伺ったからか、先生は初めキョトンとしていた。いや、無理もない。デキの悪い生徒だったから記憶にないのだろう。すると、「あのビートルズの典雄君か」とおっしゃったのだ。おれはもう、これだけで涙腺が爆発してしまいしそうだった。すっかりおじいさんになられた先生との思い出話に花が咲き、会えて本当によかったと思った。いつまでもお元気でいて下さい。
また、近所の肉屋さんに行った時のことだ。見たこともない店員が「もしかして典雄君」と言うのだった。中学の同級生で、ここに嫁いで来たのだと言う。で、「まだビートルズ聴いてるの」と。
そうなのだ。前置きが長くなってしまったが、おれは手がつけられない程のビートルズかぶれで通っていたのだ。それは50年以上経った今でもだ。全然飽きることがない。殆ど毎日聴いている。色褪せることは全くない。
いくら愛した女房でも長くいると空気のような存在になるとよく言われるが、ビートルズにはそれがない。今でもときめく。新しい発見がある。どうしようもなくなる。泣けてくる。昔と違うのは、どの曲も哀愁に満ちた気持ちになるということだろうか。
中学の時にラジオから「抱きしめたい」という曲が流れてきた。弾けるような強烈なサウンドだった。じっとしてなどいられないリズム。そして、たまらなくなるハーモニー。一発で痺れた。虜になった。酒田の田舎では盆踊りの太鼓の音しか心に響いたことのなかったおれだった。勿論、英語の意味など分かるはずがない。でも、そんなの関係ねえ。「アホな放尿、犯~」(I Want To Hold Your Hand)と一緒になって口ずさんでいた。もう全ての曲が金縛りになった。
当時は、ビートルズは音楽ではない、ビートルズを聴くと不良になると大半の大人が言っていた。おれは猛反発した。そう言われれば言われる程にのめり込んで行った。それが今では音楽の教科書にも載っている。
学校が終われば友だちと夕方まで聴き呆けた。帰宅すれば皆は受験勉強に励んでいるというのに、再び深夜まで聴き続けていた。勉強などそっちのけだった。暇がなければ暇を見つけて、寝ても覚めてもビートルズだったのだ。気がついたら、おれはすっかり不良になっていた。大人の言うことは当たるものだ。おれは大きく成長していたのだ!?
多くの人は、ビートルズで知っている曲はと聞かれたら、「イエスタディ」や「レット・イット・ビー」などを挙げるだろう。これらはポール・マッカートニーの作品で、ボーカルもポールだ。ポールの曲はどれも美しく、親しみやすい曲が本当に多い。歌い方も上品でメチャクチャに上手い。ポール以上のメロディメイカーはいないのではないか。
だが、ビートルズ4人の中でおれにとって絶対なのがジョン・レノンだ。いったい何がこんなに狂おしくなる程おれの心をわし掴みにしてしまうのか。ズバリ言うなら「あの声」だ。ちょっぴり掠れた、ささくれた、あのやさしい声。この世の中にはない。グサリと胸に突き刺さる。ハートをジーンとメロメロにしてしまう。あの声質が何よりおれをたまらなくする。
例えば、初期の「ミスター・ムーンライト」という曲だ。66年の来日公演のニュースを見た人ならビートルズが嫌いでも耳にしたはずだ。羽田から宿泊先のヒルトンホテルまでパトカーに先導されていた時に流れていた曲だ。イントロなしでいきなりジョンのボーカルが炸裂する。この圧倒的な迫力といったらない。凄まじいシャウト。もうこれだけで卒倒してしまう。身動きが出来なくなるのだ。
初期のビートルズはジョンでもっていた。他にも「イン・マイ・ライフ」や「ガール」などの切ないバラード。挙げれば切りがないが、うるうると泣かせるったらない。
世界中を熱狂の渦に巻き込み、揺るがし、狂わせてしまったジョンのあの声。世界中を席巻してトップの座に躍り出たジョンのあの声は天下一品と言う他はない。
こうして人が聴いて感動する音楽というのは科学的に解明されているのだそうだ。それは「予想を裏切る、意外性」だという。
ジョンの曲はどれもゾクゾクして、とにかくかっこいいのだが、転調が多いのだという。素人のおれには分からないが、理論家の学者や音楽の先生によればあまりにも乱暴で禁じ手なのだそうだ。つまり変。褒められたものではないのだと。
ええぃ、何をか言わんやだ。ファンでそんなふうに聴こえる人は一人もいない。ジョンは言うだろう。「ロックは理屈じゃない。自由だ」と。そうだと思う。まったくその通りだ。理論が何だと言うんだ。
ジョンには「イマジン」という有名な曲がある。平和の歌だ。ビートルズは65年に英国エリザベス女王からMBE勲章を授与されている。その時、過去の受勲者が「あんな連中と一緒にされてはたまらない」と猛反発したという。それに対してジョンは「あなた方は戦争で人を殺して貰ったが、おれたちは音楽で人を楽しませている」と発言した。ジョンは後に「ベトナム戦争の英国支援に反対する」として勲章を返還している。また、来日公演のインタビューでは「若くして富と名声を得て、あと何が欲しいか」と問われ、「平和だ」と一言答えていた。なんてクールなんだ。ナイスガイ。惚れ惚れする。
ジョンはいつもウィットとユーモアに溢れていた。ナイーブな感性、素直で潔よい。飾ることがない。弱さも情けなさも全てさらけ出していた。シンプル、だからこそ奥が深い。
その反面、夢想家でちゃっかり者なのだ。やんちゃな甘えん坊、わがまま、やりたい放題、自分勝手なやつ。それらは全て、誰もが生身の人間だということを教えてくれている。
英国はリヴァプール。田舎の港町。労働者階級に生まれ、悪ガキだったジョン。瞬く間に大スターになり、欲しい物は全て手に入れた。偉大な先駆者にまで昇り詰めたジョン。我等の正真正銘のロックンローラーはジョンをおいて他にはいない。
そんなジョンはもういない。死後40年以上になる。ビートルズも解散してから50年が過ぎた。おれにはまるで昨日のことのようだ。が、今なお絶大な人気と影響力を誇り、衰えることはない。どんな形容も賞賛も決して何一つ大袈裟なことはない。
大好きなミュージシャンや憧れだった、心の支えだった大切な人が亡くなる。これは宿命であり、どうしようもないことだ。
もっともっと聴きたかった。新しいメッセージが欲しかった。ずっと一緒にいたかった。一緒に歩んで行きたかった。一緒に歳を重ねたかった。それが全て途絶えて、二度と叶わぬ夢となる。悔しくて悲しくてどうしようもない。残された名声だけが生き続けている。
レコードやCDを聴く。ビデオを観る。まだ生きていると錯覚する。そこにいる。一緒だと感じる。「おかえり」と思わず声を掛けてしまう。
もはやビートルズはおれの体の一部分だ。生活から切り離すことは出来ない。歌を聴くと安心感を与えてくれる。当時のことが鮮明に蘇る。それも良かったことだけだ。しかも何故か実際より美しくだ。心が安らぎとともにゼイタクに高まって行く。
いずれにしても、ビートルズは格別な存在だ。ジョンとポールの絶妙なハモり。それにジョージの繊細な天の声がかぶさる。リンゴのパンチの効いたドラムがリズムをコントロールする。4人が繰りなすサウンド、コーラス、ハーモニーは荘厳なまでに美しい。
それにしても、ビートルズは二十歳そこそこでこれ程の感動的で素晴らしい旋律を生み出すこと自体が信じられない。しかも次から次へと休む間もなく立て続けだった。それもいとも簡単であるかのように。ビートルズ全213曲の名曲群。駄作など一曲もない。天才たるゆえんがここにある。
ロックは多種多様で何でもありだ。自由奔放、思うがままでいい。愛と平和、抵抗、闘争、反体制、非日常などなど。逆の見方をすれば、ストレートで大真面目と言えるだろう。
ロックはまた、多くの人に誤解されている所がある。あいつはバカだ、イカレている、狂っているといった粗暴、下品、汚いなどのネガティブな言い回しが賞賛だったり、共感だったりすることだ。分っかるかなぁ。だからこそかっこいいのだよ。
勿論、ビートルズ以外にも好きなアーティストはいっぱいいる。だが、一定の距離を置くことが出来る。つまり、冷静でいられる。聴きたいが、聴かなくても済ますことが出来る。それがビートルズとなれば別なのだ。とりあえずビールなら、その後に日本酒かウィスキーに切り替えるように、最後に辿り着くのがビートルズだ。一日に一度はビートルズに触れないとダメ。気が済まない。恋しいビートルズ。
聴いてしまったらミーハーと同じだ。誰からどう思われようがお構いなし。まるで子どもだ。ビートルズに関しては全てを肯定する。ひれ伏す。跪く。すっかりジジィだというのに、永遠の中学生になっているのだ。
さぁ、残された道を突っ走るしかない。今日も明日も、未来に向かって生きて行く。
山形県酒田市生まれ。高校卒業後上京。75年国鉄入社。新宿駅勤務。主に車掌として中央線を完全制覇。母親認知症患いJR退職。酒田へ戻る。いつくたばってもおかしくないジジィだが、漁師の手伝いをしながら現在に至る。
著書
『車掌だけが知っているJRの秘密』(1999、アストラ)
『車掌に裁かれるJR::事故続発の原因と背景を現役車掌がえぐる』(2006、アストラ)
など
→エッセイ 酒田から
第3回と第4回は、2001年以降の活動をまとめた。四半世紀を実際に経験すると、長く感じる一方、ほんの一瞬で過ぎ去ったようにも思われてならない。
最終回となる第5回は、まず、モントリオール市内と会場のバリアフリーについて触れる。続けて、ICN第29回大会の報告と大会開催後にも参加可能なSpotlight On Congress 2023について紹介する。
大会開催期間中のみの経験に留まらず、「その後」も続いている(いく)こと、さらに、2025年のフィンランド・ヘルシンキ大会をも見据えて集約・展望・提言した。
モントリオール市内のバリアフリー
筆者は、諸外国へ出向くとバリアフリー環境の状況を確認することが習慣となっている。
今回も、ICN大会参加の間を縫い、会場近辺を歩いた。
市内の路上では、車椅子や短下肢装具、クラッチを使用して移動される方を複数見受けた。
冬期は厳寒となるためか、市内は地下街が発達しており、地上から地下への移動に際するバリアフリー環境の現状も観察できた。
世界最大と称されるモントリオール地下街は、いくつかの地下街や建物が連結されており、各々を接続するためと思われるスロープや階段のアップダウンも多かった。そのためか、随所にエレベーターが設置されていた。その反面、建築年数の浅いと思われる地下道は、ほぼ平坦であった。


図50 、図51 地下街入口の低エネルギーで開閉可能なドアと地下へ向かうエレベーター(2023)


図52 、図53 地下街内部のエレベーターとエレベーターがあることを示す屋内標識(2023)

図54 建築年数の浅いと思われる地下道(2023)
以下は、地上の建物である。
厳かな雰囲気をまとった建物の入口に車椅子マークが表示されており、詳細を確認したところ、裁判所であった。


図55 、図56 裁判所と入口のスロープ(2023)
ICN第29回大会 会場(モントリオール国際会議場)におけるバリアフリー
今回のICN大会の会場は1980年代の建築とあり、比較的段差や階段を多くみかけた。しかし、モントリオール市内同様、随所にエレベーターが設置され、会場では車椅子に乗った看護職や、白杖を用いて移動する看護職を見受けた。
聴覚障害に関するバリアフリーとして、小会議室の入口にはFM補聴システム(おそらく室内全体で聴取可能)設置有の表示を確認した。

図57 小会議室入口脇の壁にかけられたタブレットの右上に、聴覚障害者マーク(2003年まで使用されていたもの)とFMの周波数が表示されており、FM補聴システム設置有であることが読み取れる(2023)
開会式やプレナリー等が開催された大会場の入口には、表示を確認できなかった。また、磁気ループ(Tコイル)の敷設についても、現地における情報は得るには至らなかった。会場のホームページを確認したところ、以下のアクセシビリティに関する情報を得た。
Palais des congress de Montreal
Universal accessibility
https://congresmtl.com/en/visitors/universal-accessibility/ (2023年11月19日確認)
以下は、会場情報のトップページとなる。
ICN第29回(カナダ・モントリオール)大会会場
Palais des congress de Montreal
https://congresmtl.com/en/ (2023年11月19日確認)
今回のICN大会における聴者向けの同時通訳は、従来の会場配布のレシーバーではなく、各自の所有するモバイル機器にアプリをインストールする形で提供された。同時通訳されたICNの公用語以外の音声言語を外部端子またはBluetooth経由等で音声認識アプリを入れたモバイル機器と接続できた場合、音声認識による文字化と音声言語の通訳を同時に閲覧・聴取可能と推測された(荷物の関係から今回の接続試行は叶わず、次回以降の課題)。これらの実現は聴覚障害者のみならず、ICNの公用語を母語としない聴こえる参加者の福音ともなりえようか。
ちなみに今回、筆者は会場で日本の音声認識アプリを2種試した。その結果、1種は演者から30m以上離れていても、ほぼ正確に音声を認識、かつ翻訳されることを確認した。国際学会ゆえか、演者の発話速度は緩徐かつ発語は明瞭、更にマイクの音量大であったことも、良好な音声認識を得るに至ったと考えられた。当方法による音声認識と通訳精度が高い場合は、前述した同時通訳と音声認識の接続をせずとも(様々な機器類をつなぐ必要なしに)、モバイル機器と音声認識アプリのみで対応可能となる。
ICN 第29回大会におけるポスター発表
今回はE-Posterで、以下について発表した。
Fusae Kurihara:Current Situation of Employment for Nurses with Hearing Disabilities in Japan、ICN(International Council of Nurses)29th Quadrennial Congress、2023.7.1-5、Montreal、Canada
(概要)同意取得と回答を得た24名のうち、就労に関する9項目について完全な回答を得た20名の日本の聴覚障害をもつ看護職の現状について分析した。
統計解析と個別回答結果から、聴力程度が医学的重度となるにつれ、医療機関における就労(雇用)は困難となる傾向が示されたものの、これらは推測の域を出ない。そのような現状にあろうと、回答者は所有する看護職資格を活かし、様々な就労環境で活躍していた。また、国から発出されている看護職の平均年齢、労働時間、給与からの著明な乖離もみられず、所謂、健常の看護職等と同程度の就労を成せているといえた。
しかし、日本国内における全ての聴覚障害をもつ看護職から回答を得られていないという偏りからの限界もあった。
今後、聴覚障害をもつ看護職の就労環境における積極的なダイバーシティとインクルージョンを推進していく。
聴覚障害をもつ看護職の視点を活かしながら就労環境を変えていくには、個別事例に留まらず、「数」としてまとまり、量的データとして蓄積し、政策提言へつなげていく必要があると考えている。各々の積み上げてきた臨床知は「Nothing
About Us Without Us(私達ぬきに私達のことを決めないで)」のマインドで、私達自身の言葉で社会へ延べ伝え、結果として、既存の枠に留まらず、看護職の世界で認められる当事者独自の専門的なキャリアの確立を期待している。
これらの結果を、よりよい未来を創るために活かし、よりベストな形で次世代へ引き継ぎたいとも考えている。
このエッセイをご覧になった方のうちに聴覚障害をもつ看護職と看護学生のおられた際は、以下の「お問い合わせ」先より、お気軽に、ご連絡願いたい。
お問い合わせ
フォーム https://ws.formzu.net/fgen/S96559754/情報提供のSNSを運用中
Twitter @fusaek または @jndhhmp2020
Facebook fusae.kuriharaまた、上記の調査・研究の概要は以下にて順次公開しており、必要時、参照されたい。
医療従事関連国家資格を有する聴覚障害者の就労実態に関する研究
http://www.reddy.e.u-tokyo.ac.jp/act/employment_for_hearing_impaired.html (2023年11月19日確認)
Spotlight on Congressのお知らせ等
今回のICN第29回大会の模様(写真・動画)は、大会期間中より、SNSへ投稿されていたが、後日、以下のページに集約して掲載された。
ICN Congress 2023 Montreal
Photo Gallery
https://icncongress2023.org/photo-gallery/ (2023年11月19日確認)
ちなみに、今回(2023年)の参加を通じて最も驚いたことは、オンライン化であった。2009年までは、郵送を用いた連絡が主であったものの、2011年からウェブ上で完結するようになっており、それらは加速度的に進歩していた。

図58 手前から、1999年、2001年、2009年のICN大会前に本部から受け取った封筒(2023)
また、今回のICN大会は2024年2月頃まで「Spotlight on Congress」(主要なセッション、開会式・閉会式、2000を超えるポスター)の形で、引き続き、参加可能となっている(大会参加登録済の者も閲覧可能)。詳細は、以下URLをご覧いただきたい。
ICN Congress 2023 Montreal
Spotlight On Congress 2023
https://register.spotlightoncongress.icncongress2023.org/icn-world-congress-2023 (2023年11月19日確認)
次回以降のICN大会は、オンライン上で対面と同等の経験、または何らかの技術革新により、より対面に近い形の参加も可能となるように思われてならない。
また、現行、ICNの公用語は3つ(英語、フランス語、スペイン語)である。昨今、翻訳技術の革新は目覚ましく、次回以降は、参加者個々の母語からICNの公用語へとスムーズに翻訳され、言語面の障壁はより小さくなった状態の交流も進むと期待される。様々な参加方法の選択肢や高度な翻訳技術等は、国を問わず、多様な背景を有する看護職への配慮・支援にもつながりうるため、大いに歓迎したい。
今後、上記の実現を見る場合は、今まで以上に日本の看護の教育や雇用、歴史的背景をはじめ、世界の看護職等から求められやすい情報を収集・理解し、さらに、国内の看護職等との交流を密に行い、最前線の情報を国の代表として心得ておく必要はあろう。もちろん、多国の現状や世界の潮流を身に付けておくことはいうまでもない。
ICN 第29回大会から第30回大会へ
日本看護協会出版会から発行されている日本看護協会の機関誌「看護」2023年10月号で、日本の参加者は160名と報告された1。過去の経験に照らすと、会場で出会う日本人は少なく、実際に渡航した者は限られていたのかもしれない。
今回の参加経験(当エッセイの第1回を改めてご覧いただきたい)から、次回のICN 第30回大会に向け、日本看護協会の1会員として以下を切望する。
- 個人情報に触れない範囲で事前に参加者数や大まなかな属性(研究者、医療機関勤務、看護学生)等、公開可能な情報を周知
理由:他の教育または医療機関から複数の参加者があることを示すことで、休暇申請の根拠となり得る、看護学生の公休申請にも有効と考えられるため- 渡航前に国内参加者間で情報交換可能なウェブ空間を設置
日本看護協会会員はキャリナース2への登録が求められており、既存の環境を活用理由:キャリナース登録未の同会会員は登録の契機となりえるため
会員となっていない看護職や看護学生はICN大会参加者として同空間を仮IDで提供し、キャリナース登録者と同等の権限を与える
日本看護協会からの個別支援は、経験上、未来の入会につながる可能性が高いと考えられる
そのうち、特に、日本看護協会の看護学生会員枠の設置[再設置・復活]を求めたい)- 渡航前の参加説明会の開催(オンライン・対面)
理由:以前は日本看護協会主催のツアー(大会登録代行を含む)もありつつ、近年の設置はないため
前述した「2.」の環境を実現可能であった場合、参加説明会開催に際する協力者(過去のICN大会参加経験者を想定)を得ることも可と思われる
(日本看護協会国際部ご担当者様の負担軽減へもつながる)- ICN大会開催の広報強化
理由:長年に渡り、ICN大会の開催報告は日本看護協会の機関誌「看護」の特集として取り上げられていたものの、2023年は取り上げられていないため
ちなみに、次回のICN大会は30回目の節目、2025年6月9日-13日 フィンランド ヘルシンキで開催される。
今回のエキシビジョン会場には、次回大会のポスターもあった。

図59 次回(ICN第30回)大会のポスター(2023)
さいごに
12年ぶりのICN大会参加・発表を契機として、この度、貴重な報告(当エッセイ)の場をいただいた。
松井彰彦教授をはじめ、松井研究室各位、看護学生時代から今へと連なる多くの友人達をはじめ、関係する全ての方へ、感謝申し上げる。
今回のエッセイ執筆を通し、改めて、2025年のICNフィンランド・ヘルシンキ大会、それも記念すべき節目となる第30回大会への参加を目指し、看護学生や若手看護職等との参加前からの交流を行いたく、その準備等へ関わることの希望を抱いた。
また、このエッセイは、一看護職の経験をまとめた歴史、さらに、次世代へ引き継いでいく際の「襷」として活用されることを願ってやまない。
閑話休題:今回のICN大会会場はモダンながらも、随所に遊び心を感じた。会場内に、こうしたブランコ形式の席が複数あり、それらに揺られながらランチや議論等、思い思いに過ごされている姿は印象的であった。

図60 会場内の一角(2023)
この場をお借りして、大切な友人へのメッセージを記したい。
過去のICN大会へともに参加し、切磋琢磨した友人のうちには、近況報告をはじめとして今後の相談すら、叶わない方もある。今年(2023年)7月の渡航時、機内の窓から満月直後の月に照らされた幻想的な空と雲を眼にしたとき、「その方は、このような綺麗な空を眺められるところにいるのだろうか。どうか、私たちを見守っていてほしい。」との思いが不意に浮かんできた。報告や相談は叶わずとも、在りし日のその方との交流を通じて志を同じくしていることは、今も変わらないと信じている。

図61 機内の窓から眼にした満月直後の月に照らされた幻想的な空と雲
参考ウェブサイト、文献
大学に合格して数日は、教職員とすれ違うたびに労いの言葉をもらった。生徒が大学進学するのは非常に珍しく、お祝いムードになっていた。受験カリキュラムでは不足している箇所があった。そのため、3年の2学期末から卒業まで教科カリキュラムが続いた。
支援費制度の説明会
平成15年(2003年)に支援費制度が施行されることになり、福祉制度が大きく変わることになった。その内容を保護者に周知させる目的で、3学期に入って学校全体の保護者説明会が開かれた。
「障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、平成12年の法律改正により、これまでの「措置制度」から、新たな利用の仕組み(「支援費制度」)に平成15年度より移行することとされている。支援費制度では、障害者自らがサービスを選択し、事業者との対等な関係に基づき、契約によりサービスを利用することとなる」
支援費制度の概要
障害者(児)が市町村からの支援費支給を受け、利用したい福祉サービス事業所と契約できる制度である。事業所への支払に対しては支援費が支給される。支援費は福祉サービスを利用したい障害当事者にとって欠かせない制度である。また、20歳を超えると障害者年金の受給が可能になる。支援費と年金が障害者の自立、障害当事者と家族の生活を支える型になった。
支援費制度と福祉サービスの利用を見据えて、進路の先生からヘルパー事業所を紹介された。主に外出の支援を行っている事業所で、体験で数回ヘルパーと外出した。家族と先生以外の人からの介助は、私にとって初めての経験だった。この利用体験をきっかけに、私は事業所と契約を結んだ。外出をしたいときにはヘルパーを利用するようになった。
学生生活に向けての打ち合わせ
入学前に在籍先の学科に呼ばれた。学部学科の校舎見学と、学生生活に関する打ち合わせだった。教授から学部で提供できること、できないことを明示された。
「ハード面での配慮は2点提供できます。まず、車いすで利用できる移動式テーブルの手配が可能です。受講する講義が決まったら、事務局で講義の時間・教室番号を伝えて、移動式テーブルの配置を申請してください。次に、車で通学するための入校許可証を発行できます。しかし、学生生活、講義中の介助までカバーするのは難しいです。可能であれば家族を講義に同伴してほしい」と、伝えられた。私自身、親に付き添われる恥ずかしさから、別の方法を探す必要があった。
また、「大学に要望はありますか」と尋ねられたので「身障者トイレのウォシュレット設置」を伝えた。打ち合わせのいきさつを知り、進路の先生から神奈川県障害者自立生活支援センター(通称KILK)を紹介された。障害者の自立に向けての助言、情報収集を行っているNPO法人である。大学生活での介助に関して「学内にあるボランティアサークルに頼るのもよいですよ」と、助言をもらった。
KILKで紹介されたサークルの部長に話をつないでもらい、電話で相談した。「サークルの打ち合わせで、サポートの必要な障害学生がいることを伝えておきます。冨田さんの受ける講義の時間に、手の空いているメンバーがいるか調整します」と前向きな返答をもらった。
卒業
受験科目に強い元高校教諭の教員、入試・社会生活面をサポートする進路の先生、クラス内外の教員たち、様々な励ましの声があって大学受験合格にこぎつけた。大学生活の準備に追われる中、あっという間に卒業を迎えた。無事に神奈川県のA養護学校を卒業した。在学中の私は受験と自立訓練の日々を送った。
とにかく忙しかった2022年
前回が2021年の8月なのでそれから一年と半年近くが経ってしまいました。連載なのに遅筆で言い訳のしようもありません。
でも書かせて頂くなら本当に2022年は忙しかったです。まず春に定年を迎えて退職しました。定年退職したのに忙しい?と思うかもしれませんが、そうなのです。退職して、引き続き同じ研究所に非常勤嘱託という立場で再雇用。これがくせ者でして、月給は何十年も前の就職したての頃と同じくらいの金額になり、退職経験がある方は皆さんご存じだと思いますが、税金だけは前年度の所得に応じた金額を源泉徴収されるので、突然激減した額が源泉徴収でさらに半分になり、殆ど貧困世帯なみの所得になりました。ですのでそれだけではやっていけず、非常勤の仕事を他にも三つやっていた(大学の非常勤講師です)おかげで、なんとか食いつないできました。
そして本職の非常勤化というのも私のような研究職だと他の選択肢がないのですが、週の勤務時間が29時間以内でないといけないのです。そして残業は原則として認められず、認められたとしても週に1時間だけ。さらにひと月あたりの勤務日は15日までという制約もかかったりして、その限られた時間内にこれまでと同じ研究会の主宰や研究論文執筆などをこなさないとなりませんでした。やらないとならない仕事の量は全く減っていないので、それを短い時間ないにこなさないとならないという状況の中、むしろ労働強化になったというのが実際のところです。
仕事でこんな大変な状況になったのにも関わらず、住んでいるマンションでは管理組合の前の理事長から次の理事長をやってくれと頼まれ、4月から理事長。毎月の理事会を仕切り、議論があっちにこっちにいくのを整理しながらなんとか決めなければいけないことを決めるように議論を持って行く。それを地域の公的派遣の通訳の方(仕事の時にお願いをしている学術通訳の方々とはまた違うコミュニティ通訳の方々)を介して、実施。これはかなりの精神的ストレスとなり理事会が終わった後は疲れ果てて、その日はもう他の仕事はできなくなる有様でした。
研究会や学会も
そうした中、年度末には、主宰している研究会で原稿を書いて頂く方々の中から二人もが精神的にダウンして原稿が締め切り日に提出されず、それをどう収拾するかで職場の各部門と折衝するというおまけまでついて本当に大変な毎日でしたが、それもなんとか少しだけ先が見えてきて、マンションの管理組合の最後の理事会も終えてあとは総会だけとなったのが現在の状況です。
そんな毎日の中、私のメイン学会である国際開発学会の大会で「中東の『障害と開発』」の特別セッションを、職場における昨年度までの研究成果をもとに開催し、また別にメイン学会の日本手話学会では日本手話の関西変種(つまり方言)の興味深い事例について報告をしました。これは今月の社会言語科学会でもさらに突っ込んだ言語学的分析を報告する予定です。他にも職場ではイスラエルの「障害と開発」の研究者の先生と日本の研究者とを切り結ぶ国際セミナーを開催、REDDYの松井先生にもご講演頂きました。他にREDDY自体でも「障害と開発」に関わる他の先生の講演の企画と司会もやりました。自身も大きな講演として1月に250人規模のオンラインでの講演で日本手話のRSとCLについて自分の過去の研究をもとにした講演をし、先週の日曜には「社会科学、障害学、ろう者学-その系譜と展開」という参加者450人というオンライン・シンポジウムでの基調講演と休む間もありませんでした。
海外調査に行けないという雑感
そんな2022年度でしたが、実は私の仕事上のデータ収集のメインである海外調査が一度もできずじまいのまま終わりそうです。もちろん大きな理由は新型コロナですが、渡航先の現地が割と大丈夫そうになって行こうとすると日本の新型コロナが流行期に入って、渡航して良いものか分からないという状況になりました。日本と現地と両方の感染状況を見比べながら渡航は考えないとなりません。特に現地でインタビューをする相手の皆さんは障害当事者の皆さんであることも多いので、私が感染源になってもいけませんし、現地で感染して病院やホテルで帰国延期の待機になってもいけない。けっこうこれはシビアな条件でした。新型コロナだけでなく、アフリカのウガンダについては一時、エボラまで発生して、現地情報がメディアくらいしかないのでちょっと待てなどと思っているうちについに年度末で原稿書きに集中しないといけなくなってしまいました。そんな感じで結局、どこにも行けずじまいというわけです。
海外調査というのは、体調の管理も必要ですし、飛行機という閉鎖空間に滞在することになるので換気はされているといってもそれでも一時期は搭乗客の多くが感染してしまったケースもあったりで、とにかく長時間のフライトがある場合には気を遣うことになります。現地に到着してからも新型コロナのような感染症の時期の渡航などの経験がないので、自分の体調も大丈夫だという状況じゃないとなかなかいけません。でも職場同僚も含め行っている人は行っているし、行っていない人は行っていない。職場でもフィリピン・プロパーの研究者はだれもまだフィリピンに行っていないという状況です(ただ不思議なのは、フィリピン・プロパーではない人は数は少ないですが行っている人もいるので、もしかしたら街中で調査をするような私のパターンとは違って、大学や研究所など特定の場所だけで仕事ができる方が行かれたのかもしれません)。
おわりに
エッセィというと2つの意味があるようで、論文のように堅くない文をさして言うケースと論文もエッセィというケースと両方があるようです。これまでの連載はどちらかというと後者の感じで書いていましたが、今回は前者のイメージで書いてみました。どうかご容赦ください。
政府がマスクの規制などを緩めるそうですから、それでも再度の流行ということにならず、ウィルスも弱毒化して少しでも2019年頃の状態に戻れることを祈るばかりです。
当事者(表):今日は完全に失敗だったな。普段は床につけばすぐに寝付く方だけど、目が冴えて眠れやしない。ああ失敗だったなあ。
当事者(裏):私が悪かったのかしら。
当事者(表):いや、悪いのはぼくの方だよ。あなたに責任はない。
本人:なんだよ、二人で譲り合って。てか、当事者の君が二人になってるね。それに表と裏ってなんなんだよ。話しっぷりに男女があるみたいだし、どうなってんだよ。
当事者(表):今日の昼間、『障害者のリアルに迫る』ゼミにゲストスピーカーとして呼ばれて、話してきたわけだよね。
本人:そうだったよな。
当事者(表):今日の出来事について当事者としていろいろ考えているうちに、自然と二人になってきて・・・
当事者(裏):当事者だって一枚岩じゃないってことを分かってもらうために、あえて私も登場することにしたの。
本人:ふーん、そういうことか。夜中に寝床で3人でごそごそ話すってのもいいか。普通は川の字になってって言うけど、この場合はなんなんだ?まあ、いいや。で、失敗、失敗ってなんでそんなに落ち込んでるんだよ。
当事者(裏):そう、ひどい落ち込みようよね。今日、東大の学生さんの前でうまく喋れなかった、って反省してるわけなの?
当事者(表):反省っていうか、あてが外れたというか、外れるような当てを抱いた自分がバカだったというか。
本人:よく分かんないなあ、怒らないで黙って聞くから正直に言ってごらん。
当事者(裏):そうよ、せっかく私も出てきたんだから、応援するわよ。さあ、勇気を出して、言っちゃえ、言っちゃえ。
当事者(表):『障害者のリアルに迫る』ゼミのことについては以前から知っていて、なかなかユニークなことをやってるなと注目してたんだ。
当事者(裏):そうよね。学生さんたちが障害者にどんなふうに迫ってるんだろうと興味があったよね。
本人:それに君たちのというか僕のというか、知り合いも何人かゲストスピーカーとして以前に話しているようで、親近感を持ってたんだよね。
当事者(表):たまたま縁をたどって、ゼミの運営担当のOさんからゲストスピーカーの出演依頼があった時はとても嬉しかったんだ。
当事者(裏):アルコール依存症の当事者として話してほしいというオファーだったのよね。
本人:Oさんは、僕が実名で書いて雑誌「統合失調症のひろば」に連載している『アル中ソーシャルワーカー誕生秘話』という文章を読んで君に関心を持ってくれて、スピーカーの依頼をしてきたんだったね。
当事者(表):そう、Oさんはとても深く君の文章を読み込んでくれていて、さすが東大生って思ったね。
当事者(裏):スピーカー出演の前に2回ほどオンラインで打ち合わせしてたけど、あなたとてもうれしそうだったわよ。
本人:良き理解者を得た、という感じだったのかな。
当事者(表):そうだね。Oさんの読みはとても深くて、君の文章の中から理路整然とイシューを取り出してきて、こんな話をゼミでしてくれないかと具体的に提案してきてくれた。
当事者(裏):それはよかったじゃない。それで、失敗、失敗って言ってるのは、そのOさんが出してくれたテーマに沿ってうまく話ができなかった、っていうこと?
本人:うん、そんな感じがするけど。
当事者(表):いや、そうじゃないんだ。
本人:じゃあ、なんなんだ。そこをじっくり聞かせてもらおうじゃないか。
当事者(表):初めはOさんが上手にテーマを設定してくれるので、それに沿って話をしようと思ってはみたんだ。
本人:初めは、って、後から変わったってことか?Oさんに悪いじゃないか。
当事者(表):本人たる君が書いている『アル中ソーシャルワーカー誕生秘話』は、「ある男が28歳でアルコール依存症に罹患し、その後断酒を続けながらソーシャルワーカーとしての人生を歩んで行く半生記」とまずは言えるわけだけど。
本人:そうだね、アルコール依存症当事者とソーシャルワーカーが自己内対話をするという形式で進んでいて、もう連載9回目になるね。
当事者(表):その文章を読み込んで、Oさんは例えば『精神疾患が「健常から切り離された何か」として捉えられる現状を変えるため、当事者、そして、ソーシャルワーカーとしての経験を聞きたいと思いました』という問題提起をしてきた。
本人:すごく真っ当なテーマじゃないか。
当事者(表):そうなんだ。語り甲斐がありそうな、とても素晴らしいテーマ設定だと思う。
当事者(裏):だけど、あなた、そこでちょっとひねくれちゃったんだよね、きっと。
本人:そうなのか?
当事者(裏):そうなのよ。そのひねくれのせいで、こうして私が当事者(裏)なんていうキャラで登場することにもなったわけよね。
本人:どういうことだ、え?
当事者(表):『「障害者のリアルに迫るゼミ」のリアルに迫ってやろう』という野望を抱いちゃったんだよ。
本人:なんだよその野望ってのは。
当事者(表):「障害者のリアルに迫るゼミ」は世の中で障害者と呼ばれる人たちにナマの真実を語ってもらおうということでとても真面目で誠実な東大駒場の学生さんたちが自主運営している。
当事者(裏):その若い学生さんたちにちょっと意地悪な気持ちを抱いちゃったんだよね、あなたは。
当事者(表):君にそうズバッと言われると何も言い返せないけど、たしかに、障害者のリアルに迫るとか言ったって、君たちは所詮、エリートの東大生だろ、という気持ちはあった。
当事者(裏):上から目線から何言ってんだ、みたいな?
当事者(表):それもちょっとあるけど、それ以上に障害者が自分のことを人前で語ることの重みというものを君たちは改めて問いかけたことがあるのだろうか、という気持ちが強かったね
本人:そうか、当事者として名指されることのそもそもの重みへの想像力ということかな。
当事者(表):そうだね。Oさんとの打ち合わせで、障害者とか当事者とかいうけど、そもそも東大生なんて世間から見れば知的レベルでは少数派で、マイノリティという意味では、重度の知的障害者と変わらない障害者じゃないか、という話をした。
本人:うん、その話は僕も陰で聞いていたよ。ちょっと挑発的なギャグにも聞こえるけど、一面の真実はついているね。
当事者(表):知的レベルが高い人は人間としてプラス価値を持っていて、逆に低い人は障害者と呼ばれるなんて変な話じゃないか。東大に行くような知的レベルの人なんて圧倒的に少数派で、人口比では重度の知的障害者とどっこいかもしれない。東大生も重度知的障害者も同じ障害者だ。そう考えれば、東大という看板を背負ってゼミに参加している学生さんにも何らかの当事者性があるはずで、そこにツッコミを入れたくなっちゃったんだよね。
当事者(裏):一方的にあなたが話すんじゃなくて、せっかくのゼミなんだから、なるべく参加型で進めたいというのもあったのよね。
当事者(表):それとさっき言いかけたけど、当事者として人前に身を晒すことの苦味というのかな、そういうことにもきちんと気を回してほしいというのもあったね。
当事者(裏):名指されれば当事者を敢えて演ずるけれど、それにも色々葛藤があって気持ちは複雑だってことよね。それでまあ、(裏)として私が登場するみたいなことになっちゃってるんだけどね。
当事者(表):まあ、一言でいうと「『障害者のリアルに迫る』ゼミに迫ってやる」という気負いを持って本番に望んだわけだ。
当事者(裏):それがつまらない野望だったということが、やってみて分かったわけなのよね。
本人:『障害者のリアルに迫る』ゼミには全くもって迫れなかった、ということだね。どうしてそうなったんだ?
・・・・・・・・・・
当事者(W大):それはさあ、ゼミの途中で僕が顔を出さざるをえない展開になったんだよね。もう夜中になってるね。続きは一夜明けてからにするか。
生年出身地情報:1953年、神奈川県藤沢市生まれ。
ジェンダーアイデンティティ情報:男を自認していたが、ここ数年女性性が20%くらいあると感じている。
当事者関係情報:1981年、28歳でアルコール依存症を発症し、入院治療。その後断酒会の活動を続けている。
経済関係情報:地元の社会福祉法人で障害福祉関係の仕事をしている。社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の資格を持ち、現在は週2日の非常勤勤務。
社会関係情報:知的障害者の本人活動の支援者を30年ほど続けている。ここ数年障害者・高齢者の意思決定支援の問題に関心をもち、理論的・実践的な活動を行っている。
生活関係情報:98歳の母親と仲良く二人で暮らしている。今年度は町内の組長を務めている。
11月某日、私のところに一通のメールが届いた。差出人は研究室の塔島さんだ。これ自体は珍しいことではないが、
「REDDYのエッセイページに載せるものがないのでなんか書いて(注:筆者の超意訳)」
という内容がとても丁寧な表現で送られてきた。
これは私にとっては一大事である。文章を書くことは得意ではないのだ。できることなら一生避けたいことの一つである。しかも相手は塔島さんである。「塔島ひろみ」でググればわかることだがいくつもの著書を世に送り出している作家である。
一方私と言えば小学生の頃作文が書けず2週間泣き続けた挙句「僕は作文が書けません。だからこの作文も書きません。」とだけ書いて提出した。中学生の頃の読書感想文は文学作品を読んでどう感じたかなんてことは一切書かず、読みたくもない本を読まされたことに対する苦痛や愚痴に始まり既定の字数を埋めるために漢字をひらがなにして字数を増やしたり、最後には「先生は宿題を出すだけで後は休んでいればいいから楽でいいですね」と内申なんざクソ食らえの勢いで提出したものである。大学入試では「寅さん」に関する問題で小論文が出たが大したことも書けるわけがなく、他の科目も全滅だったので当然落ちた。しかしどういう運命かわからないが、その18年後に、落ちた大学から生涯唯一の就職活動の「合格通知」を受け、今も仕事をしているのである。
メールはできれば見なかったことにして一生スルーしたかったのだがそうもいかないので、「とりあえず何か書きますが期待しないでください」と返信した。
ダメなら有休全部使って逃亡するか?といっても逃亡先もないのでパソコンの前で抜け殻になっているだけなのだが。
さて、エッセイの題材を何にするか。コロナ禍に突入してからはほぼ引きこもりの生活である。リハビリと診察で病院に行く以外はほぼ家にいる。大学への通勤も3回だけ。2020年の健康診断と2021年の健康診断と2022年の健康診断である。そういう状況であるから、仕事と趣味で毎日10時間パソコンの前にいるという生活が続いている。
そんな中コロナ関連の様々な記事を目にするのだが、とにかくとんでもない記事をあちこちで見かけている。どう見てもウソとしか思えない記事をSNSで発信してしまう。しかも発信力の強いインフルエンサーと呼ばれる人が何の疑いもなく垂れ流してしまうから手に負えない。さらにそれを多くの人が何の疑いもなく拡散してしまう。
そのような記事や動画などを見るとわかるのだが、そのほとんどは元になる記事や論文などの誤訳や文脈の取違い、科学的知識の欠如によるものである。
その一つの例として、新型コロナウイルスのワクチンの中にはメッセンジャーRNA(mRNA)というものが使われているが、その原料(シュードウリジン)を日本のしょう油メーカーが発酵の技術を使って作っているという記事について「しょう油の中には有害物質が含まれているからもう二度としょう油を食べない」と発信した人が何人かいたのである(元々ワクチンが身体に有害だという思想を持っている人達のようだ)。シュードウリジンは聞きなれない化学物質なので何か特別なものではないかと思ってしまうが、あらゆる生物のRNAに組み込まれているごくありふれたものであり、少々強引ではあるがうまみ成分として知られるイノシン酸やグアニル酸も仲間である。
医薬やワクチンに対してどのような思想を持とうが個人の自由であるが、バイアスをかけずに物事を科学的に考えるということは大切である。
まあ、学者とか専門家と名乗る連中にも悪質なのがいて、査読前の論文(多くの人にとっては重要な情報と錯覚してしまうがシロクロついてない主張なので「※個人の感想です」と変わらない)を根拠にしていたり、現実とかけ離れた数値予測を出して人々を不安にさせながら何の検証もせずに逃げてしまったり、データを都合のいいところだけ切り取ったり縮尺を変えて・・・(これ以上書けない)
しかしながら、私の甥や姪を見てハッと気づかされたことがある。
世の中の大半の人にとっては、理科教育というのは高校の基礎科目で終わるのである!
そこから先は「理系」という特殊な世界に入っていくという認識なのだ。
そりゃ、自分にとってはごくごく当たり前のことであっても、世の中の人にとっては新鮮なものなのかもしれない。
ところで、柳田理科雄さんの「空想科学読本」という本がある。たまにネット上の記事で見るだけではあるが、漫画やアニメ、特撮から昔話に至るまで多くの作中シーンや設定を科学的に検証するという面白い内容である。小学生の頃にこの本があったら読書嫌いの私でも全巻読破していただろう。さすがにこの域には及ばないが、私も一応博士(理学)を名乗っているので新型コロナに関するいくつかの噂についてわかる範囲で解説したいと思う。
まずはこちらの質問から。
Q.新型コロナのワクチンを接種したところ、磁気を帯びてしまいました。鉄製のものが体に張り付いてしまいます。どうすればいいでしょうか?
A.MRI検査にまつわる怪奇事件が起きていないか調べてください。
MRIとは強力な磁石を用いて身体の中を調べる画像診断装置ですが、非常に強力な磁石(電磁石)を使うため磁力のあるものを近づけることは禁止されています。検査時に金属(鉄、ニッケル、チタンなど)製のものが付いた服や下着類、アクセサリー、あるいは肩こりに使う磁気治療器などを外さないといけないのはこのためです。
MRIでよく起こる事故として、ストレッチャーや車いす、酸素などのボンベをうっかり近づけて吸い寄せられる(場合によっては飛んでいく)ことがあるため、磁力を帯びた人が近づけば装置に衝突する恐れがあります。
また、鉄分を含む染料を使っている可能性があるため入れ墨をしている人は検査できませんし、マスカラなどアイメイク用の化粧品には鉄分が入っているものがあり、MRIで化粧した部分が発熱したり火傷することがあります。まつ毛が燃えたという話も聞いたことがあります。機器との衝突を避けられたとしても検査中に全身大やけど、あるいは人体発火をするかもしれません。
検査を受けて何も起きなければ磁気は気のせいということです。検査が怖いという人はそのような事故が起きていないか調べることを勧めます。
続いてはこの質問。
Q.新型コロナのワクチンには有害物質が入っているらしいので打ちたくありません。どうすればいいですか?
A.本当に入っているかどうか調べればいいと思います。
「新型コロナのワクチンには××(有害物質の名前)が入っている」という画像や動画はかなりの数出回っています。中にはDHMO(Dihydrogen monoxide :
一酸化二水素、つまり水)なんてものまであります。物質名がわかっているということで、今の分析化学の技術であれば実際に入っているかどうかは簡単にわかります。ワクチンに懐疑的な医師は当然いますので、その人たちがワクチンを手に入れて分析しているはずですが、実際に有害物質が出たという分析結果は見たことがないので推して知るべきだと思います。分析装置としてはガスクロマトグラフィーなどの分離装置と質量分析計(GC-MSなど)で十分でしょう。重金属であれば蛍光X線装置を使えばわかります。大学や検査機関に行けばあります。私も学生の頃に使いました。
マイクロチップは世界最小のもので0.05mmの大きさで水に溶けないので生理食塩水を入れた後に光を当てれば見えますし、注射針に入らないもしくは途中で詰まるでしょう。
「ワクチンにはウイルスが入っていて、接種すると感染してしまう」と言っている医師もいるようなのですが、ウイルスも水には溶けない(注射針は通過できる)のでマイクロフィルターでろ過して電子顕微鏡で見ればわかります。その前に、薬剤の入った瓶の中というウイルスにとっては非常に過酷な環境でどうやって生かしておくか疑問ですが。
なお、「ワクチンを接種した人から出ている化学物質の影響で体調が悪い」と主張する人もいるようですが、これも周辺の空気を採取して調べればわかるかもしれません。
いずれにしても論より証拠、百聞は一見に如かず。Seeing is believing.
次の質問。
Q.新型コロナのワクチンはいまだに治験中だという話を聞きました。人体実験は嫌なのでワクチンを打ちたくないのですがどうすればいいですか?
A.ワクチンが治験中だとすると、薬局で処方される薬や売られている薬のほとんどは治験中ということになります。その上で判断してください。
少し専門的なことになりますが、臨床試験の第III相と第IV相を混同している可能性があります。臨床試験には第I相、第II相、第III相、第IV相があります。第I相は少数の健康な人を対象に安全性と有効な薬の量を調べます。第II相では少数の人(病気の治療薬の場合は病気の患者)を対象に効果があるか調べます。第III相では比較的多くの人(患者)を対象に本物の薬と偽物の薬を使って本当に効くかどうか調べます(もちろん第II相や第III相でも安全性を調べている)。ここで薬の安全性と有効性が確認されれば承認、販売となります(特例承認の場合は少し違うが、安全性に疑問のあるものは治験中止、承認されない)。
治験は第III相までのことを示し、第IV相は「製造販売後臨床試験」と呼び、発売後に治療効果や副作用などの情報を集めています。薬のロットが変わった場合にも行われることがあるので長期間(場合によっては製造販売終了まで)に及びます。
ワクチンの治験は終了しておりますが医薬品としてのデータを収集しているということです。
(※医学や薬学の専門家からツッコミが入る可能性がありますが、私の出身である理学部化学科的にはこれでだいたい通じています。)
4つ目はこの質問。
Q.PCR検査をする際に検体としてただの水道水を入れて送ったところ陽性と判定されました。これって水道水の中にウイルスが入っていたということでしょうか。
A.これだけでは断定できませんが、人間が検査しているので「技量の差」は出ると思います。
陰性の証明を得るためにだ液ではなくただの水を入れたこと自体問題があるとは思いますが、どこかから陽性になる検体が混ざったと考えるのが自然です。PCR検査は機械を使った検査(機器分析)なので、最初に疑うのは機械に付いていた(残っていた)ということです。私は学生の頃に様々な機器分析をやりましたが、測定する試料(検体)の質とともに機械についても適正な結果が出るように常に気を付けておりました。検査に使う試薬やキットは多くが1回限りの使用(使い捨て)ですが、機械は非常に高価ですから使い捨てということにはいきません。そのためいつ誰が使ったか記録しておく必要がありますし、定期的なメンテナンスが必要になります。現在PCR検査場があちこちにありますが検査施設の管理がきちんと行き届いているか、十分訓練された人が測定しているかどうかわかりません。雑な検査場で検査すれば当然精度は下がります。
「誰がやっても陽性になる検査試薬が混ざっている」といった陰謀論めいたことを言う人もいるようですが、そんなことをやればすぐばれます。
次はこの質問。
Q.新型コロナワクチン接種後に○千人亡くなっているそうです。やばくないですか?
A.そんなに少ないはずがありません。あと3ケタ多いと思います。
人口動態統計の数値とワクチンの接種率を考えれば、ワクチン接種後1年半以内に国内だけで100万人以上の方が亡くなっているはずです。ほとんどの場合は接種と無関係ですが。つまり、「ワクチン接種後」というのは5分後も3日後も3カ月後も1年半後も全部入っています。「ワクチン接種後3か月以内に死亡」という記事が出ればさもワクチンが原因で亡くなったと印象付けてしまいますが、日本では年間1%の人が亡くなっているので3か月あれば何もしなくても400人に1人亡くなります。日本では約8400万人の人がワクチンを3回接種している(出典:首相官邸HP)ので、単純計算で3か月以内にそのうち約21万人は亡くなっていることになります。まあ、ワクチンを打つ人はある程度健康な人なのでもっと少ないかもしれませんが、1000人、2000人という単位ではないでしょう。
とはいうものの、ニュースで見る限りは10人の方がワクチンの副作用で亡くなったと認定されて補償金が支払われています。それ以外にも副反応の見舞金が数千件支払われています。実際どんな薬や注射でも数百万~数億分の1ぐらいの確率で死亡するリスクはある(もっと死亡率の高い薬も実際ある)ので、リスクと効果を天秤にかけて行動することが大切です。
最後はこの質問。
Q.急速に作られた新型コロナのワクチンって本当に安全なのですか?今は大丈夫かもしれないけれど10年後も安全と言えるのですか?子供たちに何かあったらどうするのですか?
A.その通り。10年後のことはわかりません。あ、お子さんが食べているそれ、去年出た新品種ですね。
何が言いたいかというと、10年先も100%絶対安全というものは世の中にはほぼありません。ワクチンだけが特別なものではないということです。
新型コロナワクチンはメッセンジャーRNA(mRNA)を身体に注射するという新しい方法を使っていますが、これは新型コロナ対策で急に出てきた技術ではなく何十年もの研究の積み重ねで作られたものです。もちろん創薬の勉強を学生の頃に少ししたのでこのワクチン開発が異常に早かったのはわかりますし、安全性に疑義を唱える人がいるのもわかります。ただ極論を出している人は文章が理解できていない、あるいは科学を理解できていない可能性が高いと思います。医師だってピンからキリまでいますから。
ところで、最近野菜や果物の新品種が毎年たくさん出ていて、例えばりんごでは色や大きさ、味や香りがそれぞれ違いますが、これは体内で違う化学物質を作っていることを意味しますし、それぞれが今までになかった新しい遺伝子を持った生き物だということになります。もちろん多くの年月をかけて送り出されていて当然安全性についても調べられているわけですが、それでも10年後の安全性に絶対はありません。
また、「コロナワクチンで得た免疫はものすごく毒性が強いので解毒しないと短期間で死んでしまう」という情報が流れていますが免疫そのものを「解毒」する方法はありませんし、「解毒」に使うものに効果がないどころかかなり有害なもの(二酸化塩素の経口投与など)が含まれているのでお勧めしません。
それとイベルメクチンやアビガンをやたら推している人たちがいるようなのですが、イベルメクチンは寄生虫に対する薬なのでウイルスに効くというのは無理があり、比較的安全とは言われていますが副作用はありますし、使い方を間違えれば身体に悪影響が出ます。アビガンはモルヌピラビル(新型コロナ用の飲み薬)と似たメカニズムで効果を発揮するので効いても不思議ではないのですが、新型コロナウイルスには残念ながら効果が低いうえにアビガン自体の副作用が強いので使われませんでした。
なんか「国産だから安心安全」なんて思っている人がいるようですが、アビガンは出来損ないの遺伝子を大量に作って増殖の邪魔をするものなので人間の生殖機能にも大きな影響が出ますし、体内のプリン体の量がかなり増えるので痛風になりやすくなります(添付書:医薬品の説明書にそういう記述がある)。
イベルメクチンは私がお世話になった教授の師匠と同じ研究室で研究していた方が開発したものなので役に立てばうれしいということはありますが、そういうものではないので。
またイベルメクチンは実験室的には効果があるかもしれないという話もありましたが、あれは「ウイルスに熱湯をかけたら全滅した」的なものではないかと思います。熱湯をかけてもウイルスは不活化(死滅)しますが、熱湯を飲んでも注射してもウイルスが全滅しないことは誰でもわかると思います。それと似たようなものでしょう。
あとは個人的な意見なのですが、「新型コロナワクチン接種した人は10年後全員死んじゃう」なんて主張している人もいるようなのですが、仮に本当にそんなことが起きてしまっても、私は生き残った人たちのコミュニティの中では精神的に耐えられず生きていけないでしょう。
それと「知り合いの知り合いの知り合いが死にました」系の書き込みもよく見かけますが、それだけ離れれば何でもありだと思うのです。私にとっては「知り合いの知り合いがサッカーW杯出場」も「知り合いの知り合いがノーベル賞受賞」も「知り合いの知り合いの知り合いが大統領」も事実なので。
アマハラ語
エチオピアには80の言語があり、そこに200ぐらい方言があります。公用語はアマハラ語といいます。
文字はエチオピア独特の文字で、日本のひらがな、カタカナと同じに、母音と子音をいっしょにしてできた文字なんです。ひらがなカタカナには5つ母音がありますがアマハラ語はプラス2つの7個の母音があります。
「ア」は「ä(口をあまり開けない)」と「a(口を大きく開ける)」とあります。「ウ」は「u(口をとがらせる)」と「ǝ(口を少しだけ開ける)」。それで「ä」「u」「İ」「a」「e」「ə」「o」となります。あとは子音は33なんです(注1)。
数字も独自の数字。1から10まで、20,30,40から100まで、一つの文字(注2)。漢字でも「十」は一つじゃないですか。エチオピアも一つなんです。21だと「20」と「1」を組み合わせて2つ文字になります(注3)。
他のアフリカの言葉は、ローマ字、あるいは北アフリカだったらアラビアの文字を使ってます。フランス植民地、イタリア植民地とイギリス植民地。またベルギーの植民地。植民地になってるのでみんなローマ字なんです。
一番私びっくりしたのは、文章作るとき、日本語とエチオピアのアマハラ語は同じなんです。
たとえば英語だったら、主語、動詞、目的語。でもアマハラ語は日本語と同じ、主語、目的語、動詞の形なんです。だから1万キロ離れている国なんですけど、どうして同じ形なってるの? すごい私びっくりしてます。
イェコロのテマリ
エチオピアの教育は、もともと教会からなんですよ。教会で神様について指導し、いろいろ書くので、そこから教育が始まっているんです。
昔、「イェコロのテマリ」という生徒がありました。
「コロ」というのは、大麦を炒めて食べる美味しい穀食です。それを食べながら勉強している「テマリ」(学生)という意味です。
昔、ほとんどの人は農家ですから、子供たちは親の仕事を手伝う。家畜とかを世話する番として、農家では子供たちが必要なんです。だからなかなか学校へ行けない。
それでちょっと頭早い子供たちは、親から逃げていくんですよ。5歳、6歳、7歳ぐらい。逃げて、違うところの修道院行って、名前変更して、そこに入るんです。親探してもわからないところに行って、犬小屋みたいなわら小屋作って、そこに住むんです。それでまわり、1軒ずつ物乞いして暮らす、ということです。朝学校が始まる前に行って、食べ物ください、とか言って、もらって、勉強する。遊ばない。夜もずっと勉強する。
それは宗教のことなんですけど、スポーツとか遊びはなく、毎日勉強する。暗記するだけなんです。夜もずっと勉強して暗記する。それで何年か勉強して、証明書もらって、どっかの教会行って、務める。とそういうことなんです。
「コロ」食べて、勉強してる「テマリ」、学生、生徒。ということなんです。
その教会の勉強はとても深いので、大体全部終わらした場合40年間ぐらいかかる。分野として4項目あって、大体修道院は一つしか教えないので、ちゃんと勉強してる偉い、有名な先生探して、そこに行って勉強する。それ終わったらまた別の先生、そうやってまわって、大体40年ぐらいかかるということです。まあそれまでいかない人もいるし、そこまでいってる人たちもいる。そのとき自分も先生としてそれからできる。
義務教育がない
現代の教育は場所によって違うんですけど、基本的に小学生は日本と同じ、1年から6年生。中学生は1年と2年。高校は1年から4年生です。
あと大学は、私もここ出身なんですが、アディスアベバ国立大学がエチオピアの初めての大学で、サイエンスキャンパス、ソーシャルサイエンスキャンパス、マネージメントキャンパス、テクノロジーキャンパス、メディカルキャンパス、…いろんな分野があります。すごく大きな大学なんです。
町には私立学校が増えてきているけど、エチオピアの学校はほとんど公立です。私も大学までお金1円も払ってない。
基本の教育は全部で12年ですが、義務教育がないので、まだ学校行ってない子供たちもいます。何故なら農業で親が働かせるために。だから我々は大使館とかエチオピアの政府に、「義務にしてください」と言っている。すごい遅いよエチオピア。なんで今まで義務にしなかったのか。教育は一番大切。日本も明治時代の時義務教育にしたから、それで変わったと思います。
サウジアラビアとか中東のいろいろの国たち、アフリカのコンゴという国、ものすごい資源あるんですけど、変わってないんですよあんまり。日本資源ないんですけどなんでこう変わったか。それは、教育なんです。だから今エチオピアの政府に、義務付けないと国が変わらないということ、我々は強くアドバイスしたい。
日本のサービス
日本とエチオピアの違いで一番すごいと思ったのは日本のサービス。日本のサービス、どこの国にもない、すごいよ。役所行ったら。病院行ったら。お店行ったら。どこでも行ったら。サービス、素晴らしいです。エチオピアは特に一般の人のとこ行ったらもちろん大事にするんですけど(注4)、お店行ったら、働いている人たち、日本みたいに「いらっしゃいませー」ってやらない。役所行ったら、自分たち偉いと思って「何してるのお前!」とか。(笑)
日本はすごい。自分の国の人だけじゃなくても、私外国人としても区役所行くとすぐ「なにか手伝いましょうか」と言って来てもらえる。それすごいびっくりした。
日本でも大使館ではいやな思いをしたことがある。パスポート更新するために行ったとき、「何で電話しないで来たの?」と。それで「何仕事してるのあなたたち? 事務所はいつもオープンじゃないですか、何でそういうこと言ってるの?」って、私ももうケンカして。
それから6か月待ってて、全然更新しなかったんですよ。新しいパスポート来なかったんです。何回電話しても「ちょっと待って」と、6か月待って。それで電話で「ちょっと質問ある」って言ったんです。昔区役所からもらえる「エイリアンカード」というのがありました。それを更新するために区役所行くと、大体長くても20分30分で全部終わらして帰るんですけど、私の国の政府は、パスポート更新するために6か月で足りない。だから「日本で30分くらいかからないことを、何で6か月で足りないの? 1人のことが6か月で足りないとすると、1億人のエチオピア人のことはどうやって対応してるんですか? 教えてください」って質問したんです。
日本のエチオピア大使館から、それから3週間で電話来て、「今できてるよ」って。大体7か月かかってたのが。(笑)
それはサービスの問題なんです。日本はみんな、事務所で働いてる人たち、政府でも会社でも、責任もって自分で最後までやってるじゃないですか。エチオピアはその目上の人、またその上の目上の人、そういうチェーン、ハードル作って、それからまた戻ってくるまで待ってて、すごい時間かかる。そのマネジメントシステム、全然だめです。
日本での難民の問題
日本での難民の問題は、働いている人たちのシステムの問題とは思ってないです。働いてる人たちのサービスは同じ。問題は決定力ある人たち。特に政治家の人たち。その人たちの政治的な意思がないから、と思います。ポリティカル・ウィルという、それがないと、たぶん変わらない。世界中が使っている基準から、日本は特別のハードルを作ってるんです。
7,8年ぐらい前なんですけど、5,6年も日本で難民申請しても受け入れてくれないので、メキシコ経由でアメリカに行ったんですよ。10人ぐらいなんですけどみんな受け入れてもらえた。
アメリカは受け入れたのに、なんでできない。他の人も、こっちでだめで、カナダが受けたり、オーストラリアが受け入れた人たちもいる。難民条約(注5)というのがありまして、日本もその基準を使ったら、たぶん10人じゃなくても5人ぐらい受け入れるべきなんですけど。難民条約基準以外の別のハードルができてるんだと思います。そうじゃないとこうはならない。去年ドイツは100万人受け入れたんですけど(注6)、日本は50人にも満たない(注7)。
でも一般の日本人の人は、難民の問題よくわかってる。我々難民の人たちのことやるとき、よく手伝いたい気持ちあるんだけど、サポートしたいので、と言われます。
でも政治的な意思がないので、解決するのは難しいです。
注
| ä | u | İ | a | e | ǝ | o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | ሀ | ሁ | ሂ | ሃ | ሄ | ህ | ሆ |
| L | ለ | ሉ | ሊ | ላ | ሌ | ል | ሎ |
| H | ሐ | ሑ | ሒ | ሓ | ሔ | ሕ | ሖ |
| M | መ | ሙ | ሚ | ማ | ሜ | ም | ሞ |
| S | ሠ | ሡ | ሢ | ሣ | ሤ | ሥ | ሦ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 100 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ፩ | ፪ | ፫ | ፬ | ፭ | ፮ | ፯ | ፰ | ፱ | ፲ | ፳ | ፴ | ፻ | ፼ |
隣りに住む高齢の父が先日、茶飲み話の終わりにこんなことを言った。
「なにか力になれること、助けられることがあったら、何でも言ってくれ」
父は認知症を患い、「できる」ことが毎日少しずつ減っていることを自覚している。
「自分で何もできなくなったら、生きている意味がない」。こんなことも、最近よく言う。
そんな父にとても切実な感じでこう言われ、なんだかとても申し訳ない気持ちでいっぱいになった。
父が私を助けられることはまだいくつもあり、今でもときどき全力を傾けて私のためにいろいろなことをしてくれる。
でも私はそれを大抵の場合、「余計なお世話」と感じてしまう。
なので何かをしてくれようとしても、「自分でできるから大丈夫」と言ってかわすことも多く、「もう年なんだから、こっちが助ける番なんだから」とかも言う。
でも父は本当に切実に、「自分が役に立つこと」を欲していた。
「できなくなること」「役に立てないこと」は、父にとって「生きている意味がなくなる」ことだから。
生きていることへの意味づけのため、自分自身が生きるために、父は私を助けたかったのだ。
干渉する親と逃げる娘。親子関係の「あるある」かもしれない。
父は「でき」、わたしは「できない」。
「できない」私を見ていられなく、教え、助け、子どもの時から父はさまざまな場面で力を貸してくれた。
その一方、助けられる側の私は、助けられるほど、ダメな自分を意識させられ、助けられるほど、父に支配されていくような感覚を持った。「命令を下す人」「決定権を持つ人」として、私の上に君臨する父。その呪縛が煩わしく、私は父が「でき」私が「できない」世界からそっと逃げだし、別の価値観に傾いていったから、結果、父は私にとって「本音を言えない人」となり、頼るべき人でもなくなってしまった。
そして私自身がおばあさんに近い年齢になろうというのに、今でもまだ父の「助力」を「権力」みたいに感じ、とっさに心が拒否反応を起こしてしまうのだ。
せっかく助けているのに。父はなんて損な役回りなんだろう。
自分の時間を削り、娘のためを思い、労を費やし、そのあげく感謝されるどころか逆に怖がられ、避けられてしまったのだから!
「助ける」ってなんなんだろう?
多様性社会には不可欠な、良心や愛情から生まれる優しい行為。
お金がなくて困っている人に、お金がある人が食べ物をあげる。目が見えなくて書いてある説明が読めない人に、目が見える人が読んであげる。
「共生」という言葉と縁の深いその行為は、同時に「できる」「できない」の上下関係を作ってしまう行為でもある。そんな気もする。
妻と子を持つ漫画家が、漫画で食べていけなくなり、石を多摩川の河原で売る「石屋」を始める。石は売れるわけもなく一家は窮乏し、主人公は妻から「虫けら」だの「役立たず」だのと日々罵られる。つげ義春氏の名作漫画『無能の人』。
今から30年ほども前だろうか、この漫画を読んで、私は主人公の無能ぶりに心底感動してしまった。稼ぐこと、働くこと、「できる」こと、ばかりが求められる社会の中でその全部が「できない」男のぶざまな生きざまは、むしろ「かっこいい」ものに思えた。
そして、同様の意味で「かっこいい」夫を持っていることを誇りに感じた。
家事も碌にせず、不器用で世間的には役に立たない夫との貧乏暮らしに、私は当時満足していた。
弱く、みじめで、みっともないこと、役に立たなくて、社会構造の中で下位にいること。
それは果たして「悪い」ことなのだろうか?
漫画で妻は、主人公をなじりながらも、実は理解し、頼っているようにも私には思える。
たとえばこんなシーンがある。
無能の人が、石屋の構想を妻に語る。無能の人は正座で、妻の足をもんでいる。妻はうつぶせの姿勢で、タバコを吸いながら、「ふん あんたの石がいつ売れるのよ」などと馬鹿にして聞く耳を持たない。そして「この団地の三千所帯に配って回ったら足が棒になるのよ」と自分の働きをアピールしたあと、「もっとしっかりもんでよ」と、夫に命じる。(※1)
また、こんなシーンもある。
石拾いを兼ねた貧乏旅行のぼろ宿で妻がふと言う。
「これから先 私たちどうなるのかしら」
「なんだか 世の中から孤立して この広い宇宙に三人だけみたい」(※2)
自分は「より働いている」。当時は本当に意識していなかったけれど、私の満足感は、その考えと関係していたような気がする。私の方が稼ぐし、私の方が家事をする。お金にはならないけど価値の高いことを知っている夫の音楽活動を、私が支える。働きのない夫を「許す」。
結婚前父に助けられ、それを嫌がっていた私が、「助ける」側の人になった満足感。安心感。そしてそのために自分の方が少し「上」にいるような優越感。その感じが、心地よかったのではなかったかなと、今思う。
あたかも無能の人の漫画のように、アルバイトから帰ってきて「あー仕事が大変だった、疲れた」と愚痴る。(夫が有能な会社員だったら言えない)
そして誰にも理解されない私たちだけの世界に私たちは生きている、と傲慢にも思う。
許し、感謝され、頼られ、家庭生活を支配する。
当時「愛」だと思っていた感情の片隅に、そういう欲があったのだなあと思うのだ。
その欲のために、夫が「無能」であることは、非常に望ましかった。
2年前聴講した「相模原事件と、向き合う。」という東大内の自主ゼミ(※3)で、講師の熊谷晋一郎先生がこんな内容のことをおっしゃった。
価値の根拠はまず必要性の方にあり、生産性は二次的である。生産性に価値が宿るのは条件付きだが、必要性には無条件に価値が宿る。そして全ての人が、生きていく上で様々な必要性を持っているから、全ての人に無条件に価値が宿ると、自分は思う。
こうおっしゃって、生産性がない=その人に価値がない、とする優生思想を否定された。
価値はすべての人に無条件に宿る。
なんてすてきな言葉なんだろう、と思った。
そして今改めて考えると、私は、稼ぎ、家事もやり、夫より生産性があるから、夫より価値があり、夫の上にあると、だから夫に足をもませてもよいのだと、優生思想に基づき思ってしまった。
でも本当はこのとき夫は、おそらく稼ぐことも、家事も、必要と思っていなかったのだ。
『無能の人』の主人公と同じように。
石を売る主人公に、古本屋が突っ込みを入れる場面がある。
「売れるわけがないのを承知の上でしょう」
そう言われ、主人公はムッとして「ひどいことを言うね 結果はどうあれオレは一生懸命やっている 努力しているんだ」と反論する。が、古本屋は
「ふりをしているだけでしょう」
と図星を突く。(※4)「稼ぐ」ことの無意味さを知り、「稼ぐ」必要性を感じない彼の代わりにいくら妻が稼いでも、夫を助けたことにはならないのだ。
だから同様に、私が稼ぎ、家事をすることにも価値はなかった(少なくとも夫にとっては)。
何も助けていなかった。自己満足だった。それで感謝されないのが不満だったけど、感謝されることを別段私はしていなかったのだ。
その「ずれ」が「破局」の主因だったのかもな、と、今にして思う。
(そしてこれも案外、「夫婦あるある」「離婚あるある」だな、とも思う。)
冒頭の父の言葉を振り返る。
「なにか力になれること、助けられることがあったら、何でも言ってくれ」
「力になりたい」「助けたい」という切実な思いは、今の父にとって「必要性」そのものではないかと感じる。
だから、この思いにはきっと価値がある。
このエッセイページ「にじいろでGO!」のインタビューページに登場する原理子さんの、澄んだまっすぐな目を思い出す。知的障害を持ち支援を受けながら暮らす原さんが、目の不自由な方に勇気を出して話しかけ、助けた。そして「ありがとう」と言われ、「嬉しかった」と話している。
なんの打算もない純粋な、心からの「助けたい」欲望。「助けなければ」という本能的な責任感、優しさ。こんな純粋な「助け」を、いつか私もできる人間になりたいと思う。
まずは父に「助けられ」よう。
2016年7月26日に相模原の津久井やまゆり園で19人の知的障害者が殺害される事件が起きました。この事件について、同じ知的障害をもつ仲間として、自分たちの声で語り合おうと11月23日に集会を行
障害をもつ当事者が自分たちの声でこれまでの経験や事件のことについて語り合い、自分たちの力でこれからの暮らしを作り上げていくことを「にじいろでGO!」は支援者とともに目指しています。
「にじいろでGO!」の活動についてメンバーが語っています。
名前か写真をクリックするとインタビュー動画が表示されます。
聞き手:奈良崎真弓さん(にじいろでGO!代表)
制作・出演
にじいろでGO!の仲間
のっぺらぼう
私の隣人には顔がない。のっぺらぼうで、壁越しにシャワーの音を響かせている。
私の世界を構成するもの、それは私の感覚が与えてくれるものそのものだ。散らかった部屋を照らす薄暗い電灯、指先を冷やすビール缶、路地に漂うサンマの香り、通り過ぎていく救急車のサイレン。知覚できないものは私の世界に存在していない。私は自分の認識能力という壁の内側に閉じ込められている。この閉じ込められた世界に自分以外の人間は存在しているのだろうか。
もちろん私は自分以外の人間と共に社会の中に生きている(と感じている)。玄関を出れば道行く人が見え、店に入れば店員の声がする。「日本社会」という言葉が私の辞書にある以上、確かにこの日本社会は存在して、その中で生きているに違いないのだ。「では、あなたが思い描く日本社会とは何ですか」と問われると答えに窮する。本来、そこには生まれたばかりの赤ん坊から、明日死ぬ人まで、一生会うこともない無数の人がいるだろう。しかし、認識できていないそんな人たちは私の世界に存在していない。それでも私が日本社会に生きている、というとき、私の頭の中の日本社会とは何なのだろうか。
私にとっての日本社会、それは自分が見聞きした人のイメージの総体だ。家族の顔や友人の顔だけでなく、今日すれ違った人々の顔、ニュースで見る人の顔、何らかの形で知覚した様々な人の顔を思い浮かべる。「日本社会ってこんなものだろう」というイメージがなんとかできあがる。
では、このイメージされた日本社会に、私の隣人はいるだろうか。私は隣室の住人の名前も顔も知らず、その事実が覆ることはない。私の隣人は彼・彼女がたてる物音以上には私の世界に存在しない。私が思い描く隣人にはやはり顔がない。
顔のない隣人は他にもいる。「あなたの思い描く日本社会とは何ですか」と問われたとき、車いすの人、寝たきりの人、LGBTの人、移民、そういったマイノリティと呼ばれる人を思い描いただろうか。いや、そもそも車いすの人を想像したとして、その言葉「車いすの人」で思い描いたのはどんな顔だろうか。日本社会とは何だろうか、という問いと同じように、そもそもマイノリティとは何なのか、それすらも結局私がいままで知覚したことのある誰かの顔の寄せ集めに過ぎない。でも、私が顔を知らない人は知らないまま、今日もどこかでのっぺらぼうのまま生きている(と私は知覚している)。
のっぺらぼうを消すには顔を見てくるしかない。しかし、日本中の全ての人に会うわけにもいかず、認識能力の限界によって私の世界からのっぺらぼうはいなくならないだろう。否、私の世界はのっぺらぼうだらけだ。それは怖いことだろうか。だったら、知らない顔を知っている誰かの顔で代用するのはどうだろう。頭の中の隣人に仮面を被せるのは簡単なことだ。どこかで見たことのある誰かの顔のイメージを貼り付けて納得すればいい。のっぺらぼうの代わりに知っている顔のコピーに囲まれて暮らす世界は居心地いいかもしれない。
しかし、仮面は仮面に過ぎない。仮面の下の素顔は空っぽのまま存在していない。仮面に満足した世界、それは虚構の世界だ。虚構に慣れてしまうと、いざ素顔を見る機会に出会っても、もう顔を見ようとしなくなるのではないか。それでは欺瞞の世界ではないか。だとしたら、のっぺらぼうに囲まれた世界にとどまることで、いつか隣人の素顔を知る日を待てばいいではないか。
残念ながら、仮面の欺瞞から逃れることは出来なそうだ。そもそも、私は「のっぺらぼう」という仮面をもう隣人に被せている。灰色で目も鼻も口もない。これはれっきとした仮面だ。純粋無垢なまま、ただ真実の素顔を知覚できる日を待つことなどこの世界では許されていない。そもそも、知っていると思っている人の顔ですら、再現性がないことに気付くだろう。友人のまゆげの形、親のほくろの数、上司の禿げ頭の生え際、どれも細部は知覚されていない。私がそもそも知っていると思っている顔ですら、すべて仮面に過ぎない。少しばかり、のっぺらぼうより精巧な仮面だ。
どうやら、私の世界にいる人間は皆仮面をつけているらしい。仮面の造り手は私だ。「のっぺらぼう」が気に入らないなら他の仮面を与えることができる。そして、自分が居心地の良い仮面を積極的に散りばめ、知らないものを知った気になる。知覚に支えられた虚構と欺瞞の世界。この自分だけの世界で、望む仮面を作り、他人を理解した気になる。細部まで作りたい仮面があるならこだわり、どうでもいいものは作らない。どうせ、知った気分という感覚以外に、何かを知り得ることなどないのだから。仮面の種類の豊富さが、私の世界の多様性だ。
正直に言おう、私は隣人の顔に興味がない。いざ玄関前ですれ違ったとしても、きっと目を合わせずにやり過ごし、顔など見ない。所詮は知覚能力の限界によって限られた世界、隣人の顔が「のっぺらぼう」のままでも構わない。
白地図に線を
地元から東京に出てきた頃、東京出身者と話していてとまどうことが多かった。彼らの日本地図が同心円状だったのだ。「東京」が真ん中、その外側をぐるっと取り囲む「地方」。東京以外はみな「地方」という言葉でくくられ、その中にある差異は無視される。いや、想像がつかないのだ。知っている場所と知らない場所、東京とその他。要は「その他」の意味としての「地方」から私はやってきたとみられた。
地元は広島県だ。広島県は隣の岡山県や山口県とも異なるし、海を挟んだ愛媛県とも異なる。いや、訂正しよう、広島は広島でも私の出身は備後地方だ。私は自分を広島出身と名乗ることはない。広島と言えば広島市を含む安芸を指すことが多い。安芸は備後とは異なる。旧国名も違えば、江戸時代の藩も異なる。言葉だって違う。備後弁も広島弁と言われるが、安芸と備後それぞれの出身者が出会えば、会話をした途端に違いがわかるほどには異なる。
地元に帰れば、備後地方であることなど名乗らない。誰もが同じ地域の出身だから当然だ。問題になるのはどの小学校に通っていたか、いや、それどころか、同じ学区内のどのエリアに住んでいたか、が問題になる。私が住んでいたのは八幡神社が祀られた小高い丘の周辺に広がる住宅街で、「宮の端(みやのはな)」と呼ばれていた。町名とは全く異なるにも関わらず、小学校の秋の運動会では皆地区名をゼッケンにつけて参加していた。「宮の端(みやのはな)」は他地区より人口が多く、地区対抗では有利で毎年優勝候補だった。それが誇らしかった。
知らないものはおおざっぱにまとめてしまう。そして知っているものは細かく区切りがちだ。私の日本地図は、広島の備後地方だけ細かく線が引かれているが、他の地域は同じ広島県でも白い部分が多い。隣の岡山県もすこしだけわかるが細かい線は引けない。同心円状ではないけれど、私の日本地図もずいぶん雑なものだ。
ただ、一部だけでも細かい地図を持っていると、違う地域を訪れたときに、類推することはできる。数年前、東日本大震災の復興支援で福島の各地を訪れる機会があった。行ってみると浜通り、中通り、会津の3つの地域はまるで独立しているかのようだった。歴史も異なれば江戸時代の藩も違う。風土も農産物も異なる。もともと西日本の端に暮らしていたころには、所在地さえ曖昧だったが、今は福島県というと必ず三つの地域に分けて考えるようになった。震災以降特に1つの県にまとめられて語られがちだが、浜通り、中通り、会津には私が「宮の端」とそれ以外の地域を分けて考えていた以上の大きな違いあると今ならわかる。もちろん、もっと細かく分けられるはずだが、そこまで深く知らないことはご容赦願いたい。ただ、さらに細かい線が引けることは想像に難くない。
もちろんこれは類推に過ぎない。それでも、まだ訪れたことのない県、地域、国にもひとくくりにできない何かがあり、そこに暮らしている人にしかわからない細かい境界線がいくつも引かれているに違いないと思う。日本の中の広島の中の備後の中の「宮の端」のように。
そんな類推に何の意味があるのかと思うかもしれない。東京に出てきたとき、「その他」の扱いをされて私はたじろいだ。自分が大切にしてきた細かい線が全てないがしろにされ、動揺した。だからこそ、私はせめてもの類推をし、他の「地方」出身者の線を大事にしたいと思っている。そして、新しい場所、新しい地域に行くときには、きっとそこに私が知らない細かい線が無数にひかれていることを想像する。うっかり大事にされている線を無視しないよう、目を凝らす。とてもすべての線を見ることはできないが、かといって白紙のままであるよりは、と思うのだ。
もちろん、細かい線を引き続ければいいというものでもない。出身地を聞かれるたびに実家の住所を番地まで答えていても仕方がない。出身を通じて伝えたいのは、自分が他人と共有した文化的体験だ。たまたま同じ地域に住んでいただけにも関わらず、同じ方言を話し、同じ季節の移ろいをみて、その土地の歴史を共に受け継いだこと、それこそが文化の共有体験だ。広島、や備後と口にするのは、共有体験をしていない人に自分の文化を伝えるための符号に過ぎない。アイデンティティの一部、自分を構成する社会的要素を伝える1つの方法が出身地なのだ。
だからこそ、自分がどこに属しているのか答えることは難しいのかもしれない。相手によって「広島」や「備後」と答えたり「宮の端」と答えたりする必要があるのはなぜか。これは今自分が相手に伝えたいアイデンティティはなんであるのか選ばなければならないからだ。出身地を語ることで、自分はこんな社会的背景を共有している、と瞬時に伝えてしまえるからこそ、どれだけ細かい地図を相手にみせるのかが重要になる。むしろ、ある程度漠然とした白地図を使うことが便利な時もあるのだ。
そうそう、今なら東京の中にも細かい線がたくさんひかれているとわかる。私は私で東京のことをわかっていなかった。環八の内側、環七の内側、山の手通りの内側がそれぞれ異なること、下町の文化と山の手の文化の違い。私の地図にも、やっと東京の細かい線が引かれ始めている。
Northwestern University 経済学博士課程に所属する学生。ゲーム理論と経済史を勉強中。
第3回のエッセイの最後で、女性労働の「デバリュエーション(devaluation)」理論にふれた。これは、男女間の賃金格差が生じる原因を探る中で出てきた考え方で、女性労働の価値が引き下げられる要因を次のように分析する。公私二元論のもと、市場で支配的な位置にいるのはこれまでも、そして現在においても男性(実際には、特定の男性集団)で、彼らは自身の優位性を維持する方向で市場のルールを設定したり書き換えたりできる特権をもつ。このため、より多くの女性が市場活動に参加するようになったとはいえ、市場のルールは女性に対して不利に働きやすい。また、他者のケアを含む家事労働に低い社会的価値しか与えられてこなかったことも相まって、女性が行う労働は、とりわけそれが家事労働に近い要素を持っていればいるほど、市場において低く価値づけられてしまう(*1)。
したがって、女性労働の価値を適正なものにしていくためには、市場のルールを多様な参加者の存在をふまえた、より公平なものへと変更するとともに、女性が携わってきた労働(家事労働を含む)の価値が社会において適切に認識される必要がある。このように整理すると、ダラ・コスタらによって主張された「家事労働に賃金を!」運動の狙いは、後者に狙いを定めることで、女性労働の価値を、家庭内と市場の両方で高めていこうとしたものだったといえる。第3回のエッセイで記したように、ダラ・コスタの議論は、当時のマルクス主義フェミニストから批判された。しかし、両者の目的はいずれも、家庭内で働こうが市場で働こうが、両方の場で働こうが、資本主義社会のもと、女性が不利な位置に置かれやすくなっている構造を変えていこうという点にあったのだ。
さて、ここまでダラ・コスタらを擁護する形で議論を進めてきた。だが、ディスアビリティ(障害)の視点を加えると、彼女たちの議論の前提に憂慮すべき危険があることが見えてくる。このエッセイの後半では、主に2点を指摘したい。
ひとつは、労働力を再生産しない家事労働をどう位置づけるのかという点に関わる。ダラ・コスタとジェイムスの議論は、女性の家事労働が、現在と将来の労働力を生み出すという点で、資本主義にとって不可欠なものだという前提に立っていた(第2回のエッセイを参照)。しかし、家事労働の中でもとりわけケアに関わる労働には、高齢者や病者の介護、障害者の介助など、資本主義が必要とする労働者になることが期待されていない人たちへのケアも含まれる。こうした人たちに対して行うケアは、先の議論のロジックに沿って考えると、労働力を再生産するものではないので「労働」ではなく、したがって対価を支払わなくてもよい、ということになってしまう。このように、ダラ・コスタとジェイムスのロジックのみに依拠して女性労働の価値を高めていこうとすると、資本主義にとってどの程度有用性があるのかを軸に、女性労働の内部に新たな階層秩序が作り出されかねない。さらに危険なことに、そうした階層秩序は、能力主義や優生思想と結びつくことで、特定の人びとの生存を著しく困難にしたり、彼ら/彼女らの存在を否定する傾向に手を貸してしまうことがある。
ダラ・コスタらの議論に対するもうひとつの違和感は、家事労働(とりわけケア労働)の負担をめぐる議論の仕方に関わる。「家事労働に賃金を!」運動は、女性たちが家庭内での無償労働と市場での低賃金労働によって大きな負担を抱えていること、それにより資本家が利益を得る一方で、女性たちが不利な位置に置かれていることを問題にした。この問題提起の重要性が過小評価されるべきではない。だが、家事労働やケア労働の負担をめぐる議論では、労働を担う側の負担にばかり焦点があてられ、それら労働を直接受けとる側が経験している負担が不可視化されがちだ。その結果、負担をめぐる議論は、他者によるケアなしでは生活・生存の維持が著しく困難な人たちの存在を欠いたままなされる傾向にある。
ケアする側である女性がそうであるのと同様、ケアされる側も既存の社会構造や社会規範によって不安定かつ脆弱な位置に置かれ、さまざまな負担を抱え、我慢させられている。しかも、ケアされる側は、ケアする側との関係を容易に退出できないという点で、より不利な位置に置かれやすい。この点をふまえると、ケア労働を担う人たちの負担をどう減らすかという課題は、その労働を通して提供されるケアの量や質をどう担保するかという課題とあわせて議論されなければならない。後者の視点を欠いた議論は、誰かの生存の不安定性・脆弱性を加速させる可能性があるのだ。その暴力性に意識を向けること。それは、社会保障制度改革のもと緊縮削減政策が進められている昨今において(*2)、これまで以上に重要なものになってきている。
発達障害なんて他人事と思っていた。
自分とは全く関係のないものだとずっと思っていた。
いまだにおかしな感覚に囚われる。
自分は発達障害なのだろうか。
私が発達障害であろうとなかろうと
私は変わらない同じ人間なのに。
発達障害の診断を受ける前も受けた後も
私自身は変わらない。
振り返れば、自分の様々な困難は発達障害の特徴によるものが多い。
幼い頃から長年ずっと苦しんで来たことが、感覚過敏によるものであると、最近になってやっと気づいたり。できることができなかったりすることも発達障害のせいだったりする。自分の抱える様々な困難や特徴が発達障害から来ているものだと、今更解ってもどうすれば良いのか。解りたい知りたいとは思うが、解ったところで困難が解決する訳ではない。
障害者である自分を知ったり周りに知ってもらうことで、何かメリットがあるのだろうか。本当にわからない。
自分にとってはデメリットしかない。
コロナウィルスに対しての
緊急事態宣言、自粛要請で困難になった就労活動について綴ろうと思う。
正社員で務めていた会社で仕事中、膝を痛め休職し転職を考え、昨年から就職活動をしていた。
やっと就職活動に本格的にうごきはじめられた。矢先。
履歴書や職務経歴書を数カ所送って、やっと現実的に動き始めた矢先のコロナウィルスによる緊急事態宣言。
就職活動がかなり困難になってしまった。
就労支援で相談に乗ってもらったり支援頂いていた機関は施設自体が利用禁止。
ことごとく直接面談中止になる。
電話相談電話対応に変わる。
東京都の自粛要請で
会社も自粛が多いが公共機関も、できる限り接触を避けるようにと、ほとんどの就労支援などの施設が電話相談に切り替わって、施設の利用は不可。職員は交代で出勤。
働いているが施設自体閉じてしまった。
対面での面談も受けられず
電話相談の予約も受けてもらえなかったり。
施設により対応はまちまちだが、
出来れば次の予約を入れたくない。来ないでくれと言われる。
しかし、相談が必要なら断りはしない。みたいな対応が多い。
電話しても担当職員も他の現場に駆り出され、いなかったり。交代制の勤務になって、担当者がいなかったりする。
国の緊急事態宣言による自粛体制がさらに5月末まで延長。いつコロナが終息するのか。先が見えない。 自粛がいつまで続くかわからない。
4月1日二次面接予定だった会社は二次面接先延ばしになり、障害者雇用の合同面接会は中止になり、トライアル雇用の受け入れもコロナウィルスの終息を待ってから受け付けると言われ、ハローワークは開いているものの
求人は減っているし、応募しても返信がない会社も多く。
ハローワークは開いてはいるもののハローワークの電話はつながるまで1時間待ち。繋がらない・・。
求人自体も減っている。
求人取り下げたり、求人の更新をしない会社が増えていると。ハローワーク窓口からも言われた。
更に、この状況で今人が欲しいという企業・・。いま、求人を出している企業が、
ブラックな企業である可能性が高そうで気が重い。
身動き取れなくなって。途方にくれる、
でも、その中でどうにかやってゆかなくてはならない。
これが、現在。5月
3月末
就活中の生活費としてつなぎでやっていた結婚式場の皿洗いのバイトが無くなる。
4月の仕事がゼロ
つなぎでやっていた結婚式場の皿洗いは1月2月3月とだんだん仕事がなくなり、とうとう4月にゼロになる。今月だけゼロではなく、だんだん減って、と言うのが辛い。5月もゼロだし6月7月もないだろう・・。
結婚式も宴会もこの状況では当分ないだろう。
就活どころではなく、まず明日の食糧、今月の電話代のために、何か仕事をさがさねば、
電話が切れたら、就職活動がさらに困難になる。とりあえず収入がなければ生活できないので、スーパーのバイトの面接を受ける。
返事が来てとりあえず短い時間だが雇ってもらえる。
スーパーのバイトは週20時間からのスタートだから、多くて月8万ぐらいだが、ゼロよりまし。4月はもう半ばなので
4月の収入は多くて2万ぐらいかもしれない。いや・・2万もらえないかも。もしかしたら、もっと少ないかも。
2万でどうやって。暮らすか・・。
電話代と親の会社で働いた際にきちんとした給与が支払われなかったために負った借金の返金を返したらお金が残らない。
社会福祉協議会に電話すると
コロナウイルス対策の
上限20万円の貸付金の話をされる。
最悪、本気でどうしようもなくなったら、
お金を借りるしかないが、仕事が決まってるわけではないのに、借金を重ねるのは、
恐怖だ
給付金30万の話は無くなったが、
自分は、みんながそんな奴はいないと
騒いでいた、給付の対象であったのではないかと。ちょっとがっかりする。
住民税の非課税対象にまで落ちた人間、少ないだろうが、現実に対象者はいて、厳しい訳で、
一律10万円に反対なわけではないが、
そこで、救われなかった人たちに対しての
救済手段は、考えて欲しい。
お金が本当にないので、昨年、秋ぐらいからフードバンクも利用しているが、フードバンクに登録できるまでが、もう本当に本当に大変で大変で、何度も何度も区の困窮支援窓口に行くが登録させてくれない。
現状と困難ぐあいは説明したが、
フードバンクの利用を希望すると
その場で少し食べ物はくれるが、フードバンクの登録はさせてくれないし、フードバンクの説明もあまりない。
登録は財布の中身が1000円以下になったらと言われ、何度も何度も、何回も何回も 通って、そのたびに、財布の中身の金額を職員の前で数えてそれを行くたびに、何度もやって
フードバンクの登録を渋られ、断られ
本当に精神的にも肉体的にも追い込まれた状態まで追い詰められてから、精神的疲労から眠ることもできなくなり、とにかく少しでも休まなくては、きちんとご飯を食べて、きちんと睡眠をとって、当たり前のことだけれど、それもままならないくらいに追い詰められる。もう限界となって体調をさらに崩したのが、昨年11月21日
要は、仕事などできないレベルまで追い込まれないと、登録させてくれない。
現実それ、ですよね。区困窮支援窓口の対応は
削れるところは、食費、となるので、食費を削ったがために、体調や精神状態を崩す。
その状態でバイトにゆき、先が見えない就職活動と職業訓練校の受験
もともと、状態がいいわけではない。
収入が安定していれば、
食事と睡眠時間の確保を優先するが・・。
何故、ここまでならないと、登録させてもらえないのか・・・。
電話口で、どれくらい危機的な状況なのか、訴える。とにかく、食糧の援助をもらえれば、生きては行ける。最低限のところまで、バイトを減らすこともできるから、ここでさらに肉体的にも精神的にも働けないレベルまで追い込まれては、きつい。フードバンクの登録をさせてくれと、電話口で必死に捲し立てて、
その状況でも、生活福祉課困窮支援窓口職員は、
財布のなかのお金を数えろと言う。
もうこれまでに、何度も数えているし、
現状は以前から話している。
財布の中お金が1000円以下、それがフードバンク登録のための基準なのか。
これは、全国的にそうなのか?X区だけか?本気で切羽詰まって、ギリギリの状態で
やっと、
電車移動の交通費がない、状態で
やっと登録できた、
しかし、登録したら
生活が充分できるだけの食料がもらえるわけではない。だったら、何故、もう少し早い時点から、登録させてくれないのか・・。
このシステムは何なのだ??と、思う。
少しでも食料がもらえるのは本当にありがたいが、
生活するのに十分な食料がもらえるのでないのなら、なぜもっと早い時点で、登録させてくれないのか・・・。
こうやって、かなり前から生活が厳しくなったところから困窮支援窓口に相談していても、本気で経済的にギリギリに追い込まれるまで、フードバンクの登録はさせてもらえなかった。せめて、もっと早い段階で、登録させてもらえれば、
ここまで追い詰められない。ここまで、追い詰められなかったのに。
精神的にも肉体的にも追い詰められ、
障害者就労支援センターに2箇所、都と区とに登録し、東京しごとセンター、ハローワークのキャリアカウンセリング、生活福祉課の就労支援、区の就労支援センター
あちこち就職の相談をしているのに
なにも進まず、先も見えず
☆☆☆
今まで一般の就労しかしたことがなく。
障害者就労をしたことがなく、一般の普通の仕事普通の会社で問題なく働いてきた。
クローズで問題なく働いてきている。
今後のためにも、障害者就労も視野に入れて
オープンとクローズ両方で探そうと思った。
☆☆☆
障害者就労も視野に入れて、オープンとクローズ両方で仕事を探そうと、散々動いた末
手間も時間も 労力もお金もかけた末、
結局、一般就労(障害者就労ではないという意味)をするかもしれない。現在。
そしてその過程の困難。
グレーゾーンといえばグレーゾーンなのか・・?
自分は所謂グレーゾーンなのか
それとも障害が重いのか、
それって、何で決まるのかな。
困難度合い??医者の診断書??
この、偏りはどこから来るのです??
あと、そもこれ、障害じゃないでしょ。
特徴なので、脳の機能の偏りだし・・。
障害になってるのは、この社会のせいですよね。私と同じタイプの人間が世の中の多数派であれば、いま、健常者とされている人間達がむしろ障害者ですよ。
発達障害も
自閉スペクトラム症も障害ではあるけれど、
人口に対する割合そんなに低くもないのです。何故こんなに苦労しなければならないのか。
障害を隠し、一般就労を初めから目指していれば、こんな苦労をしなかったかも、ですし、経済的にここまで、追い込まれることはなかったかもしれない。
障害者就労支援が言うことは正しいのかもしれない。「一般就労でいいんじゃないですか?」
けれど、違和感を感じる。
障害者エリートでなくては、就労が難しい現実。
障害者就労が一般就労より困難。と言う部分。
発達障害支援法 とか、ありますが、
発達障害支援してもらえるのでしょうか。
どう支援してくれるの??あの法律なんなの??と思う。
世の中、発達障害について、差別ばかりで、マイナスばかりですよね。と。
支援受けていないとは言いませんが、
確かに、支援してもらえているのかもですが。どうなの??と、思う・・。
そんなに支援受けられてはいないぞと。
結局表面的な部分のみ
一部の人間が支援されれば、それで良し。
法律で社会が大きく変わっていく
発達障害にとって生きやすくなるわけではない・・。
世の中がそんなに、発達障害について
優しい世界には思えない。
理解もほとんどない。
偏見や差別は強くても理解は薄い。浅い。
障害者差別防止法とか
字面だけ並べて、当事者は苦しむしかない。
かえって、しんどくなる現実。
今、この世の中で、
発達障害だと、名乗らなくて済む人は
日本では特に名乗らない方が良いのではないかと思う。
発達障害だけでなく、精神障害についてもそうだ。
障害者を差別しない。理想や建前はいいよ。
勝手に語ってくれ。と思う。
福祉の表面的な理想論的な建前の話と、
現実。の対応。その差。
フラワーランドから来たお花の妖精
未来人のメッセージを伝える使者として
パフォーマンス活動を続けている。
うたっておどれる陶芸家
陶芸家 国立国際美術館 作品集蔵
インディーズアイドル
(キララ社発行インディーズアイドル名鑑の大鳥)
パフォーマンス活動
LUFF (Lausanne underground film and music festival) ローザンヌ国際アンダーグラウンドフェスティバル2016年日本代表アーティスト
音楽イベント主催
『大宇宙ロックフェスティバル』
『凶人解放治療』
『こたつライブ』
『音詩空間』
ゆるキャラデザイナー
南新宿商店会・南新宿町会公式キャラクター『ミナミー』をデザイン
イラスト・デザイン
東急デパート『福祉ものづくり展』ポスター製作
国会議事堂セブンイレブン障害者の販売スペースありがとうショップのPOP製作
関東ウェーブの会 アイコン製作
ペイディフェ pays des fees
ヤドクガエルコレクション Tシャツデザイン
他
私自身が「障害」について考え始めたのは、4年ほど前のことである。それまでにも漫然と考えることはあったが、自分と、自分の中にある障害(感音性難聴)という悶々としたモノとのかかわりについて、真剣に向き合い始めたのはその時からだった。
「障害」を考える際には、その対比として「健常」「ふつう」という概念が用いられる。最近では「障害」と「健常」ということばによって隔てられる二項対立の構図自体が見直されつつあるが、それでも尚、それらのことばを以てしてのみ語り得る言説が多く存在するし、このような議論においては現状欠かすことのできない概念である。以下では、それぞれのことばの扱いを考える上での、私なりの解釈を与えたいと思う。以下の議論は、障害に関する理論の定式化といった大袈裟なものでは決してなく、あくまで一つ一つの概念について読者の方々の思考を広げるヒントとして読んでいただければ幸いである。
「ふつう」とは
「ふつう」というのはつくづく便利なことばだなあと思う。普段そのことばを使う上でも、何をもって「ふつう」と言っているのか、常々意識している人は少ないだろう。それほどに使いやすく汎用性の高いことばではあるが、一方で「ふつう」に囚われ、振り回されるようなケースも多く存在する。「ふつうは〜なのに、あなたは〜(自分は〜)」といったフレーズのように、一般的に「ふつう」を基準にして、それと比較して優れているか、劣っているかを判断するケースは典型的なものだ。ここでは、そのような「ふつう」という基準の意味するところについて、私の専門である統計学の観点も少し交えながら考えてみる。
「ふつう」ということばの意味を定義するならば、自分の周りに存在するある一定数の人たちの平均±誤差といったところだろうか。これを統計学的にもう少し厳密に言うと、ある母集団の平均値や最頻値などの代表値±誤差、ということになる。ここでの母集団ということばに注目してほしい。統計学の世界では、大前提として性質を調べたい対象である母集団が存在し、その母集団の中から得られたデータをもとに分析を行う。当然、異なる母集団があれば性質の違いが数値として表れるし、そこから導かれる結論も異なってくる。統計学においては至極当たり前な考え方だが、このことを「ふつう」ということばに当てはめるとどうだろうか。
母集団が違えば、「ふつう」も異なる。例えば「大学生のふつう」と「幼稚園児のふつう」は異なるし、母集団が一人であれば「自分のふつう」「その人のふつう」ということになる。そして普段私たちが「ふつう」ということばを用いるとき、そこには無意識のうちに何らかの母集団が背後に想定されている。つまり、普遍的な「ふつう」というものは、理論上はともかく現実的には存在しないのである。ここで改めて先ほどのフレーズを思い出してほしい。「ふつうは〜なのに、あなたは〜(自分は〜)」というフレーズはすんなりと多くの人に受け容れられているが、「ふつう」の背景にある母集団は見事なまでに意識されていない。そしてたいていの場合、母集団はその場やその発言者の都合によって無意識に、また故意に選択されている。そのことが、この類のフレーズに対して居心地の悪さを感じる一つの要因であると考えている。このように不用意に「ふつう」ということばを用いて語ることは、統計学において母集団についての議論をすっ飛ばして平均値や中央値を議論するのと同義であり、それほどに愚かなことである。
「健常」と「障害」
同様に「健常」と「障害」についても私なりに解釈してみる。「健常」とはある指標について「ふつう」であるか、もしくは「ふつう」に到達可能な状態のことであり、「障害」とはある指標について「ふつう」との間に解消が極めて困難な、または不可能な障壁が存在する状態のことであると考える。ここには2つの論点がある。①指標の存在、そして②「ふつう」の裏側の母集団の問題である。
まず①の論点について、先ほど「ふつう」が母集団の代表値±誤差を意味しているという話をしたが、そこには同時に母集団の何の性質に着目しているか、代表値が何の代表値であるか、という指標が存在している。指標というのは、例えば学校のクラスの母集団の中で身体測定のデータをみるときの、身長や体重といったもののことだ。障害について考える上でも指標というものが存在するが、2つ注意点がある。1つは必ずしも数値で表される定量的なものではなく、定性的なものもあり得ること、そしてもう1つはその指標の軸上での評価は、とくに定性的な指標に関しては主観的にしかなされ得ないということである。例えば私の聴覚障害の評価は、聴力という指標の上で定量的にもなされるが、一方で聴力の数値に表れない「ことばの聞き取りやすさ」という指標も実は存在し、これに関しては私の聞き取りの感覚について、ことばを十分に聞き取れるという一般的な(私にはわからない、すなわち想像の)感覚との乖離を、私自身が主観的に評価している。指標の主観的評価に関しては、障害の程度評価などの客観性が要求される場合にはなかなか折り合いが難しく、現実にもその問題は多く見受けられる。
指標を明らかにすることにはメリットも存在する。それは、不用意に「障害者」と一括りにされる論調を回避できることだ。例えば肢体障害を持つ方の中には「移動のしやすさ」という指標に関して不利を被っている方もいらっしゃるが、聴覚障害の当事者である私は、「移動のしやすさ」という指標の上では「健常」である。逆もまた然りで、肢体障害の方は「聴力」「聞き取りやすさ」「コミュニケーションの理解度」などの指標の上では「健常」であったりする。このことは当たり前に見えるが意外と見落とされがちなところで、何か「障害」があるからといって決して「障害者」と一括りにして論じないという意識は大変重要である。
そして②の論点について、実はこの議論から本題に迫っていくのだが、第1回は一旦ここまでとし、次回以降詳しく考えていこうと思う。
東京大学大学院経済学研究科卒。聴覚障害当事者。在学中に「障害者のリアルに迫る」ゼミに携わる。
海外で困ることの一つがトイレだ。これは開発途上国だけでなく、先進国でも同じだ。背の高い人が多いことで有名なドイツ。その田舎町へ行ったときのこと。トイレに入ると、小便器が高い(あ、もちろん男性トイレのことである)。これは屈辱的だ。つま先立ちにならないと用が足せない(あるいは、ひょいと持ち上げる方法もある)。郷に入ったら郷に従えというが、背の高さはいかんともし難い。
社会の建物やきまりは(便器も)人のために造られてきた。しかし、すべての人に等しく配慮するように作られてきたわけではない。人はそれぞれ異なっているから、すべての人に便利な建物やきまりというものはなかなか存在しない。いきおい、なるべく「ふつうの人」に便利な建物やきまりを作ろう、ということになる。
ひとはみな「平均」から多かれ少なかれ、ずれている。このずれがそれほど大きくない場合には、何とか自分を建物やきまりに合わせていくことができるだろう。
しかし、このずれが大き過ぎると、もはや社会生活を営むことが困難になってしまう。何せ公衆トイレで用も足せないのだ。
日本人男性はどうして日本の公衆トイレで用が足せるのか。それは平均的な日本人男性に合わせてトイレが作られているからである。「ふつうの人」は社会で配慮されているけれども、それに気づかない。一方、「ふつう」からはずれている人への配慮は不十分なのだ。
ドイツのトイレで見回すと、一つだけ子供用の小便器があった。しかし、これを使うのも何だかだなあという感じだったことは記しておこう。
私は2000年の年末に馬から落ちて首を骨折しました。その時に中枢神経の脊髄が切れ、車椅子生活となりました。「切れたなら繋げはいいんでしょ?」と思いながら、早20年が経とうとしています。「世の中そんなに甘くない…。」と思いながらも「まあ、そのうち何とかなるかも?」と相変わらず甘い考えで生きています。
車椅子生活になったお陰か、健常者の頃には見えなかった物が良く見える様になりました。多くの面白い方にも影響を受けました。特に影響を受けたのが、入院当時に隣のベッドだったおっちゃんです。糖尿病で両目の視力を失っていたのに、やけに明るいおっちゃんでした。外で歩行訓練をしていた時にたまたま見かけて「今日、外で歩いていましたね。」と言うと「支援員さん美人でしょ?エヘへ!」と返して来ました。「オイ、おっちゃん!アンタ見えてないから。」と突っ込んでおきましたが、どこ吹く風って感じでした。この頃の私は、退院してからの生活を想像出来ませんでした。地方の病院でもう何年かリハビリを…なんて話しもありました。塞ぎ込む程ではなかったのですが、このおっちゃんを見ていると「まあ、どうにかなるか。」と思えて来ました。この「どうにかなるか」の緩い考えは、今の相談支援にも役立っています。どうにかしようと思えば、完璧ではないのですが希望に近い形になる事が多々あります。
1年半ほどの入院とリハビリの生活をして、今の家には2002年の夏に引っ越して来ました。運良く、高校時代の親友が建築関係の仕事をしていたお陰で、設計士さんからハウスメーカーまで紹介してくれて、バリアフリーの一軒家に住める事になりました。二世帯住宅で、私の両親は1Fに、私達夫婦は2Fに住み、ホームエレベーターを設置しました。このホームエレベーターが意外な展開になりました。
何とか生活にも慣れてきて、妻が犬を飼いたい…云々と言い出したのが翌年の始め頃でした。私も動物が好きだったので、特に異論も無くGWに保護犬を引き取る事になりました。名前を岳(ガク)と付けたのですが、この岳が妙に頭が良いと言うか、ずる賢いと言うか…。エレベーターの使い方を分かっているのか、1Fで私が乗ろうとすると狭い車椅子の横の隙間に潜り込み、2Fに着くと当たり前の様に先に降りて行く始末でした。結果として、老犬になり足腰が衰え階段が登れなくなった頃には、逆にこの性格が助かったのですか…。
この辺りから「どうにかなるか」の楽観主義が、家族間では「どうにもならない」事に気付き始めました。五代徳川将軍の綱吉公は犬将軍なんて揶揄されたとか…まさにウチのお犬様も特別待遇の始まりです。自分の気が乗った時には普通に階段を行き来するのに、気が乗らない時はエレベーターの前で扉を見て待っています。仕方無くエレベーターのボタンを押してドアを開けると、自分からスタスタと乗って行きました。そして2Fに着くと何の違和感も無く当然の様に降りて来ます。家族も最初は渋々だったのが徐々に当たり前となって行き、いつの間にか当然の権利となって行く…習慣とは怖ろしいものです。
綱吉公の生類憐みの令は元々日本初の福祉政策(=車椅子の私のための我が家のバリアフリー)だったとか?それが徐々に暴走してしまったとか?我が家にもお犬様の特別待遇が暴走して行きます。
2013年の1月に長男が誕生しました。ここから「生類憐みの令」の暴走の始まりです。お犬様は「長男>自分>私達」…特にお犬様は長男優遇の姿勢が露骨です。お犬様が寝ている所に長男が行っても仲良く甘えているのですが、妻が同じ事をすると牙を剥き出しにして威嚇して来ます。まさに「切り捨て御免!」。そして、10歳を超えた老犬に、家族は今更しつけだ何だと求める事も無いまま、この関係は当然となって行く…自然と上下関係は定着して行きます。この露骨な身分制度は、お犬様が亡くなる2019年まで続きました。
綱吉公の「生類憐みの令」は人にも生き物にも優しい社会作りがスタートでしたが、我が家は「生類甘やかしの悪例」でした。次に犬を飼う事があれば、人にも優しい「共生社会」になって欲しいと思っている、今でも甘い考えの私です。
*
この連載では、頸椎損傷で車椅子生活を送る私が、老若男女のさまざまな 「生類」と共生する(した)中で経験したこと、感じたことを綴っていきたいと思います。皆さんも『あるある!』と共感して頂ければ嬉しいです。

障害者相談支援専門員
2000年12月に受傷。
大井競馬場で競走馬のウォーミングアップ中に落馬し頸椎を脱臼骨折、頸髄損傷で車椅子生活となりました。
1年半ほどの入院生活を経て、2002年8月に退院し、町田市で生活を始めました。
5〜6年ほど家族介護で生活していましたが、友人よりヘルパーサービスの利用を薦められ利用を開始しました。
これに合わせて訪問看護も利用を開始し、家族介護主体から医療・福祉サービス主体の生活になって行きました。
2008年7月に受傷後初めて仕事に就きました。
内容は主にデータ入力と電話対応で、週2日の出勤と在宅ワークで作業を行っていました。
2012年9月に現在の仕事に就きました。
業務は、役所が福祉サービス支給の判断基準にする資料、サービス等利用計画の作成です。
当時は障害者自立支援法から障害者総合支援法への移行時期でもあり、福祉サービスの変化も多々ありましたが、日常生活では比較的安定して重度訪問介護のサービスを利用出来ています。
2013年1月に長男が誕生しました。
現在小学校1年生で、学校の運動会や授業参観、休日にはサッカーの試合に付き添うなど、行事には出来る限り参加しています。
身体に正常に機能しない部分がある。その箇所が同じだと、そのような人たちは、よく顔を合わせることになる。例えば病院で、学校で、団体で、役所などで。それとは少し異なるが、実生活が関係してきても、直面する社会的障壁が同じ人とはよく顔を合わせることになる。この場合は、自分の体に抱える障害が同じでなくてもよい。例えば車いすを使う人は、車いすを使うがゆえに生活がしにくいところが同じである。こういった人とも話をする機会が多くなる。場所はやっぱり病院、学校、団体、役所などだ。
障害に直面して生きていると、意図的であるか否かに関わらず、こんな形で障害者の知人は増える。身体に正常に機能しない部分があると、生物として生きることにも制約となることが多い。だから、障害者の寿命は健常な人と比べると平均的に短い。結果として、障害者は多くの知人の死に直面する。僕はそのように思っている。あたりまえだけど、知人が死ぬことは辛いことだ。しかしながら、車いすユーザーは通常冠婚葬祭には参加できない。この点は、バリアフリーの議論で見落とされている部分でもある。皮肉なことなのかもしれないけれど、こういった事情があることで知人の死に直面した時の僕の考え方は(自分では悪くはないと感じるような形で)変化してきている。自分が健常者だったときと比較すると、辛い気持ちが先に立つというよりはむしろ、その人の志をくみ取って生きていこうと思うようになってきたのだ。こういったことに直面した時、僕は意外に冷静にもなった。でも、金子能宏先生の訃報を知った時、僕は(障害者となった後では多分初めて)取り乱した。理由はよくわからない。まとまった文章が書けるのかどうかが不安ではあるが、先生に希望をもらった一人として、先生との思い出を追悼文としたい。
金子能宏先生(以下、能宏先生と記述する)と僕との出会いは、20年ほど前にさかのぼる。当時僕は、東京の大学の大学院で経済学を勉強しており、障害問題を経済学的に分析しようと考えていた。しかし、研究を行ったこともない一大学院生が、何から手を付けていいのやらわかるわけがない。とにかく何でもいいから「障害」なるものを扱った経済学研究を探そうとEconlit(経済学研究のデータベース)で「Disability」と入力しても何もヒットしない。当時は今のように情報が迅速に入手できなかった。Econlit もCDである。そんな時代だった1(Oiをはじめ、脚注で書いた論文以外の文献が当時存在しなかったわけではない。当時の僕の検索の仕方も悪かったのかもしれないが、少なくとも数が少なかったことは間違いない)。でも当時の僕は、障害問題は経済学で扱うからこそ意味があると思っていたし、今でもそう思っている。しかし、僕程度の人間が思うことと同じことを考える人がいないはずがない。どのように扱うかはさておき、障害問題が経済学で扱われていないわけがないだろう。そのように思って図書館にこもっていた。そのころ当時の指導教授が「経済学会に行ってみたらどうだ」とおっしゃってくれた。当時の僕は手動車いすで動いており、自己導尿を行っていたため、身近に介助者がいないと、いざというときに困る状況だった。そこで、母親同伴で当時入寮させていただいていた大学の学生寮から出て、一橋大学で行われていた日本経済学会に参加した。
学会では、医療経済学の研究報告を聞いていた。午後のセッションが終了して、学外でお茶を飲んでいた母親との待ち合わせ場所で待っていた時、同じ車いすにのった小さいおじさんが声をかけてきてくれた。「どこの子?」と聞かれたので、大学名を答えた。丁度そのとき母親が来た。後から聞いた話だが、母親にはそのおじさんがすごく偉く見えたらしい。僕がどうしてそんなに偉い人と話しているのか不思議に思いながらも、失礼があってはいけない、と緊張したそうだ。冷静に考えると、そう見えることが普通だったのかもしれない。実際大会運営者らしい人や経済学者らしい方々は、みんなおじさんに頭を下げていくし、一部の人とは、「少しお待ちください」、「ああ、いいよ。先にゲラ送るからゲラ」とかいうお話をされてもいた。それらの方々とのお話し中にはおじさんは確かに目上の人だったからである。でも僕は、大学で障害者に会うことはほとんどなかったし、経済学研究でも障害者にまつわる諸問題の研究を行う人はいないのではないか?と勝手に思っていたので、関係者らしき人に会えて少しワクワクしていた。おじさんに緊張することがなかった理由はそれだけではない。そのおじさん=能宏先生が、すごくフランクに話してきてくれたからでもある。後から感じたことでもあるが、能宏先生はおしゃべりな人ではない。僕が感じた温かさは、先生の自身の経験からくる他人へのやさしさと、同じ車いすユーザーへの配慮、そして何よりも先生の人間性が現れたものだと思う。
話し始めてから数分程度で僕の状況をいち早く察した先生は、自分の体験談を話してくださった。先生も母親に助けられながら一橋の大学院に行き、国家公務員総合職(旧一種)試験を複数回合格しながらもバリアフリーの不備を理由に断られたこと2。周りの方々、指導教授の理解があって今があること。アメリカに行った時の苦労話などもしてくれた。いずれも、僕ができたのだから頑張れば君にもできるよ、というメッセージが込められたお話しだった。母親に対しても、少なくとも先生が切り開かれて来た道には、いい人が多いから安心して大丈夫ですよ、と話してくださっている。この出会いで僕は先生にあこがれたし、先生のようになりたいと思った。良かれあしかれ母親も同じだったようだ。その後で僕は大阪大学に行って学位取得を目指すことになるのだが、母親の決まり文句が「能宏先生のようになりなさい」になったのだ。
大阪で学位を取ったころ、松井彰彦先生を代表とする障害と経済の研究プロジェクトが立ち上がったのを知った。だが、場所が東京だったため、僕は自分の研究に力を入れていた。偶然にもその時に、僕は研究報告の機会をいただいた。それがきっかけとなって、今も障害と経済の研究プロジェクトに参加させていただいている。後から聞いた話だが、僕の研究を紹介してくださったのも能宏先生だと伺った。一橋大学での出会いからずいぶんと時間を経ていたが、多忙なのにも関わらず、僕のことを覚えていてくださったことがとてもうれしかった。
このプロジェクトで僕がかかわっている部門は実証部門である。プロジェクト名がREADとなっていた時、第一回目の統計調査が完了して、そのデータを基にした一次的基礎分析結果を公開講座で報告したことがある。この時に僕は能宏先生とペアとなって報告を行った。報告では、障害者の労働供給と賃金プロファイルについての分析を報告したが、その内容は、一般雇用されている障害者の賃金プロファイルがフラットになっている実態を中心にしたものであった。障害と一口に言ってもその種類は多岐に及ぶ。種別によって直面する困難も多様だ。READで開催する公開講座では、どのような障害に直面していようとも、参加してくださった方々には報告が理解しやすいように手厚く配慮を提供する。例えば、視覚障害に直面されている方であれば、点字資料が準備されている。また、聴覚障害に直面されている方であれば、手話通訳や文字通訳などが準備される。このような配慮を提供する都合上、報告者はそれらに合わせた資料の作成とタイトな〆切制約がかけられる。僕と金子先生との報告に関していうと、内容は、僕が選択・準備などを担当して、能宏先生はチェックするという役割分担だった。
当時の僕は、視覚障害に直面される方や聴覚障害に直面される方に配慮した報告を経験したことがなかったため、資料作成にはずいぶん苦労した。賃金プロファイルは、年齢層を横軸に取り、縦軸に各年齢層の平均賃金をとったものをプロットすることで得られる。日本の常用雇用者をサンプルとした賃金プロファイルは、通常右上がりの形状を取り、定年年齢層を上回ると右下がりになる。賃金プロファイルがフラットになっていることは、経済学者であれば、パートタイム労働者の賃金プロファイルの形状と類似したものであることは理解できるし、それが持ついくつかのインプリケーションも同時に理解できる。しかし、経済学者以外が対象になると、追加的な情報と解説が必要になる。さらに、READで開催する公開講座で提供される配慮を考慮する必要もある。この点を考えると図表を使用した解説はなるべく少なくすべきだ。どう説明したものかな…と悩んでいた。〆切が迫ってきている中で、夜中の2時頃に能宏先生から一通のメールが届いた。そこには、日本の賃金プロファイルを表すのに通常使用される賃金センサスの公表データを用いた一般労働者の賃金プロファイルの図が添付されていた。
一般的に言えば、異なる調査による分析結果を比較することは危険だ。なぜかというと、調査によって標本の取り方が異なるからである。僕が読み取った、この図に込められた能宏先生のメッセージは次のようなものだ。「公開講座」という場において、最も重視すべきことはわかりやすさだ。厳密な議論は犠牲にしたとしても、READ調査で発見された事実を前面に打ち出して報告すべきだ。そのためには日本の平均的な常用雇用者の賃金プロファイルを使って、比較対象を明示的に示した方がよい。
どのように説明すべきか悩んでいた丁度その時、まるで僕が横にいて先生に相談したかのようなベストなタイミングで、的を得た助言が届いたのである。一聴すると当たり前のように聞こえるかもしれないが、公開講座で何を、どのように伝えるべきか、といったことは案外難しい。木も森も同時に見えていなければ、判断できないことが多いのだ。日本の障害研究・障害統計の現状をよくご存じで、READ調査や公開講座の意味を理解していなければ上のような判断はできない。先生の助言は、僕にとってはコロンブスの卵的な助言であり、タイミングの良さも手伝って、舌を巻いたことを強く覚えている。
この報告で、僕と能宏先生がメールで情報交換したのはこの一度だけである。この時、先生と連絡を取りたいこともあったが、全く取れない体験をした。この体験があって、先生の普通では考えられない忙しさを感じることができた。このころから徐々にわかってきたことであるが、能宏先生は、ご自分の抱えられている仕事にいつも全力で取り組まれていた。「当たり前」の全力ではなく、常に「そこまで?」と感じるくらいの全力である。普通と感じられることを普通にこなすことほど難しいことはない。多くの優秀な研究者は、このような特徴があると僕は思っている。多くの業務にまじめに、真摯に向き合っており、多忙であるからこそ、鋭い視点が保てると考えている。他人の評価や信頼などはそういったところから生まれてくるものだ。僕は先生に、どのような仕事に対しても、全力で取り組むことの大切さを教えていただいたと思っている。でも、僕らには残念ながら体の制約がある。この点については、後々先生とお話させていただいたことがある。健常な方であっても、過密スケジュールとなっている状況が継続するとどこかがおかしくなる。頭では仕事のことを考えられても、身体がついてこない。こういったときには往々にして無駄な作業をしていることも多くなる。自分の経験からも言えることだが、この状態で無理をすると、大きな犠牲を払うことになる。先生は「最近は僕も週に一日だけ休むようにしているよ。馬鹿みたいに寝てるの。」と話してくださった。この点も参考になっている。
先生が国立社会保障・人口問題研究所をおやめになり、一橋大学、日本社会事業大学で働かれるようになってからはほとんどお会いする機会もなかった。職場を変わることが身体に与える影響も大きかったのではないかと思う。先生は週に一日休まれていたのだろうか。僕は先生にいただいたものを大切にして、先生の志の一端でも担えるように頑張りたいと思う。
ご冥福をお祈りいたします。