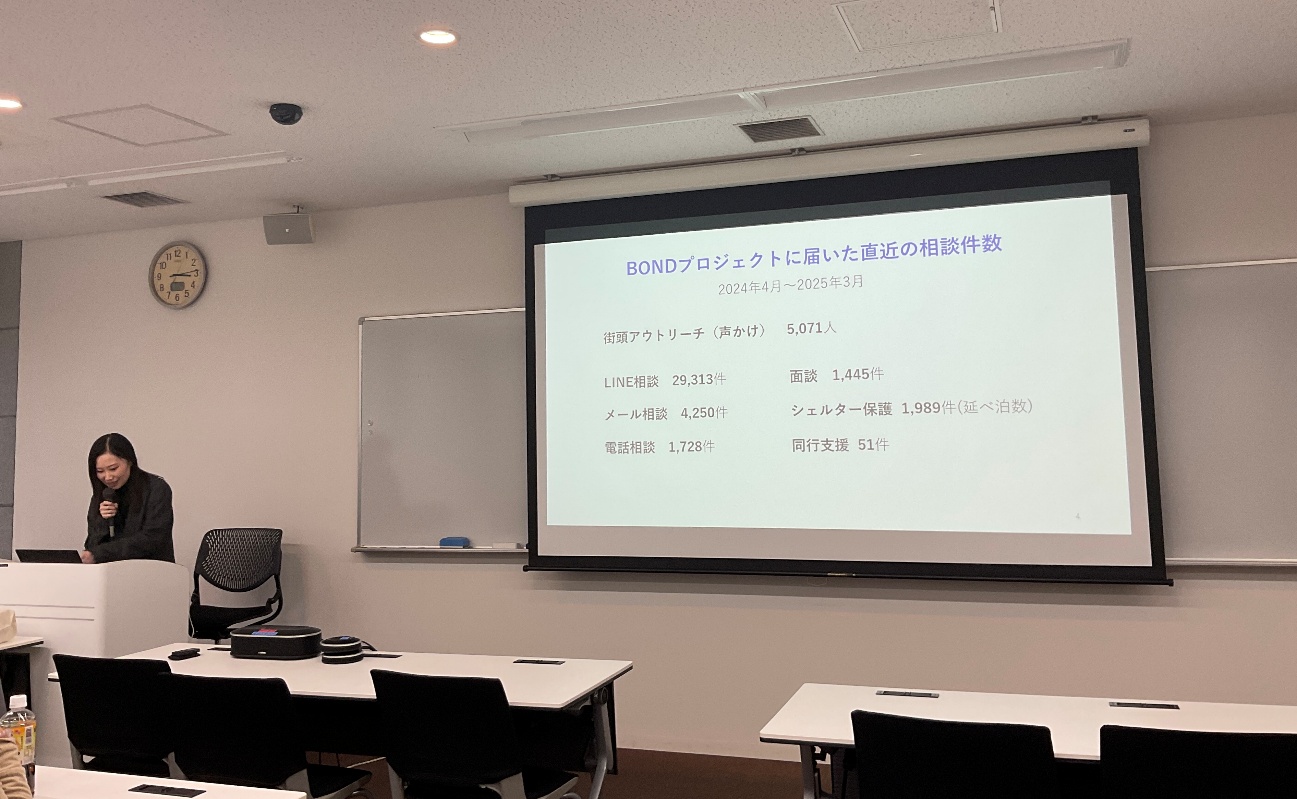REDDYの活動
2025年11月11日
精神障害のある女性のための研究会
第6回
精神障害のある女性のための研究会(2025年10月29日)開催レポート
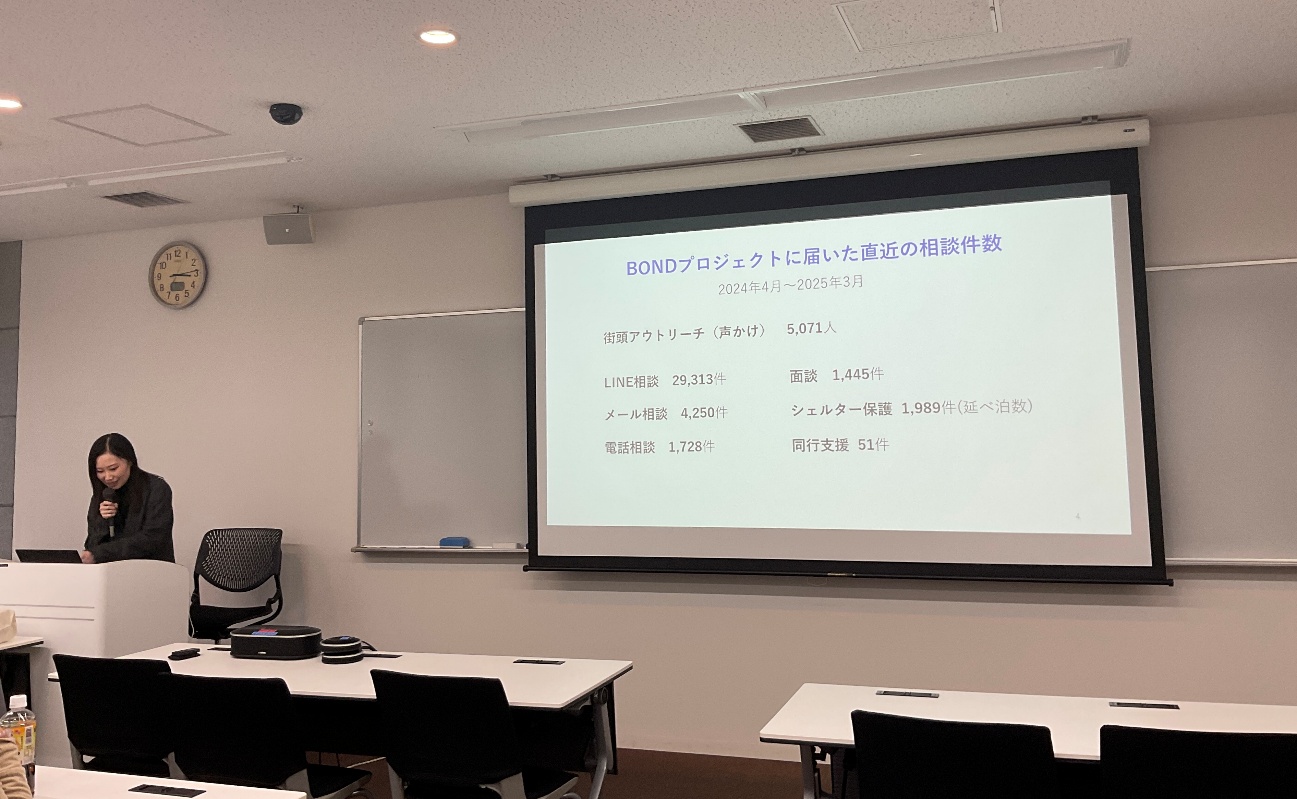
BONDプロジェクトさんをお呼びして、若年女性の支援について講義をしていただきました。
レポート本文続き
REDDYの活動:目次
〈活動分野〉
研究会・講演会
2025
2024
2023
2022
2019
2018
精神障害のある女性のための研究会
2025
2024
医療従事関連国家資格を有する聴覚障害者の就労実態に関する研究(2020)
2024
2023
2021
出張見学レポート
2025
2024
2023
災害が発生、そのとき障害者は
2022
2021
2020
特別講義
2022
東北地方の性的マイノリティ団体 活動調査報告書
2022